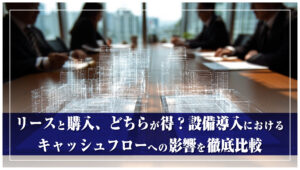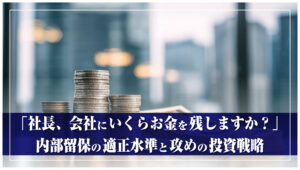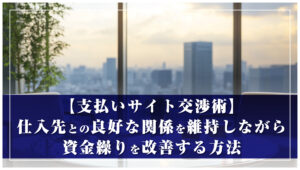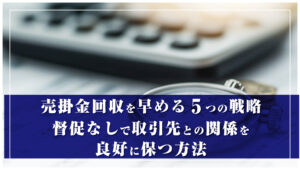「先月も売上目標を達成して黒字決算だったのに、なぜか銀行口座の残高が減っている…」
こんな経験はありませんか?
私は銀行員として7年、その後コンサルタントとして15年以上、多くの中小企業の資金繰りを見てきました。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆驚くべきことに、倒産企業の約半数は決算書上では「黒字」だったのです。
この「黒字なのにお金がない」状態を解決する強力な武器が「キャッシュフロー計算書」です。
この記事では、キャッシュフロー計算書の読み方と作り方、そして経営に活かすコツを専門用語を極力噛み砕いて解説します。
この記事を読めば、資金繰りの不安から解放され、自信を持って経営判断ができるようになるでしょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ今?キャッシュフロー計算書が中小企業経営に不可欠な理由
キャッシュフロー計算書(C/F)とは、一定期間における企業の「お金の流れ」を表す財務諸表です。
損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)と並ぶ「財務三表」の一つですが、中小企業では作成していないケースも多いのが実情です。
しかし、「利益」と「現金」は別物であるため、中小企業こそキャッシュフロー計算書を活用すべきです。
利益≠現金!「黒字倒産」のワナとは?
「黒字倒産」とは、決算書上は黒字なのに、資金繰りが行き詰まって倒産する事態です。
東京商工リサーチの過去の調査によれば、黒字決算でありながら倒産する企業、いわゆる『黒字倒産』の割合が年々増加傾向にあります。
具体的な数値は調査年度によって異なりますが、直近の調査では倒産企業の中で一定割合が黒字決算だったと報告されています。
黒字なのにお金がない主な原因
- 売上代金の回収が遅れている(売掛金の増加)
- 過剰な在庫を抱えている(棚卸資産の増加)
- 設備投資に資金を使ってしまった(固定資産の増加)
- 借入金の返済に資金を充てた(負債の減少)
「利益は意見、キャッシュは事実」という格言があるように、利益は会計処理によって変動しますが、現金の残高はごまかせない現実なのです。
月次決算で利益が出ていても油断は禁物です。特に成長期の企業は売上増→売掛金増→資金不足という連鎖に陥りやすいもの。毎月の資金繰り表とキャッシュフロー計算書の両方をチェックする習慣をつけることが、黒字倒産を防ぐ第一歩です。
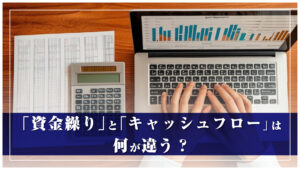
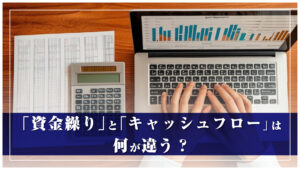
財務三表の役割分担:P/L・B/SとC/Fの関係性
財務三表はそれぞれ異なる視点から企業の状態を表しています。
財務三表の役割と関係性
| 財務諸表 | 役割・見えること | 例えるなら |
|---|---|---|
| 損益計算書(P/L) | 「儲け」(収益-費用) | 企業の「筋力・体力」 |
| 貸借対照表(B/S) | 「財産状態」(資産-負債) | 企業の「体格・体型」 |
| キャッシュフロー計算書(C/F) | 「お金の流れ」 | 企業の「血流・循環器系」 |
これらは互いに連動しています。
例えば、P/Lで利益を計上すると、B/Sでは資産が増加しますが、その資産が「現金」なのか「売掛金」なのかによって実際のお金の流れは大きく変わります。



銀行融資の審査では、P/LとB/Sだけでなく、C/Fも重視されています。
なぜなら、返済原資となるのは「利益」ではなく「現金」だからです。
作成義務はなくてもメリット大!中小企業こそC/Fを作るべき理由
法律上、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられているのは上場企業などの大会社だけです。
しかし、中小企業こそキャッシュフロー計算書を作成するメリットは大きいのです。
中小企業がキャッシュフロー計算書を作るべき理由は以下になります。
1. 資金繰り予測の精度が上がる
- 過去の現金の流れを分析し、将来の資金ショートを回避
2. 銀行融資が受けやすくなる
- 返済能力への信頼度が高まり、融資条件の交渉も有利に
3. 経営判断の質が向上する
- 投資回収や資金繰り圧迫要因が明確になり、対策が打てる
4. 黒字倒産を防げる
- 利益と現金の乖離を早期に発見し、適切な手を打てる
私のクライアント企業では、キャッシュフロー計算書の作成で売掛金回収の遅れに気づき、回収条件の見直しで資金繰りが大幅に改善したケースもあります。
これで安心!キャッシュフロー計算書の基本的な読み方
キャッシュフロー計算書は一見複雑に見えますが、基本構造を理解すれば誰でも読めるようになります。
💡 キャッシュフロー計算書の3つの区分
- 営業活動によるキャッシュフロー:本業での現金の増減
- 投資活動によるキャッシュフロー:設備投資や資産売却などによる現金の増減
- 財務活動によるキャッシュフロー:借入や返済、増資などによる現金の増減
この3つの区分を足し合わせると、当期の「現金の増減額」になり、これに期首残高を加えると期末残高となります。
営業活動キャッシュフロー:本業で稼ぐ力をチェック
営業活動によるキャッシュフロー(営業CF)は、企業の本業での現金創出力を表す最も重要な指標です。
営業CFのポイント
- プラス:本業で現金を生み出せている(健全)
- マイナス:本業で現金が減っている(要注意)
マイナスの主な原因
- 売掛金の増加(売上増加だが未回収)
- 在庫の増加(商品は作ったが未販売)
- 本業そのものの不振
いくら利益が出ていても、営業CFがマイナスなら「返済原資が生まれていない」状態です。
投資活動キャッシュフロー:将来への投資状況を見る
投資活動によるキャッシュフロー(投資CF)は、設備投資や資産売却など、将来のための投資活動による現金の増減を表します。
💡 投資CFの読み方
- マイナス:設備投資や資産取得(成長投資なら健全)
- プラス:資産売却(事業整理・リストラの可能性)
営業CFがプラスで投資CFがマイナスという組み合わせは、「本業で稼いだお金を将来に投資している」という健全な状態です。
ただし、投資CFのマイナスが営業CFを大きく上回る場合は、外部資金に頼らざるを得なくなるため注意が必要です。
財務活動キャッシュフロー:資金調達と返済の動きを知る
財務活動によるキャッシュフロー(財務CF)は、借入・返済や株式発行、配当支払いなどによる現金の増減を表します。
💡 財務CFのポイント
- プラス:資金調達(借入増加、増資など)
- マイナス:返済や配当で現金が減少
財務CFの読み方で最も重要なのは、営業CFとの関係性です。
危険な組み合わせ:「営業CFマイナス × 財務CFプラス」
これは「本業で現金が減り、借入で穴埋めしている」状態で、「借金で借金を返す自転車操業」の始まりかもしれません。
健全?危険?キャッシュフローの典型パターン
3つのキャッシュフローの組み合わせから、企業の状況を判断できます。
代表的なパターン
| パターン | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 企業状況 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | – | – | 健全成長型 | ◎ |
| 2 | + | – | + | 積極投資型 | ○ |
| 3 | – | – | + | 成長痛型 | △ |
| 4 | – | + | + | 資金調達型 | × |
健全成長型(営業+/投資-/財務-)
- 本業で稼いだ現金で投資と返済をまかなう理想的な状態
積極投資型(営業+/投資-/財務+)
- 本業は好調だが、より大きな投資のために資金調達
成長痛型(営業-/投資-/財務+)
- 成長過程で一時的に本業の現金が不足
- 短期的には許容できるが長期化すると危険
資金調達型(営業-/投資+/財務+)
- 本業の赤字を資産売却と借入でカバー
- 「黒字倒産予備軍」の可能性が高い
キャッシュフローパターンは3〜5年の推移をチェックすることが重要です。特に「営業CFのマイナスが続く」「財務CFのプラスで営業CFのマイナスを埋め続けている」状況は黒字倒産の前兆かもしれません。
【実践】中小企業向けキャッシュフロー計算書の作り方(間接法)
ここからは、中小企業が自社でキャッシュフロー計算書を作成する方法を解説します。
一般的な「間接法」を中心に説明します。
これは損益計算書と貸借対照表から比較的簡単に作成できるため、中小企業に適しています。
準備するもの:これだけあれば作れる!
🔍 必要な資料
- 前期末の貸借対照表(B/S)
- 当期末の貸借対照表(B/S)
- 当期の損益計算書(P/L)
🔍 あると便利な補助資料
- 減価償却費の明細
- 固定資産の増減明細
- 借入金・社債の増減明細
🔍 作成に必要な時間とスキル
- 初めての場合:半日程度
- 慣れてくると:1〜2時間程度
- 必要なスキル:基本的な決算書の読み方、エクセルの基礎知識
ステップ解説:営業キャッシュフローの計算(間接法)
間接法による営業CFの計算は、「税引前当期純利益」から始めて「現金の増減」に調整していく方法です。
営業キャッシュフロー計算の基本ステップ
1. 税引前当期純利益を起点とする
2. 非資金項目の調整
- 減価償却費(加算)
- 引当金の増減(増加なら加算、減少なら減算)
3. 運転資本の増減調整
- 売上債権の増減(増加なら減算、減少なら加算)
- 棚卸資産の増減(増加なら減算、減少なら加算)
- 仕入債務の増減(増加なら加算、減少なら減算)
減価償却費を加算する理由
減価償却費は現金支出を伴わない費用のため、キャッシュフロー計算では加算します。
例:税引前利益1,000万円+減価償却費200万円=キャッシュベースでは1,200万円
売上債権増加を減算する理由
売掛金が増加した場合、その分は売上計上されても現金回収されていないため、利益から差し引きます。
例:税引前利益1,000万円-売掛金増加300万円=現金収入は700万円
ステップ解説:投資・財務キャッシュフローの計算
投資活動によるキャッシュフローの計算
投資CFは主に以下の項目で構成されます。
- 有形固定資産の取得による支出(マイナス)
- 有形固定資産の売却による収入(プラス)
- 投資有価証券の取得・売却
計算方法は、前期末と当期末の貸借対照表を比較し、該当科目の増減額を把握します。
財務活動によるキャッシュフローの計算
財務CFは主に以下の項目で構成されます。
- 借入金の増減額(借入れはプラス、返済はマイナス)
- 社債の発行・償還
- 株式の発行・自社株買い
- 配当金の支払額(マイナス)
例:借入金の計算
前期末の長期借入金が5,000万円、当期末が4,000万円、期中に新規借入2,000万円があった場合:
- 財務CFでは「長期借入れによる収入2,000万円」「長期借入金の返済による支出△3,000万円」と表示
検算と完成:数字が合えばOK!
3つのキャッシュフローが計算できたら、最後に検算を行います。
検算方法
- 3つのCFを合計 = キャッシュフロー合計(現金等の増減額)
- 期首の現金 + キャッシュフロー合計 = 期末の現金
- 計算結果が貸借対照表の現金預金と一致するか確認
もし一致しない場合は、どこかに計算ミスや見落としがあるサインです。
キャッシュフロー計算書の完成形式
キャッシュフロー計算書
自 20XX年4月1日 至 20XX年3月31日
I. 営業活動によるキャッシュフロー
税引前当期純利益 XXX
減価償却費 XXX
売上債権の増減額(△は増加) XXX
棚卸資産の増減額(△は増加) XXX
仕入債務の増減額(△は減少) XXX
営業活動によるキャッシュフロー XXX
II. 投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の取得による支出 △XXX
有形固定資産の売却による収入 XXX
投資活動によるキャッシュフロー XXX
III. 財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金の増減額 XXX
長期借入れによる収入 XXX
長期借入金の返済による支出 △XXX
財務活動によるキャッシュフロー XXX
IV. 現金及び現金同等物の増減額 XXX
V. 現金及び現金同等物の期首残高 XXX
VI. 現金及び現金同等物の期末残高 XXX作るだけじゃもったいない!キャッシュフロー計算書を経営に活かす方法
キャッシュフロー計算書を作成することは目的ではなく、手段です。
ここからは、作成した計算書を経営に活かす具体的な方法を紹介します。
未来を読む!資金繰り予測(資金繰り表作成)への応用
キャッシュフロー計算書は過去の実績ですが、これを基に「将来の資金繰り予測」を立てることができます。
キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い
| 項目 | キャッシュフロー計算書 | 資金繰り表 |
|---|---|---|
| 目的 | 過去の現金の分析 | 将来の現金の予測 |
| 期間 | 年次・四半期(過去) | 月次・週次・日次(未来) |
| 重視点 | 3区分(営業・投資・財務) | 入金・出金のタイミング |
資金繰り表作成の手順
❶過去のキャッシュフローパターンを分析
- 売上に対する回収サイトの実績
- 仕入から支払いまでの期間
- 季節変動と固定費の支出タイミング
❷将来の売上・仕入予測と入出金タイミングを予測
❸資金不足が予想される時期を特定し対策を立てる
私のクライアント企業では、資金繰り表を作成したことで毎年2月に一時的な資金不足が発生することが分かり、事前準備で乗り切ることができました。
銀行交渉を有利に進める武器にする
銀行が融資審査で最も重視するのは「返済能力」、つまり将来のキャッシュフローです。
キャッシュフロー計算書を活用した銀行交渉術
1. 自社分析を事前に行う
- 強みと弱みを把握
- キャッシュフロー上の課題と対策を準備
2. 返済能力を具体的に示す
- 営業CF÷年間返済額=返済余力倍率
- 過去の返済実績とキャッシュフロー改善状況
3. 資金使途とキャッシュフロー改善効果を紐づける



ある製造業のクライアントは、キャッシュフロー計算書を分析して「本業の稼ぐ力は十分ある」ことをアピールした結果、追加融資と金利引き下げを実現できました。
🔍 銀行が評価するキャッシュフロー改善策
┗ 売掛金の回収サイト短縮
┗ 在庫の適正化
┗ 固定費の削減
┗ 返済条件の見直し
投資判断の精度を高める:本当にその投資は回収できるか?
投資判断においても「投資回収期間」と「フリーキャッシュフロー」の考え方が重要です。
投資判断のためのキャッシュフロー分析
1. フリーキャッシュフローの把握
- フリーキャッシュフロー = 営業CF + 投資CF
- プラスなら投資余力あり、マイナスなら外部資金が必要
2. 投資回収期間の計算
- 投資金額 ÷ 年間の営業CF増加見込額
- 目安:3〜5年なら良好、7年以上なら要検討
3. 投資後のキャッシュフローシミュレーション
- 短期的な資金不足が生じないかチェック
中小企業では「社長の勘」だけで投資判断するケースも多いですが、キャッシュフロー計算書を活用した冷静な判断が投資の成功確率を高めます。
会社の状況別!キャッシュフロー改善のヒント
黒字だが資金繰りが厳しい企業
- 営業CFの改善策
- 売掛金回収の早期化
- 仕入・支払条件の見直し
- 在庫削減
- 前受金の活用
- 投資CFの改善策
- 不要不急の設備投資の延期
- 財務CFの対策
- 借入金の借換え(長期化)
積極的に成長投資したい企業
- 営業CFの強化策
- 利益率向上
- 運転資本効率の改善
- 投資CFの効率化
- 投資の優先順位明確化
- 段階的投資計画
四半期ごとにキャッシュフロー計算書を作成し、数値の変化をチェックしましょう。「営業CF÷売上高」という比率を経営指標として導入すると、売上1円あたりどれだけのキャッシュを生み出せているかが分かります。
もっと手軽に!キャッシュフロー計算書作成に役立つツール
「キャッシュフロー計算書は大切そうだけど、作成するのは難しそう…」
こう感じる経営者も多いでしょう。しかし、近年では作成を支援するツールが充実しています。
無料で使える!中小企業庁提供のExcelテンプレート
中小企業庁では「キャッシュフロー計算書の簡易作成ツール(Excelファイル)」を無料で提供しています。
中小企業庁の簡易作成ツールの特徴
- 完全無料で使用可能
- シンプルな入力フォーム(白色のセルに入力するだけ)
- 自動計算機能で手計算の手間が省ける
- 間接法と直接法の両方に対応
入手方法:中小企業庁のウェブサイト「中小企業の会計」ツール集からダウンロード
基本的な決算書の読み方さえ分かれば使用できるので、まずはこれから始めてみることをお勧めします。
会計ソフト連携で自動作成も可能に
最近のクラウド会計ソフトでは、キャッシュフロー計算書を自動作成する機能を備えているものが増えています。
キャッシュフロー計算書に対応した主な会計ソフト
- freee(フリー)
- マネーフォワード クラウド会計
- 弥生会計
- その他多数
会計ソフトのメリット
- 完全自動化:手作業による計算ミスがなくなる
- リアルタイム性:月次・四半期ごとに自動更新
- グラフ化・分析機能:視覚的に把握しやすい
適切な仕訳入力がされていないと精度が下がるため、日常の会計処理の正確性が重要です。
困ったときは専門家(税理士・コンサルタント)に相談
自社での作成が難しい場合や、より専門的な分析・アドバイスが欲しい場合は、専門家への相談も選択肢の一つです。
相談できる専門家
- 税理士:決算書作成と合わせてキャッシュフロー計算書も依頼
- 中小企業診断士:経営全般のアドバイスとともに資金面も相談
- 資金繰りコンサルタント:キャッシュフロー改善に特化したアドバイス



外部専門家の最大の価値は「客観的な視点」です。
社内では気づかない問題点や改善機会を発見できることも少なくありません。
費用の目安
- 税理士によるキャッシュフロー計算書作成:5〜10万円程度/回
- キャッシュフロー分析・改善コンサルティング:10〜30万円程度/回
資金繰り改善によるリターンを考えれば、十分に投資価値のある金額と言えるでしょう。
よくある質問(FAQ)
キャッシュフロー計算書について、経営者の方からよく質問される内容にお答えします。
Q: 利益が出ていればキャッシュフローは気にしなくても良い?
A: いいえ、決してそんなことはありません。
利益が出ていても現金が足りなくなる「黒字倒産」は珍しくありません。
東京商工リサーチの調査によれば、倒産企業の約半数は決算書上「黒字」だったというデータもあります。
利益は会計上の概念であり、実際の現金の動きとは一致しません。
売掛金の回収遅れや在庫増加、設備投資、借入返済など、様々な要因で利益と現金の動きにズレが生じます。
特に成長期の企業は売上増加に伴い運転資金も増えるため、黒字でも資金ショートのリスクが高まります。
「利益と現金は別物」という認識を持ち、両方をしっかり管理することが経営の基本です。
Q: キャッシュフロー計算書と資金繰り表はどう違うのですか?
A: キャッシュフロー計算書と資金繰り表は、目的と視点が異なります。
キャッシュフロー計算書は「過去の一定期間における現金の増減の実績を分析するもの」で、財務諸表の一つです。
一方、資金繰り表は「将来の現金の収支を予測・管理するためのツール」で、主に社内管理用の資料です。
簡単に言えば、キャッシュフロー計算書は「なぜこうなったか」を分析するもの、資金繰り表は「これからどうなるか」を予測するものです。
両者は互いに補完し合う関係にあります。
過去のキャッシュフローの分析結果は将来の資金繰り予測の精度を高め、資金繰り表の実績と予測の差異は次のキャッシュフロー分析の視点になります。
経営者は両方を活用することで、より確かな資金管理ができるようになります。
Q: 作成はどのくらいの頻度でするべきですか?
A: 法律上は年1回(決算時)で十分ですが、経営管理の観点からは四半期ごと、できれば月次での作成・分析をお勧めします。
資金繰りの問題は突然現れるわけではなく、徐々に悪化していくものです。
年1回だけでは問題の兆候を見逃し、対応が遅れる恐れがあります。
四半期ごとの作成であれば、3ヶ月単位でキャッシュフローの傾向を把握でき、早めの対策が打てます。
余裕があれば月次での作成が理想的です。
特に以下のような企業は頻度を高めるべきでしょう。
- 成長が急激な企業
- 季節変動が大きい業種
- 資金繰りが逼迫している企業
- 大型投資を控えている企業
近年はクラウド会計ソフトなどのツールで自動作成も可能になっているため、手間を最小限に抑えつつ、定期的な分析ができるようになっています。
まとめ
キャッシュフロー計算書は、「利益」と「現金」のズレを明らかにし、企業の資金創出力を把握するための強力なツールです。
この記事では、キャッシュフロー計算書の重要性、基本的な読み方、作成方法、そして経営への活かし方を解説しました。
「黒字なのにお金がない」という状況は珍しくありません。
売掛金の増加、在庫の積み増し、設備投資など、利益は出ていてもキャッシュが減少する要因は多岐にわたります。
キャッシュフロー計算書を理解し活用することで、資金繰りの危機を事前に察知し、適切な対策を打つことができます。



今日からできるアクションとしては、まず中小企業庁の無料Excelテンプレートを使って自社のキャッシュフロー計算書を作成してみることをお勧めします。
銀行員そして資金繰りコンサルタントとしての経験から断言できますが、キャッシュフロー経営は、不確実性の高い時代を生き抜くための必須スキルです。
現金の流れを正確に把握し、将来を見据えた経営判断ができれば、黒字倒産の不安から解放され、より自信を持って事業に打ち込むことができるでしょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる