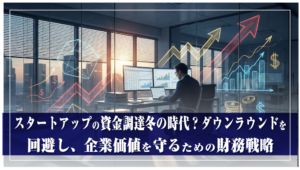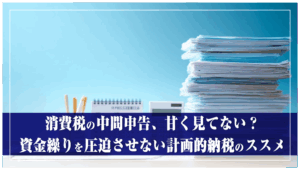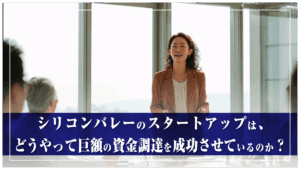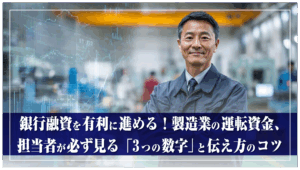「担保にできる不動産がないせいで、急ぎの仕入資金が用意できずチャンスを逃していませんか?」――そんな資金繰りの悩みを抱える中小企業の経営者・財務担当者へ。
この記事では、眠っている在庫や売掛金を“即戦力の現金”に変えるABL(動産・売掛金担保融資)の仕組みと活用手順、つまずきがちな落とし穴までを具体例つきで解説します。読み終えた頃には、
- 自社資産の何%を資金化できるか
- 銀行・信用金庫へ持参すべき書類と準備のコツ
- ファクタリングよりコストを3〜5%下げる方法
がクリアに分かり、明日の打ち合わせからすぐ動き出せるはずです。
【この記事の結論】ABL(動産・売掛金担保融資)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ABLとは? | 在庫や売掛金といった「事業資産」を担保にする融資。不動産担保や個人保証に依存しない資金調達が可能。 |
| 主なメリット | 不動産がなくても融資枠を拡大でき、ファクタリングより低コスト(金利3〜8%程度)で資金調達できる。 |
| 主なデメリット | 資産評価や登記に手間と時間がかかる。融資後も在庫状況などの定期的報告(モニタリング)が必要。 |
| 向いている企業 | 在庫や売掛金が多い製造業・卸売業や、事業拡大を目指す成長企業、不動産担保が不足している企業。 |

💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ABLの基本と仕組み
ABLとは何か?――企業版”質屋”のイメージで理解
ABL(Asset Based Lending)とは、商品在庫や売掛金など流動性の高い事業資産を担保として活用する融資手法です。
従来の不動産担保融資と異なり、企業の事業そのものに着目する金融手法として注目されています。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆簡単に言えば「企業版の質屋」のようなイメージです。
例えば、季節商材を扱う企業が次のシーズンに向けた在庫を抱えている場合、その在庫を担保にして仕入資金を調達できます。
あるいは、大企業への納品後、入金までの期間が長い中小企業が、その売掛金を担保に運転資金を確保するといった使い方が可能です。
特に重要なのは、ABLでは「生きている担保」を使うという点です。
つまり、企業努力によって担保の質や量が変わる性質を持った資産を活用するのです。
💡 ABLの基本的な仕組み
- 企業が保有する在庫や売掛金などに金融機関が譲渡担保権を設定
- 金融機関は担保評価に基づいて融資を実行
- 企業は通常の営業活動を継続しながら、定期的に担保状況を報告
- 返済完了後、譲渡担保権を解除
ABLが注目される理由――法改正と政策支援の追い風
近年、ABLが注目されている背景には、いくつかの制度面での追い風があります。
まず、債権法改正により、債権譲渡の対抗要件が整備され、ABLの法的安定性が高まりました。
また、信用保証協会によるABL保証制度の導入により、金融機関のリスク許容度も向上しています。
さらに金融庁が中小企業の経営改善や事業再生支援策として、ABLの積極活用を推進しているのも大きな要因です。
これにより、各金融機関もABLへの取り組みを強化しており、中小企業にとっては資金調達の選択肢が広がっているのです。
特に昨今の経済環境下では、次のような企業のニーズに応える手法として重宝されています。
- 事業の急成長に伴い、従来の融資枠では足りない企業
- 不動産担保に依存せず多様な資産を活用したい企業
- 返済条件変更中でも新たな資金調達を必要とする企業
ほかの資金調達との位置づけ
ABLと他の資金調達手法との違いを理解しておくことは重要です。
以下の表で、ABLとファクタリング、プロパー融資の違いを比較してみましょう。
| 特徴 | ABL | ファクタリング | プロパー融資 |
|---|---|---|---|
| 資金調達の形態 | 借入(オンバランス) | 売却(オフバランス) | 借入(オンバランス) |
| 担保 | 在庫・売掛金など | なし(売掛金を売却) | 原則不要または不動産 |
| 金利/手数料 | 3〜8%程度 | 1〜10%程度 | 1.5〜5%程度 |
| 資金調達額 | 担保評価額の50〜80% | 売掛金額の80〜90% | 企業の信用力による |
| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月程度 | 数日〜2週間程度 | 2週間〜1ヶ月程度 |
| 向いている企業 | 在庫・売掛金が多い企業 | 早期資金化を求める企業 | 信用力の高い企業 |



重要なのは、ABLは「資産を売却する」のではなく「担保に入れる」という点です。
つまり、ファクタリングのように売掛金をオフバランス化するのではなく、あくまで借入としてオンバランスで処理します。
具体的に言うと、ファクタリングでは売掛金を売却するため、相手先に請求や回収業務が移りますが、ABLでは従来通り自社で回収業務を継続します。
これにより取引先に資金繰りの問題を悟られることなく資金調達ができるのです。
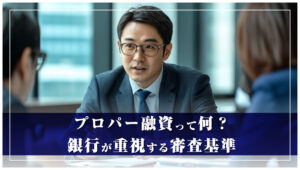
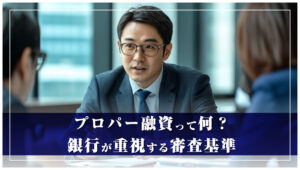
動産担保融資と売掛債権担保融資の違い
ABLは大きく分けて「動産担保融資」と「売掛債権担保融資」の2種類があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
動産担保融資(在庫・機械)の特徴
動産担保融資は、企業が所有する在庫や機械設備などの動産を担保とする融資方法です。
この場合、以下のプロセスが必要となります。
- 動産譲渡登記を行い、担保権を公示
- 評価会社による動産の査定・評価
- 定期的な在庫モニタリングの実施
動産担保融資の対象となる資産は実に多様です。
例えば、
- 商品在庫(食品、衣料品、電化製品など)
- 原材料(金属、木材、化学物質など)
- 機械設備(製造機械、建設機械など)
- 車両(トラック、フォークリフトなど)
私が銀行時代に関わった案件では、なんと牛や豚などの家畜を担保としたABLも実現しました。
このように担保対象が多様化しているのが動産担保融資の大きな特徴です。
ただし注意点として、動産は不動産と違って移動や変質が可能なため、モニタリングが重要になります。
特に在庫は日々変動するため、適切な管理体制が求められるのです。
売掛債権担保融資の特徴
売掛債権担保融資は、企業が保有する売掛金(取引先に対する代金請求権)を担保とする融資方法です。
この融資形態の特徴は次の通りです。
- 債権譲渡登記による担保権の設定
- 売掛先の信用力が重要な評価要素となる
- リボルビング方式(回転融資)が可能
売掛債権担保融資の最大のメリットは、売掛金の回収を待たずに資金化できることです。
例えば、大手企業への納品後、入金まで60日かかるケースでも、売掛債権を担保に即時資金調達が可能になります。
特に取引先の信用力が高ければ、担保評価も高くなる傾向にあります。
これは私がコンサル時代によく見た光景ですが、上場企業との取引がある中小企業は、その売掛金を担保に有利な条件で融資を引き出せるケースが多かったです。
- 通常の売掛金サイクル:
商品納入→請求書発行→支払期日→入金(60日後)- ABL活用時:
商品納入→請求書発行→ABL実行(即日)→支払期日→入金→ABL返済このように資金回収を前倒しできるのが大きな魅力です。
どちらを選ぶ?――業種・資産構成別判断フロー
動産担保と売掛債権担保、どちらが自社に合っているかは、業種や資産構成によって異なります。
以下のチェックリストを参考に最適なスキームを選びましょう。
在庫比率の高い企業(製造業、卸売業、小売業など)
- 商品在庫が多い → 動産担保融資
- 原材料在庫が多い → 動産担保融資
- 機械設備が充実 → 動産担保融資
売掛金比率の高い企業(サービス業、IT企業、建設業など)
- 大企業向け売掛金が多い → 売掛債権担保融資
- 公共事業の売掛金がある → 売掛債権担保融資
- 少数の大口取引先がある → 売掛債権担保融資
両方の比率が高い企業(総合商社、総合メーカーなど)
- 両方を組み合わせたハイブリッド型ABLも検討
これだけは押さえておきたいポイントとして、担保評価は「在庫」より「売掛金」の方が高くなる傾向があります。
なぜなら、売掛金は確定債権として現金化の確実性が高いからです。
在庫は変質や劣化、陳腐化のリスクがあるため、評価掛け目(担保価値の掛け率)が低めに設定されます。
ABLのメリット――資金繰り改善の切り札
ABLには多くのメリットがありますが、特に中小企業の資金繰り改善に役立つポイントを解説します。
不動産不要で調達枠を拡大
ABLの最大のメリットは、不動産担保や個人保証に依存せずに資金調達できる点です。
これにより多くの中小企業やスタートアップが直面する次のような課題を解決できます。
- 自社所有の不動産がない
- 既に不動産に担保が設定されている
- 個人保証の限度に達している
- 創業間もなく担保となる固定資産が少ない
実際、私が支援した家電販売業のA社は、創業5年目でリース店舗を使用していたため不動産担保がありませんでした。
しかし、在庫商品を担保としたABLを活用することで、年末商戦に向けた仕入資金2,000万円を調達できました。
これにより販売機会ロスを防ぎ、前年比120%の売上達成に貢献したのです。
金利・コストを抑えつつ迅速調達
ABLは無担保融資と比較して金利が低く設定される傾向があります。
また、ファクタリングのような高額な手数料も不要です。
以下は、1,000万円を調達する場合の費用比較シミュレーションです。
| 資金調達手法 | 金利/手数料 | 1,000万円調達時のコスト | 調達までの期間 |
|---|---|---|---|
| ABL | 年3〜5% | 年間30〜50万円 | 2週間〜1ヶ月 |
| ファクタリング | 一律5〜10% | 一律50〜100万円 | 数日〜2週間 |
| 無担保融資 | 年4〜8% | 年間40〜80万円 | 2週間〜1ヶ月 |
特に売掛金サイクルが短い企業(2〜3ヶ月程度)であれば、ファクタリングよりもABLの方がコスト効率が良いケースが多いです。
具体的に言うと、ファクタリングは一回の取引ごとに手数料が発生しますが、ABLは融資期間中の金利のみのため、複数回転するほどコスト優位性が高まります。
事業拡大・再建フェーズでの活用効果
ABLは特に次のような局面で効果を発揮します。
- 成長投資の資金確保:
急成長企業が次の投資資金を確保する際、既存の在庫や売掛金を活用できます。 - つなぎ資金としての活用:
大型案件受注時など、入金までの期間をつなぐ資金として役立ちます。 - 再生資金の調達:
金融支援中(リスケジュール中)でも、別枠での新規資金調達が可能です。
私がコンサルタントとして支援したIT企業B社の例では、リスケジュール中にもかかわらず、大手企業からの受注案件の売掛金を担保に開発資金を調達。
これが会社再建の足がかりとなり、2年後には通常の取引に復帰できました。
この事例からも分かるように、ABLは「最後の砦」としてではなく、事業再生の積極的な武器として活用できるのです。
内部管理体制の強化という副次的メリット
ABLを導入すると、金融機関から在庫や売掛金の管理体制構築を求められます。
これは一見、負担に思えるかもしれませんが、実は経営管理の高度化につながる大きなメリットです。
例えば、
- 在庫管理の可視化によるムダの発見
- 売掛金回収サイクルの最適化
- 商品回転率の向上
- 経営数値への感度向上
実際、私のクライアントである製造業C社では、ABL導入をきっかけに在庫管理システムを刷新。
結果として過剰在庫が20%減少し、キャッシュフローが大幅に改善しました。
つまりABLは単なる資金調達手法ではなく、経営改善の契機にもなり得るのです。
ABLのデメリットと注意点――失敗しないためのチェックリスト
ABLの魅力は分かっていただけたと思いますが、同時にいくつかの注意点も理解しておく必要があります。
審査・登記の手間と時間
ABLでは通常の融資より複雑な審査プロセスがあります。
特に初めて利用する場合は、以下のような手間と時間がかかることを想定しておきましょう。
- 担保となる資産の棚卸と評価:3日〜1週間
- 担保資産の価値査定:外部評価会社利用で5日〜2週間
- 登記手続き:司法書士経由で2日〜1週間
- 全体の審査期間:早くて2週間、通常は1ヵ月程度
また、評価費用として以下のコストが発生する場合があります。
- 動産評価費用:10万円〜数十万円
- 債権譲渡登記費用:債権額×0.2%+司法書士報酬
これらの時間とコストを考慮して、余裕をもったスケジュールで準備することが大切です。
掛け目・過剰担保リスク
ABLでは担保資産の価値に「掛け目」(掛け率)が設定されます。
一般的な掛け目の目安は以下の通りです。
- 売掛債権:評価額の70〜80%程度
- 在庫(商品):評価額の50〜70%程度
- 在庫(原材料):評価額の30〜50%程度
- 機械設備:評価額の50〜70%程度
例えば、時価1億円の在庫があっても、融資額は5,000万円程度になることがあります。これは担保資産の変動リスクや処分コストを金融機関が見込んでいるためです。
このギャップを理解せず資金計画を立てると、「思ったより借りられない」という事態に陥りかねません。
適切な資金計画を立てるためには、事前に金融機関と掛け目について確認しておくことが重要です。
モニタリング負荷と報告義務
ABLでは融資実行後も定期的なモニタリング報告が必要です。
具体的には以下のような報告が求められることが多いです。
- 在庫状況の報告:月次または四半期ごと
- 売掛金残高の報告:月次
- 担保資産の実地調査:半年または年次
この報告業務は企業側にとって負担になる可能性があります。
しかし、経理システムの整備や報告フォーマットの標準化により、負荷を軽減することも可能です。



私のクライアントであるアパレル企業D社では、Excelベースの月次報告テンプレートを作成し、担当者が30分程度で報告書を作成できる体制を整えました。
こうした工夫で継続的に対応できる体制を構築することが成功のカギです。
返済不能時の事業継続リスク
ABLでは返済不能となった場合、担保資産(在庫や売掛金)が処分される可能性があります。
これは事業継続に直結するリスクとなり得ます。
例えば、
- 在庫が処分されると → 販売できない
- 売掛金が差し押さえられると → 資金繰りが悪化
- 機械設備が処分されると → 生産ができなくなる
このリスクを回避するためには、次の対策が有効です。
- 無理のない返済計画を立てる
- 返済原資を複数確保しておく
- 資金繰り予測を精緻化する
- 早めに金融機関と相談する
私の経験上、問題が生じた際に早期に金融機関と相談した企業は、ほとんどの場合で債権者と協調して事業継続の道を見いだせています。
逆に隠して対応が遅れると、選択肢が狭まる傾向があります。
✅ ABL利用の注意点チェックリスト
- □ 審査・評価にかかる期間とコストを把握している
- □ 担保評価の掛け目(掛け率)を確認している
- □ モニタリング報告の頻度と内容を理解している
- □ 返済不能時のリスクを認識し対策を講じている
- □ 金融機関との密なコミュニケーション体制がある
ABL活用ステップ:申込から融資実行まで
ABLを実際に活用するためのステップを見ていきましょう。
STEP1 事前準備:担保資産の棚卸と損益予測
ABL申込の前に、まずは自社の担保となる資産を正確に把握することが必要です。
具体的には以下のような準備を行います。
❶在庫の棚卸と評価
- 商品カテゴリー別の数量と金額
- 保管場所と状態
- 回転率や鮮度(陳腐化リスクの有無)
❷売掛金の明細作成
- 取引先別残高
- 支払条件と回収予定日
- 取引先の信用情報
❸資金需要と返済計画の策定
- 具体的な資金使途の明確化
- 売上・利益予測に基づく返済シミュレーション
- 最低限必要な調達額の算出
これらの情報を整理するためのExcelテンプレートを用意しました。
以下のような形式で情報をまとめておくと審査がスムーズです。
| 在庫管理表のサンプル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品カテゴリー | 数量 | 単価 | 総額(円) | 最終入庫日 |
| A商品群 | 100 | 5,000 | 500,000 | 2025/3/15 |
| B商品群 | 50 | 10,000 | 500,000 | 2025/3/20 |
| C商品群 | 30 | 30,000 | 900,000 | 2025/2/28 |
| 売掛金明細表のサンプル | |||
|---|---|---|---|
| 取引先名 | 売掛金額(円) | 請求日 | 入金予定日 |
| X株式会社 | 2,000,000 | 2025/3/31 | 2025/5/31 |
| Y株式会社 | 1,500,000 | 2025/3/31 | 2025/5/15 |
| Z株式会社 | 1,000,000 | 2025/3/31 | 2025/4/30 |
銀行時代の経験からアドバイスすると、この段階で情報が整理されているかどうかが、その後の審査のスピードと融資条件に大きく影響します。
STEP2 金融機関・保証協会への相談と必要書類
準備ができたら、金融機関への相談に進みます。
一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 基本書類
- 決算書(直近3期分)
- 試算表(直近のもの)
- 会社案内・商品カタログ
- 事業計画書(資金使途と返済計画)
- 担保関連書類
- 在庫リスト(場所、数量、金額)
- 売掛金明細(取引先、金額、期日)
- 仕入れ・販売サイクルの説明資料
- 取引先との契約書(コピー)
メインバンクがABLに積極的でない場合は、信用保証協会付きABLも選択肢となります。



信用保証協会のABL保証制度を利用すれば、金融機関のリスク負担が軽減されるため融資が実現しやすくなります。
私のクライアントの中には、メインバンクでABLの相談を断られた後、地元の信用金庫と信用保証協会を組み合わせてABLを実現したケースもあります。
STEP3 資産評価・審査のポイント
申込後、金融機関は担保資産の評価を行います。
ここでのポイントは以下の通りです。
❶売掛先の信用調査
- 売掛金の場合、売掛先の信用力が重要
- 上場企業や公的機関向け売掛金は高評価
- 貸倒実績や回収サイトも審査要素
❷在庫査定のフロー
- 外部評価会社による実地調査を実施
- 在庫の質・量・管理状況をチェック
- 流動性(換金性)の高い在庫ほど評価は高い
❸審査における重要ポイント
- 資産価値だけでなく事業の継続性も評価
- 資金使途の妥当性
- 過去の返済実績
- 在庫・売掛金管理体制の整備状況
審査では単に資産価値だけでなく「事業継続によって融資が回収できるか」という観点も重視されます。
そのため、事業計画の説明も丁寧に行うことが大切です。
STEP4 契約・登記・融資実行後のモニタリング
審査通過後は、契約締結・登記手続き・融資実行というステップを踏みます。
❶契約関連
- 金銭消費貸借契約書
- 譲渡担保権設定契約書
- モニタリング条件の確認
❷登記手続き
- 動産譲渡登記(在庫・機械設備の場合)
- 債権譲渡登記(売掛金の場合)
- 司法書士への委託が一般的
❸融資実行後のモニタリング体制構築
- 報告頻度と内容の確認
- 担当者の明確化
- 報告フォーマットの標準化
私が実務で経験した効率的なモニタリング方法は次の通りです。
- 月初5営業日以内に前月末時点の状況報告
- Excelで統一フォーマットを作成し、毎月更新
- 写真つきレポートによる在庫状況の視覚的説明
- 四半期に一度の取引先訪問(金融機関と同行)
このようなサイクルを確立することで、金融機関との信頼関係構築と継続的な融資関係の維持につながります。
中小企業の活用事例3選――成功と失敗から学ぶ
実際のABL活用事例から、成功のポイントと注意点を学びましょう。
季節商材メーカー:繁忙期在庫を担保に資金繰り改善
【企業プロフィール】
- 業種:アウトドア用品製造業
- 規模:年商10億円、従業員30名
- 課題:季節的な資金需要の変動が大きい
【ABL活用方法】
このメーカーは夏物商品(テント、キャンプ用品など)の製造が中心で、冬場の仕入れ時期に資金需要が集中する季節変動がありました。
ABLを活用し、倉庫に保管された完成品在庫を担保に、次シーズンの仕入資金3,000万円を調達。
【成功ポイント】
- 製品の品質が高く、担保価値評価が安定
- 在庫管理システムの導入で在庫状況の可視化を実現
- シーズンに合わせた変動融資枠の設定
このケースでは、在庫の価値を適正に評価してもらうため、製品の市場価値や流通経路を丁寧に説明した資料を準備したことがカギでした。
結果として、在庫→販売→入金→返済のサイクルが確立され、安定的な資金繰りを実現しています。
ITスタートアップ:大企業向け売掛金で低コスト調達
【企業プロフィール】
- 業種:システム開発
- 規模:年商3億円、従業員15名
- 課題:大口案件の受注に伴う資金需要
【ABL活用方法】
この企業は上場企業の基幹システム開発を受注しましたが、開発期間中の人件費や外注費の支払いが先行し、資金繰りが厳しい状況でした。
そこで、受注契約に基づく売掛債権を担保に、開発期間中のつなぎ資金2,000万円を調達。
【成功ポイント】
- 売掛先が大手上場企業で信用力が高い
- 確定した契約書があり、将来債権の確実性が高い
- プロジェクト管理体制が整っている
このケースでは、発注元の上場企業の信用力を活かし、リスクの低い案件として融資条件が優遇されました。
無担保融資より2%低い金利での調達が実現し、資金繰りの改善と利益確保の両立に成功しています。
再生局面の製造業:ABL+保証協会で事業再建
【企業プロフィール】
- 業種:金属加工業
- 規模:年商5億円、従業員25名
- 課題:赤字決算が続き、既存融資の返済条件変更中
【ABL活用方法】
この企業は2期連続の赤字で返済条件変更中でしたが、新規設備導入による生産性向上が必要な状況でした。
通常融資では新規資金調達が困難だったため、機械設備と売掛金を担保としたABLを信用保証協会付きで実行。新設備導入資金1,500万円を調達しました。
【成功ポイント】
- 保有設備の価値が高く、流動性もある
- 信用保証協会のABL保証制度を活用
- 設備導入による収益改善計画が説得力を持つ
この事例では、再建計画の実現可能性を丁寧に説明し、金融機関と保証協会の理解を得られたことが重要でした。
結果として、新設備導入により生産性が30%向上し、1年後には黒字化を達成。3年後には通常返済に復帰しています。
ある卸売業では、ABLを導入したものの、在庫管理体制が不十分だったため、担保資産の減少を適切に報告できませんでした。
結果として金融機関の信頼を失い、融資枠の縮小を余儀なくされました。
この事例から、ABL成功の鍵は「担保資産の正確な把握と透明性の高い報告体制」にあることがわかります。
ABLが向いている企業・向かない企業
すべての企業にABLが適しているわけではありません。
自社の特性を見極めて判断しましょう。
向いている企業の特徴
ABLが特に有効な企業には、以下のような特徴があります。
- 在庫・売掛金比率が高い企業
- 製造業(機械、食品、アパレルなど)
- 卸売業
- 商社
- 小売業(特に大型店舗)
- 成長投資が急務の企業
- 事業拡大フェーズのスタートアップ
- 新規事業に取り組む中小企業
- 設備投資ニーズの高い企業
- 担保不足に悩む企業
- 不動産を持たない企業
- 創業間もない企業
- 既存担保枠を使い切った企業
特に重要なのは、事業に必要な在庫や設備を持ち、安定した商流があることです。
例えば、銀行時代に私が担当したある食品メーカーは、工場はすべて賃借でしたが、原材料在庫と製造機械を担保としたABLで設備更新資金を調達し、生産性向上につなげました。
向かない企業の特徴
反対に、ABLが適さない可能性が高い企業の特徴は以下の通りです。
- 赤字継続・債務超過の度合いが深刻な企業
- 債務超過3期以上が継続
- 営業赤字が構造的で改善の兆しがない
- 資金繰りが極めて逼迫している
- 回収リスクの高い売掛先が中心の企業
- 貸倒実績が多い
- 取引先の経営状態が不安定
- 債権回収トラブルの履歴がある
- 在庫管理体制が整っていない企業
- 棚卸が不定期または未実施
- 在庫データが不正確
- 管理責任者が明確でない
特に在庫管理体制の整備は重要で、これが不十分だとモニタリングに支障をきたし、ABL継続が困難になります。
私のクライアントで失敗した例では、在庫管理システムがなく手書きの台帳管理だったため、金融機関の実地調査で在庫金額に大きな乖離が発見され、融資条件の見直しを求められたケースがありました。
判断フローと次善の選択肢
ABLが自社に適しているか判断するためのフローチャートです。
1.自社に安定した流動資産(在庫・売掛金)があるか?
- YES → 2へ進む
- NO → ファクタリングや補助金を検討
2.在庫または売掛金の管理体制は整っているか?
- YES → 3へ進む
- NO → 管理体制整備を優先
3.事業の継続性と返済能力はあるか?
- YES → ABLを検討
- NO → 事業再構築を優先
ABLが向かないと判断された場合の代替手段としては、
- 資金調達先の多様化(ファクタリング、クラウドファンディングなど)
- 補助金・助成金の活用
- リースの活用
- 資本提携の検討
例えば、私が支援したITベンチャーは、ABLに必要な売掛債権の蓄積がなかったため、代替策として開発案件のマイルストーン分割払い契約とクラウドファンディングを組み合わせて資金調達に成功しました。
適切な判断と柔軟な対応が、資金調達成功のカギとなります。
よくある質問(FAQ)
ABLに関してよく受ける質問とその回答をまとめました。
Q: ファクタリングとの一番の違いは?
A: 最大の違いは「売却(オフバランス)」か「借入(オンバランス)」かという点です。
ファクタリングでは売掛金を売却してしまうため、バランスシートから資産が消えます(オフバランス)。
一方、ABLは売掛金を担保にした借入なので、バランスシート上に資産も負債も残ります(オンバランス)。
これにより税務処理やコスト構造が大きく異なります。
ファクタリングは一度の取引ごとに手数料が発生するのに対し、ABLは融資期間中の金利のみです。
また、ファクタリングでは取引先への通知が必要になるケースが多いですが、ABLでは債権譲渡登記のみで通知不要の場合もあります。
Q: どのくらいの在庫があれば借りられる?
A: 一般的な目安としては、在庫評価額の50%程度が融資上限となることが多いです。
例えば、1億円の在庫があれば、5,000万円程度の融資が可能になります。
ただし、これは在庫の種類や管理状況によって大きく変わります。
特に棚卸の精度が高く、在庫管理システムで数量と金額が常に把握できる状態であれば、評価率が上がる傾向にあります。
逆に、陳腐化リスクの高い在庫(ファッション商品や季節商材など)は評価率が下がることがあります。
コンサルタントとしての経験上、最も重要なのは「在庫の健全性」を示す資料(回転率、鮮度、廃棄率など)を準備することです。
Q: 売掛先に知られずに利用できますか?
A: 債権譲渡登記のみで通知不要としているケースもありますが、金融機関によっては売掛先への通知を条件とする場合もあります。
この点は事前に金融機関と確認することが重要です。
通知が必要な場合でも、「担保設定」という形で通知するため、資金繰りに問題があると誤解されることは少ないです。
私のクライアントでは、取引先に「金融機関との取引拡大に伴う手続き」として説明し、支払先の変更などはせずに円満に手続きを進めた例が多くあります。
Q: 評価費用はいくらかかる?
A: 動産評価は規模や複雑さによって異なりますが、一般的に10万円〜数十万円程度かかります。
また、登記費用は債権額×0.2%+司法書士報酬が目安です。
例えば、5,000万円の債権を登記する場合、約10万円の登記費用が発生します。
ただし、金融機関によっては融資枠設定の中でこれらの費用を吸収するケースもあります。
費用対効果を考えると、融資額が1,000万円以上のケースでABLを検討するのが現実的でしょう。
Q: 創業2年目でも利用できますか?
A: 決算1期分の実績があれば審査は可能です。
ただし、創業間もない企業の場合は、以下の要素が重視されます:
- 売掛先の信用力(特に大手企業との取引があれば有利)
- 事業計画の実現可能性
- 経営者の過去の実績や信用情報
- 在庫・売掛金管理体制の整備状況
私が支援したIT企業は創業2年目でしたが、大手企業との確定契約があり、それを担保としたABLで開発資金を調達することができました。
事業の将来性と管理体制の整備が評価された好例です。
まとめ
ABLは「資金調達の最後の砦」ではなく、成長ドライバーにもなる手法です。
不動産担保や個人保証に頼らず、事業そのものの資産価値を活かせる点が最大の魅力。
ただし掛け目やモニタリング負荷など特有のハードルも存在します。
メリット・デメリットを理解し、自社の資産構成と資金計画に照らして活用可否を判断しましょう。
この記事を一歩目に、まずは自社の在庫・売掛金を棚卸し、金融機関に相談してみてください。
資金調達の選択肢を広げることは、経営の自由度を高め、事業成長のチャンスを広げることにつながります。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる