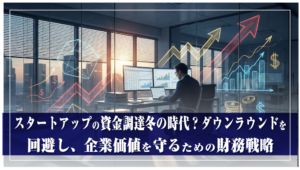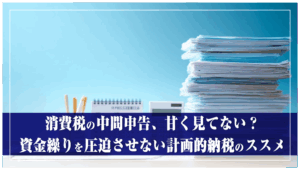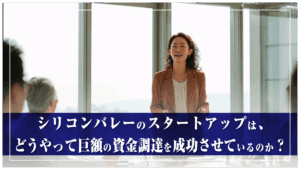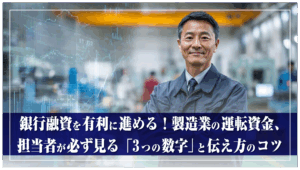「今期は赤字だ。もう銀行からの借入は絶望的かもしれない…」
そんな不安を抱えている経営者様に、まず結論からお伝えします。
赤字でも借入は可能です。実際に、私がコンサルティングした企業の約7割が、赤字状況でも融資を獲得しています。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆多くの経営者様が信じている「赤字=融資不可」は、実は大きな誤解なのです。
【この記事の結論】赤字でも借入を成功させる3つの鉄則
「赤字だから借入できない」と諦めるのはまだ早いです。金融機関は赤字の「中身」と「今後の改善計画」を重視します。以下の3つの鉄則を押さえることで、融資の可能性は大きく高まります。
- 鉄則1:説得力のある資料を準備する
赤字の原因と具体的な黒字化への道筋を示す「事業計画書」と、返済能力を証明する「資金繰り表」は必須です。「なぜ赤字で、どうやって立て直すのか」を数字で示しましょう。 - 鉄則2:赤字の理由を前向きに説明する
将来の成長に向けた先行投資など「良い赤字」であることを論理的に説明します。減価償却による会計上の赤字など、キャッシュフローがプラスである点も重要なアピールポイントです。 - 鉄則3:適切な金融機関を選ぶ
メガバンクだけでなく、中小企業の状況に理解がある「日本政策金融公庫」や地元の「信用金庫」にも相談しましょう。自社の状況に合った相談先を選ぶことが成功の鍵です。
本文では、これらの鉄則をさらに詳しく解説し、融資担当者を納得させるための具体的な方法を紹介します。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ「赤字は借入できない」という神話が生まれたのか?
元銀行員が語る金融機関の視点
銀行がなぜ赤字を嫌うのか。
それは非常にシンプルで、「貸したお金を、約束通りに返してもらえるか」という一点を最も重視しているからです。
銀行の審査では、決算書をもとに「返済能力」を判断します。
利益は、借入金を返済するための最も重要な原資(源泉)です。
そのため、「赤字=返済原資がない」と機械的に判断されてしまうのが、基本的な考え方なのです。
これは銀行のビジネスモデルを考えれば当然のこと。
しかし、全ての銀行員が数字だけで判断しているわけではありません。
決算書の数字の裏にある「ストーリー」を、私たちは必死に読み解こうとしていました。
「良い赤字」と「悪い赤字」がある
ここで最も重要なことをお伝えします。
それは、すべての赤字が同じように見られているわけではない、ということです。
私はこれを「良い赤字」と「悪い赤字」と呼んでいます。
良い赤字(前向きな赤字)
将来の成長のための設備投資や人材採用、新商品開発などが原因で、一時的に発生している赤字。
悪い赤字(構造的な赤字)
売上不振やコストの高止まりなど、事業構造そのものに問題があって慢性的に発生している赤字。



金融機関との交渉の第一歩は、自社の赤字が「良い赤字」であることを、客観的な事実と未来への展望をもって説明することにあります。
【元銀行員が解説】赤字でも借入が可能な5つのケース
では、具体的にどのような赤字であれば、融資の可能性があるのでしょうか。
私が銀行員時代やコンサルタントとして関わってきた事例から、代表的な5つのケースをご紹介します。
ケース1:先行投資による「未来のための赤字」
新事業の立ち上げや、生産性を向上させるための大規模な設備投資、優秀な人材の先行採用など、将来の大きなリターンを見込んだ投資が原因で一時的に赤字になっているケースです。
私がコンサルしたあるIT企業は、新しいSaaSプロダクトの開発に多額の費用を投じ、2期連続の赤字でした。
しかし、そのプロダクトの将来性や詳細な販売計画、そして何より経営者の熱意を盛り込んだ事業計画書を提出した結果、銀行は「未来への投資」と判断し、運転資金の融資を実行しました。
この場合、その投資が「単なる浪費」ではなく「計算された未来への布石」であることを、具体的な収益計画で示すことが鍵となります。
ケース2:創業期に避けられない「計画通りの赤字」
創業当初は、売上が安定するまでの初期投資や運転資金で赤字になるのが一般的です。
これは金融機関も十分に理解しています。
重要なのは、提出した創業計画書通りに事業が進捗しているか、という点です。
「計画通りに進んでおり、想定の範囲内の赤字です。来期には黒字化する蓋然性が高いです」と説明できれば、むしろ計画性があると評価されることさえあります。
ケース3:減価償却による「会計上の赤字」
これは、経営者の方が見落としがちな重要なポイントです。
減価償却費は、会計上は費用として計上されますが、実際には会社からキャッシュが出ていくわけではありません。
もし、赤字額のほとんどが減価償却費によるものであれば、「キャッシュフロー(実際のお金の流れ)は黒字」である可能性があります。
この場合、「会計上は赤字ですが、キャッシュはプラスで、返済能力に問題はありません」と資金繰り表などを用いて説明できれば、融資担当者も納得しやすいです。
ケース4:一過性の要因による「突発的な赤字」
- 自然災害による設備の損壊
- 主要な取引先の倒産
- 役員退職金の支払い
このような、一過性の特別な損失によって赤字になった場合です。
この要因が今期限りで解消され、翌期以降は黒字に回復する見込みが高いことを論理的に説明できれば、融資の可能性は十分にあります。
「不運だったが、事業の根幹は揺らいでいない」ということを示すのがポイントです。
ケース5:営業利益は黒字の「経常赤字」
決算書をよく見てください。
本業の儲けを示す「営業利益」は黒字なのに、借入金の支払利息などがかさんで「経常利益」が赤字になっているケースです。
これは、「本業で稼ぐ力は十分にある」という証明になります。
この場合、追加融資によって高金利の借入を一本化する(借り換える)など、財務体質を改善する具体的な計画を提示できれば、金融機関も前向きに検討してくれる可能性があります。
赤字企業が借入を成功させるための5つの重要ポイント
では、これらのケースに当てはまる企業が、実際に融資を成功させるためには何をすべきでしょうか。
私が常にクライアント様にお伝えしている、5つの重要ポイントをご紹介します。
ポイント1:説得力のある「事業計画書・経営改善計画書」
なぜ赤字になったのか、そして今後どのように黒字化していくのか。
このストーリーを、具体的な数値目標と行動計画に落とし込んだ計画書が、あなたの会社の未来を示す「設計図」になります。
私がコンサルで実際に指導している計画書では、最低でも以下の点を盛り込みます。
1. 赤字の原因分析
誰のせいでもなく、客観的な事実を記載する。
2. 具体的な改善アクションプラン
「経費削減を頑張る」ではなく、「〇〇の費用を△△円削減する」と具体的に。
3. 売上計画とその根拠
新規顧客の獲得目標、客単価アップの施策など、どうやって売上を作るのかを具体的に示す。
4. 数値計画
損益計画、資金繰り計画を具体的な数字で示す。
ポイント2:「資金繰り表」で返済能力を証明する
「この会社にお金を貸しても、本当に返ってくるのか?」
この金融機関の最大の懸念を払拭するため、資金繰り表の作成は必須です。
最低でも過去3ヶ月の実績と、今後6ヶ月〜1年の予測を立てましょう。
これにより、将来のキャッシュフローを「見える化」し、借入返済が滞りなく行えることを証明できます。
エクセルで構いません。これがあるだけで、あなたの会社の信頼性は格段に上がります。
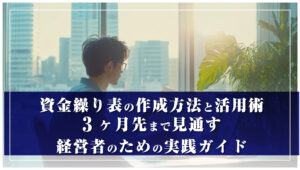
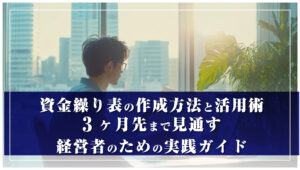
ポイント3:資金使途の明確化と妥当性
借りたお金を何に使い、それがどう事業の改善に繋がるのかを明確に説明することが求められます。
「赤字補填のため」といった曖昧な目的では、お金をドブに捨てるような印象を与えかねません。
「新規顧客獲得のためのWEB広告宣伝費として300万円」「生産性向上のための新型機械導入費用として500万円」など、前向きで具体的な使途を示しましょう。
ポイント4:適切な金融機関を選ぶ
金融機関にもそれぞれ特徴があります。自社の状況に合った相談先を選ぶことが、成功の確率を大きく左右します。
| 金融機関の種類 | 特徴 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|
| メガバンク | 審査基準が厳格な傾向。事業規模の大きい企業向け。 | 大規模な設備投資を計画している体力のある企業 |
| 地方銀行・信用金庫 | 地域密着型で、地元の企業の状況に理解がある。親身に相談に乗ってくれることが多い。 | 地域に根差して事業を行っている中小企業 |
| 日本政策金融公庫 | 国の政策金融機関。中小企業支援を目的としており、赤字企業にも比較的寛容。 | 創業期の企業、民間からの借入が難しい企業 |



いきなりメガバンクに飛び込むのではなく、まずは地元の信用金庫や、日本政策金融公庫に相談してみることをお勧めします。
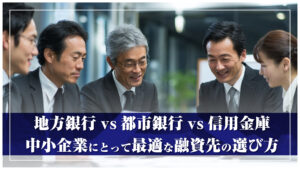
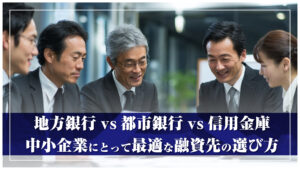
ポイント5:経営者の熱意と誠実な対話
最終的に融資を判断するのは「人」です。
私が銀行員時代、最終的に稟議を通す後押しになったのは、書類の数字だけではありませんでした。
ピンチの状況を正直に語り、それをどう乗り越えようとしているのか。事業への熱い想い、従業員を守りたいという覚悟。そうした経営者の誠実な姿勢が、担当者の心を動かすのです。
決して嘘をつかず、できない約束はせず、誠実に対話することを心がけてください。
融資が難しい場合の次の一手:ファクタリングという選択肢
あらゆる手を尽くしても、融資が難しい。
そんな時に、ぜひ知っておいてほしいのが「ファクタリング」という資金調達方法です。
ファクタリングとは?融資との根本的な違い
ファクタリングとは、あなたの会社が持っている「売掛債権(入金待ちの請求書)」を専門の会社に買い取ってもらうことで、早期に資金化するサービスです。
最大のポイントは、これが「借入(融資)」ではない、ということです。
審査の対象は、あなたの会社ではなく、請求書の発行先である「売掛先(取引先)」の信用力になります。
そのため、あなたの会社が赤字や債務超過であっても、利用しやすいのです。
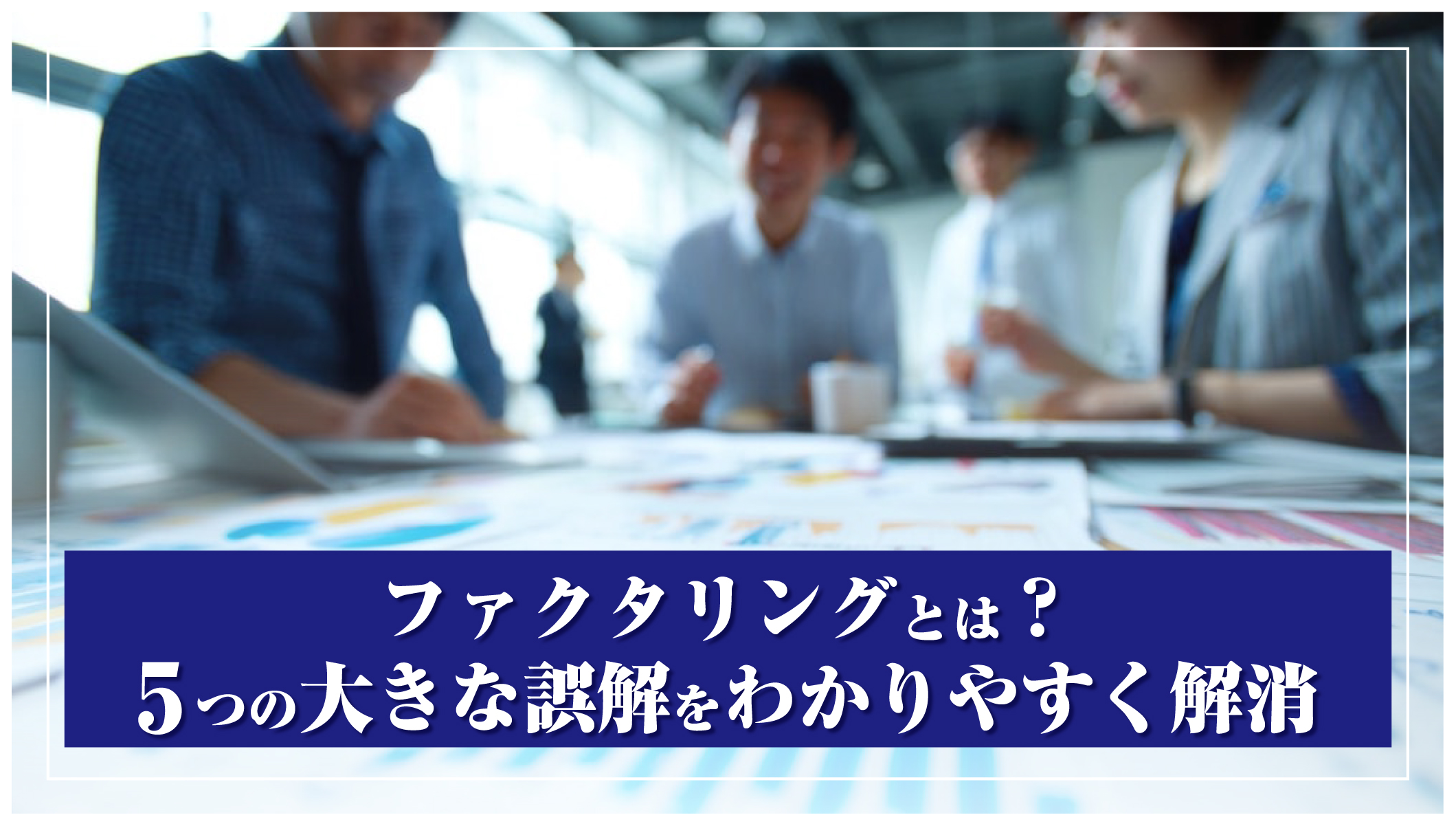
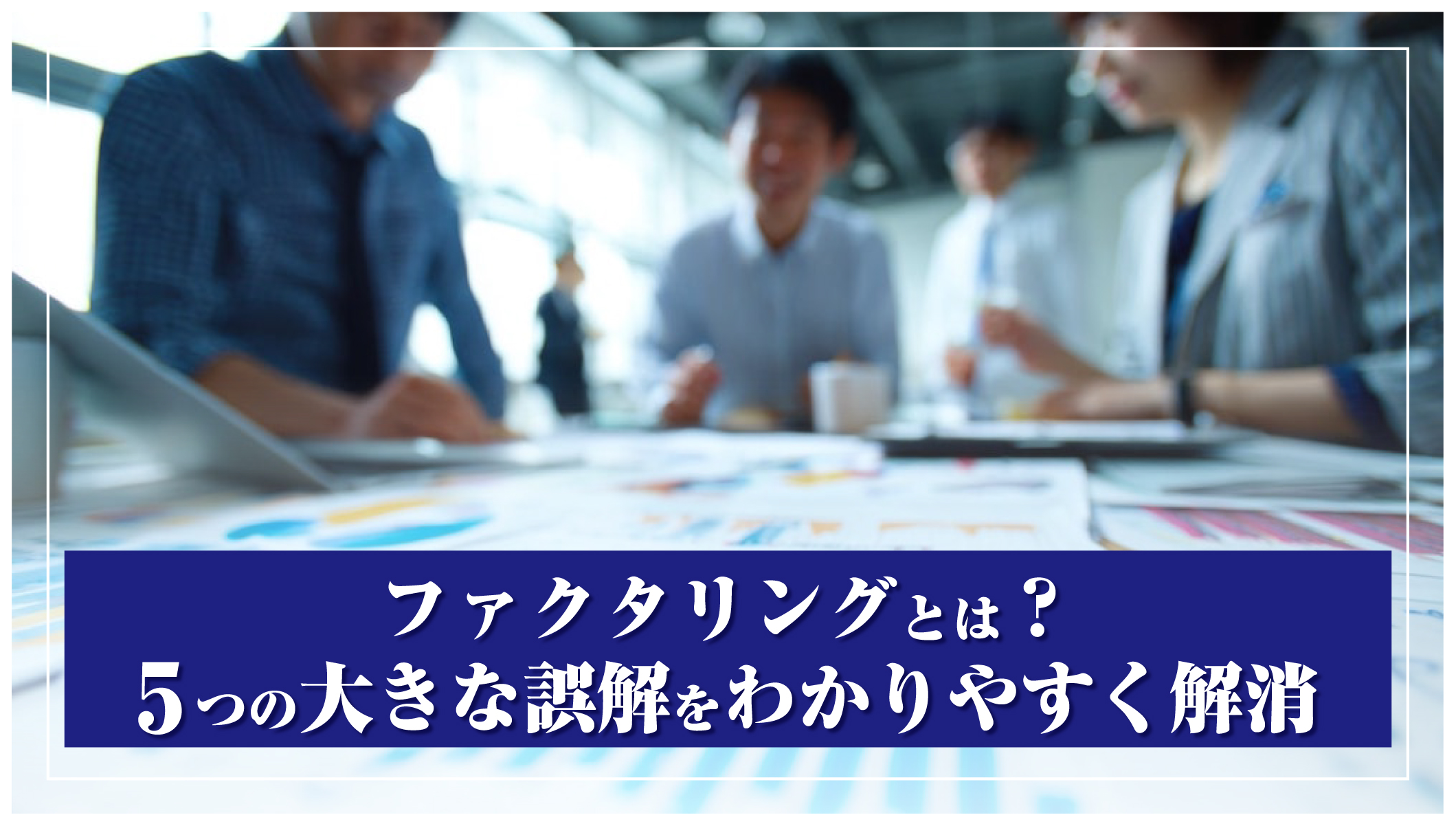
ファクタリングのメリットと注意すべき点
メリット
- 最短即日の資金化: 融資に比べて圧倒的にスピーディーです。
- 担保・保証人が不要: 売掛債権そのものが信用の源泉となります。
- 負債にならない: 貸借対照表(B/S)をスリム化でき、財務内容を悪化させません。
注意すべき点
- 手数料が割高: 融資の金利に比べると、手数料は割高になる傾向があります。
- 売掛先に通知が必要な場合がある: 3社間ファクタリングの場合、売掛先の承諾が必要です。
- 債権譲渡登記が必要な場合がある
- 悪徳業者の存在
【佐々木からの重要アドバイス】
ファクタリングは非常に有効な手段ですが、残念ながら法外な手数料を請求する悪徳業者が存在することも事実です。契約前には必ず複数の会社から見積もりを取り、契約内容を隅々まで確認してください。少しでも「おかしい」と感じたら、安易に契約しない勇気が大切です。
よくある質問(FAQ)
Q: 2期連続、3期連続の赤字でも借りられますか?
A: 非常に厳しくなりますが、可能性はゼロではありません。慢性的な赤字と見なされるため、なぜ赤字が続いているのかという原因分析と、それを断ち切るための抜本的な経営改善策、そしてそれを裏付ける極めて精度の高い事業計画書が不可欠です。専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをお勧めします。
Q: 債務超過に陥っている場合はどうなりますか?
A: 債務超過は、資産よりも負債が多い状態で、融資のハードルは格段に上がります。ただし、増資による自己資本の強化や、実現可能性の高い事業再生計画を策定することで、資本性ローン(返済の優先順位が低く、自己資本と見なされるローン)などの特定の融資制度を利用できる場合があります。
Q: 融資の相談に行ったら、何を話せば良いですか?
A: まず、赤字になった原因を正直に、かつ客観的に説明してください。次に、それをどう乗り越えるかの具体的な改善策と今後のビジョンを、本記事で解説した事業計画書や資金繰り表を元に熱意を持って語ることが重要です。
Q: 日本政策金融公庫は赤字に本当に寛容なのですか?
A: はい、民間金融機関に比べて、国の政策として中小企業を支える役割を担っているため、事業の将来性をより重視する傾向があります。特に「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」などは、業況が悪化した企業を対象としており、赤字企業でも利用しやすい制度の一つです。
Q: 融資以外の資金調達方法はありますか?
A: はい、あります。本記事でも詳しく解説したファクタリングは、赤字企業にとって非常に有効な選択肢です。その他にも、返済不要の補助金・助成金の活用、クラウドファンディング、資産の売却など、融資以外の選択肢も多様化しています。自社の状況に合わせて、これらの方法も並行して検討すると良いでしょう。
まとめ:あなたの会社の未来は、まだ終わっていない
「赤字だから借入できない」
その固定観念は、今日で終わりにしましょう。
本記事で解説したように、赤字には様々な「種類」があり、その原因と今後の展望を的確に説明できれば、金融機関から支援を得る道は確かに存在します。
【これだけは押さえたいポイント】
- 自社の赤字が「良い赤字」か「悪い赤字」か分析する。
- 説得力のある「事業計画書」と「資金繰り表」を作成する。
- 日本政策金融公庫や地元の信金など、適切な相談先を選ぶ。
- 誠実な対話で、経営者の熱意と覚悟を伝える。



そして、万が一融資が難しい場合でも、ファクタリングという力強い選択肢があることを忘れないでください。
ピンチは、事業を見つめ直し、より強固な経営体制を築くチャンスです。
この記事を参考に、まずは自社の「赤字の理由」を分析することから始めてみてください。
そして、希望を持って金融機関の扉を叩いてみましょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる