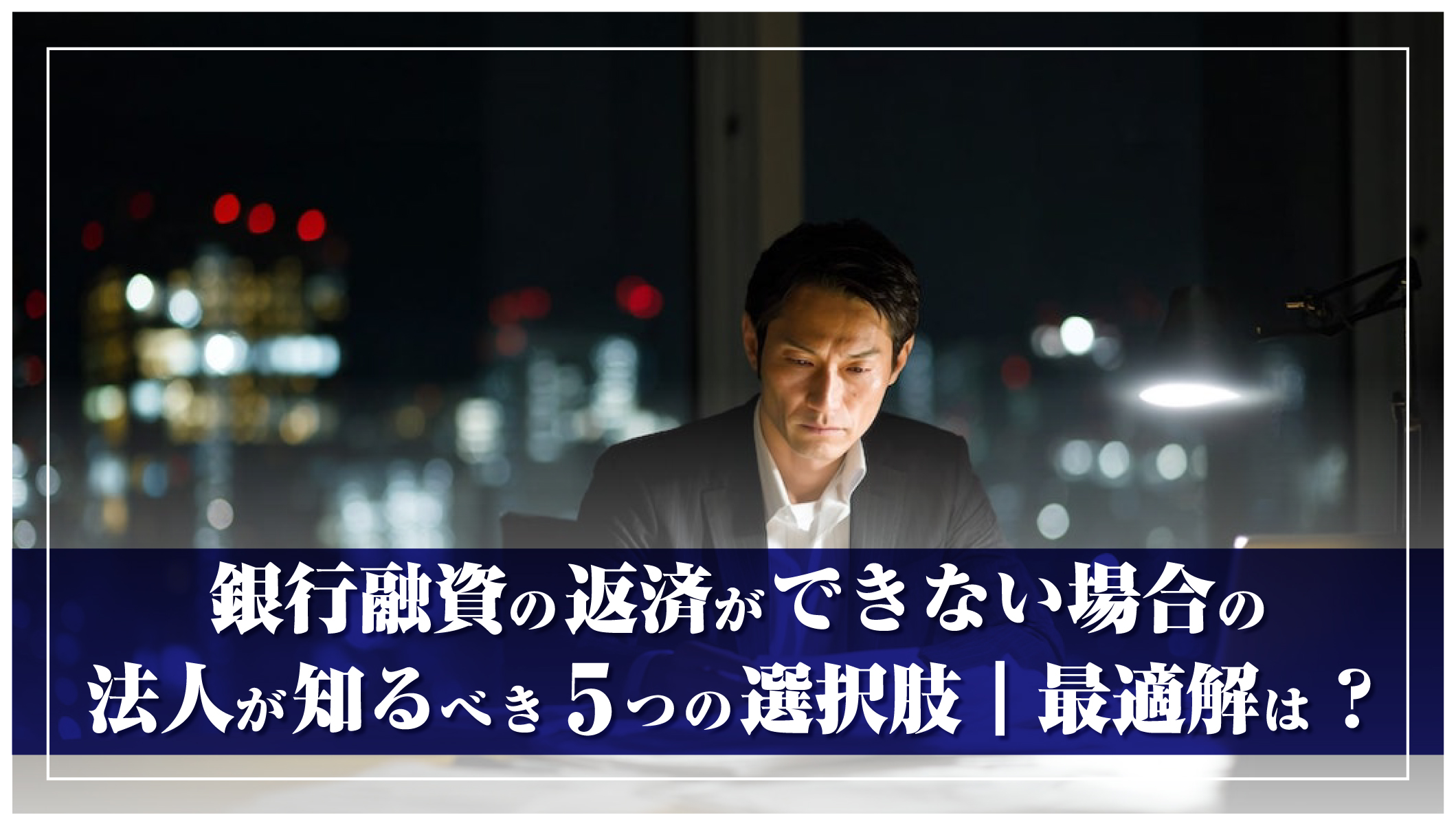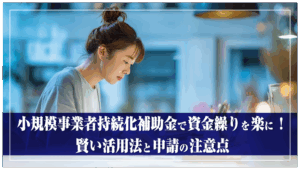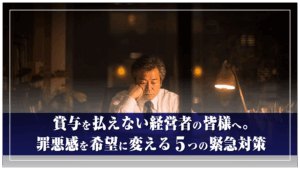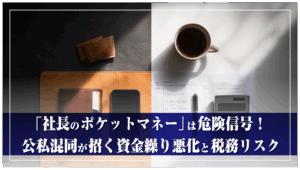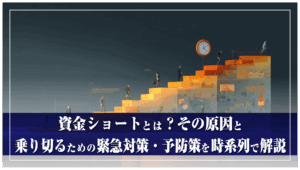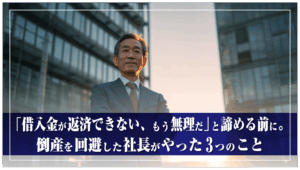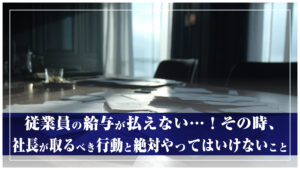銀行融資の返済が迫り、「このままでは資金がショートしてしまう…」と、夜も眠れないほどの不安を抱えていませんか?
ご安心ください。そのプレッシャーは、かつて銀行で融資を担当し、現在は多くの企業の財務を立て直してきた私には痛いほどわかります。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆素晴らしい技術やサービスがありながら、資金繰りの問題だけで事業を諦める経営者を、私はもう見たくありません。
実は、返済不能に陥る前に、あなたの会社が今すぐ打てる手は、まだ5つも残されています。
【この記事の結論】銀行融資が返済できない時に取るべき5つの選択肢
銀行融資の返済が困難になった場合、放置することが最も危険です。状況に応じて、以下の選択肢を速やかに検討する必要があります。
- ① 銀行に相談する(リスケジュール):
返済が苦しいと感じたら、資金がショートする前に銀行へ相談し、返済計画の見直し(リスケ)を交渉します。これが最初に行うべき最も重要な行動です。 - ② 新たな資金を調達する:
リスケと並行し、ファクタリングや補助金・助成金など、銀行融資以外の方法で当座の運転資金を確保します。ただし、手数料の高い資金調達には注意が必要です。 - ③ 事業を再生する(私的整理・法的整理):
事業に将来性があるものの借入金が過大な場合、専門家の支援のもとで私的整理や法的整理(民事再生など)を行い、抜本的な会社の立て直しを図ります。 - ④ 会社・事業を売却する(M&A):
自社での再建は難しいが事業自体に価値がある場合、M&Aによって他社に事業を譲渡し、従業員の雇用や取引先を守りながら事業を未来へ繋ぎます。 - ⑤ 会社を清算する(破産):
あらゆる手段を尽くしても返済が不可能な場合の最終手段です。会社の財産を清算し、経営者自身が再スタートを切るための法的な手続きです。
本文では、元銀行員の視点から「交渉を有利に進めるコツ」や「各選択肢のメリット・デメリット」を詳しく解説します。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
銀行融資が返済できない状態に陥る前に。元銀行員が教える危険なサイン
資金繰りの問題は、人間で言えば静かに進行する病気のようなものです。
気づいた時には手遅れ、ということにならないよう、まずは「危険のサイン」を早期に察知することが何よりも重要です。
資金繰り表で見るべき3つのポイント
コンサルタントとして多くの企業を見ていると、危険な状態に陥る会社には共通の兆候が資金繰り表に現れます。
売掛金の回収サイトが延びていないか?
売上は立っているのに、入金までの期間が長くなると、その間の支払いに充てる現金が不足します。これが「黒字倒産」の入り口です。
在庫が急に増えていないか?
在庫は「現金が形を変えたもの」です。売れずに滞留している在庫が増えるほど、会社の現金は減っていきます。
営業キャッシュフローがマイナスになっていないか?
本業で現金を生み出せているかを示す最も重要な指標です。これが3ヶ月連続でマイナスになるようなら、事業の根幹に問題がある可能性が高く、危険信号です。
銀行員が「おや?」と思う経営の変化
銀行員は、融資先の財務諸表だけでなく、経営者の「行動の変化」も見ています。
私が銀行員だった頃、「この会社は少し危ないかもしれない」と感じた変化は、次のようなものでした。
試算表の提出が遅れる
これは最も分かりやすいサインの一つです。数字を見せたくない、という心理が働くからですが、これが続くと銀行は「何か隠しているのでは?」と不信感を抱き始めます。
経営者と連絡がつきにくくなる
以前はすぐに折り返しがあったのに、電話に出ない、メールの返信が遅い、といった変化です。これは、経営者が資金繰りに奔走し、精神的に追い詰められているサインであることが多いのです。
給与や経費の支払いが遅れる
社員への支払いが遅れるのは、資金繰りがかなり悪化している証拠です。これが外部に漏れると、会社の信用は一気に失墜します。



苦しい時ほど、銀行とのコミュニケーションを絶やしてはいけません。
悪い情報でも正直に、そして早めに共有することが、結果的に信頼関係を守り、銀行からの支援を引き出すための第一歩になるのです。
選択肢1:銀行との交渉(リスケジュール)で時間を作る
資金繰りが厳しくなった時、最初に検討すべき選択肢が、銀行への返済条件の変更、いわゆる「リスケジュール(リスケ)」です。
リスケジュールのメリットと知られざるデメリット
リスケジュールは、一時的に元金の返済を減額または猶予してもらい、利息のみの支払いに変更してもらう交渉です。
最大のメリットは、手元のキャッシュフローが劇的に改善されることです。
例えば、毎月100万円の元金返済がなくなれば、年間1,200万円の資金を事業の立て直しに使うことができます。
しかし、安易なリスケには大きなデメリットも存在します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・月々の返済負担が減り、資金繰りが楽になる | ・原則として、新規の追加融資が受けられなくなる |
| ・事業の立て直しに集中する時間を確保できる | ・銀行内での企業評価が下がり、「要注意先」となる |
| ・倒産を回避し、事業継続の可能性を探れる | ・返済期間が延びるため、総支払利息額は増える |
| ・一度リスケをすると、正常な状態に戻すのは容易ではない |
私が銀行員だった頃も、リスケに応じるということは「この会社は自力での返済が困難な状態にある」と判断することと同義でした。
つまり、リスケはあくまで延命措置であり、根本的な解決策ではないことを肝に銘じる必要があります。
元銀行員が明かす「交渉を有利に進める」経営改善計画書の書き方
銀行にリスケを認めてもらうためには、「経営改善計画書」の提出が不可欠です。
この計画書の出来が、交渉の成否を分けると言っても過言ではありません。
銀行が納得する計画書には、共通のポイントがあります。
窮状の原因分析が客観的であること
「コロナ禍で売上が落ちて…」というだけでは不十分です。「なぜ同業他社より売上の落ち込みが激しいのか」「固定費のどの部分が経営を圧迫しているのか」など、具体的な原因を数字で示す必要があります。
アクションプランが具体的であること
「経費削減を頑張ります」ではなく、「役員報酬を20%カットし月額〇〇万円、遊休資産である不動産Aを売却し〇〇万円を確保する」といった、誰が・いつまでに・何をするのかを明確にします。
数値目標に具体性と実現可能性があること
銀行が最も重視するのがこの部分です。ただ「売上をV字回復させます」という精神論では通りません。
「具体的なアクションプランを実行することで、3年以内に営業利益を黒字化し、5年以内に債務超過を解消する」といった、実現可能な返済計画の道筋を数字で示すことが極めて重要です。
選択肢2:新たな資金調達で当座をしのぐ
リスケジュールと並行して、あるいは別の選択肢として、新たな資金調達で当面の運転資金を確保する方法も考えられます。
追加融資・借り換えの現実的な可能性
まず、既存の取引銀行に追加融資を申し込む、あるいは金利の低い他の銀行へ借り換える、という選択肢です。
しかし、正直にお伝えすると、返済が困難な状況に陥っている企業が、銀行から新たな融資を受けるのは極めて困難です。
銀行の審査では「返済能力」が最も重視されます。
既存の借入返済に苦しんでいる時点で、その能力に疑問符がついている状態だからです。
具体的に言うと、既存の借入に対して一度でも延滞があれば、新規の融資は絶望的です。
銀行内の信用格付けが著しく低下し、その情報は銀行間で共有される可能性もあるため、他行への借り換えも非常に難しくなります。
ファクタリングや補助金活用の注意点
銀行融資が難しい場合、他の資金調達方法を検討する必要があります。
ファクタリング
売掛債権(請求書)をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する方法です。
メリット:審査がスピーディーで、自社の信用力より売掛先の信用力が重視されるため、赤字決算でも利用しやすい。
注意点:手数料が銀行融資に比べて非常に割高です。 安易に利用を続けると、利益を圧迫し、かえって資金繰りを悪化させる「ファクタリング依存」に陥る危険性があります。あくまで短期的なつなぎ資金と割り切るべきです。
補助金・助成金
国や地方自治体が提供する、返済不要の資金です。
メリット:返済義務がないため、財務状況を改善する上で非常に有効です。
注意点:申請手続きが煩雑で、受給までに時間がかかるケースが多いです。また、後払いが原則のため、当座の資金繰りには直接結びつかないこともあります。
選択肢3:事業再生で会社を立て直す
自社の事業には将来性があるものの、過大な借入金が原因で身動きが取れない。
このような場合に検討するのが、法的な手続きや専門家の支援を得て、本格的に会社の立て直しを図る「事業再生」です。
私的整理と法的整理の違いとは?
事業再生には、大きく分けて「私的整理」と「法的整理」の2つの方法があります。
| 私的整理 | 法的整理(民事再生など) | |
|---|---|---|
| 手続きの進め方 | 裁判所を介さず、主に金融機関など特定の債権者との話し合いで進める | 裁判所の監督下で、法律に則って進める |
| 公開性 | 非公開で進められるため、取引先や従業員に知られにくい | 官報に公告されるため、公になる |
| 対象となる債権者 | 主に金融機関のみ | 原則として全ての債権者(金融機関、仕入先、リース会社など) |
| 合意形成 | 原則、対象となる債権者全員の同意が必要 | 法律の要件(多数決など)を満たせば、一部の反対があっても強制的に成立させられる |
| メリット | ・事業価値が毀損しにくい ・柔軟な再生計画が可能 | ・強制力があり、抜本的な再生が可能 ・手続きの透明性が高い |
| デメリット | ・1社でも反対すれば成立しない ・手続きが不透明になりがち | ・「倒産」のイメージが強く、信用が低下しやすい ・費用が高額になる傾向がある |
例えば、取引先に知られずに内々で金融機関との交渉だけで進めたいなら「私的整理」、債権者の数が多く、個別の合意形成が難しい場合は「法的整理」といった使い分けになります。



詳しくは「【賛否両論】私的整理と法的整理、あなたの会社に適しているのはどちら?」でも解説してますので、良かったらご覧になってください。
専門家(コンサルタント・弁護士)と進める再生計画
事業再生は、経営者一人の力で成し遂げることは不可能です。
財務と法律の高度な専門知識が必要となるため、私のような資金繰りコンサルタントや弁護士といった専門家の協力が不可欠です。
【私のコンサル体験談】
これを知ったときは衝撃を受けましたが、専門家が入るだけで銀行の対応が劇的に変わるケースは本当に多いのです。
以前、私が支援した運送会社は、社長が一人で銀行と交渉していましたが、全く相手にされませんでした。
しかし、私が第三者の専門家として同席し、客観的なデータに基づいた再生計画を説明したところ、それまで硬直していた銀行の態度が軟化し、話し合いのテーブルについてくれたのです。
専門家は、銀行の論理を理解し、彼らが納得する「言語」で対話することができるのです。
選択肢4:M&A(事業譲渡)で事業を未来へ繋ぐ
事業の継続は難しいかもしれないが、この技術やサービス、そして何より従業員の生活を何とか守りたい。
そう考える経営者にとって、「M&A(事業譲渡)」は非常に有効な選択肢となり得ます。
借金があっても会社は売れるのか?
「借金まみれの会社なんて、誰も買ってくれないだろう」
そう思われるかもしれませんが、答えは「No」です。
債務超過の会社でも、事業の将来性や独自の技術力、優良な顧客基盤などがあれば、売却できる可能性は十分にあります。
買い手企業は、あなたの会社の負債ではなく、その事業が持つ「未来の収益力」や自社事業との「シナジー効果」に価値を見出すのです。
従業員と取引先を守るためのM&A
M&Aは、単なる会社の売却や延命措置ではありません。
従業員の雇用を守り、取引先との関係を維持し、長年かけて築き上げてきた事業そのものを未来へ繋ぐための、前向きで責任ある経営判断なのです。
自社単独での再生が困難な場合、より経営体力のある企業の傘下に入ることで、事業が大きく成長する可能性も秘めています。
経営者としての責任の果たし方は、一つではないのです。
選択肢5:法的整理(破産)という最終手段
あらゆる手を尽くしても事業の継続が困難であり、債務の返済が不可能になった場合、最終手段として「破産」という選択肢を検討せざるを得ません。
破産手続きの流れと経営者の責任
破産とは、裁判所の監督のもと、会社の全財産を現金化し、法律に基づいて各債権者に公平に分配(配当)することで、会社を清算する手続きです。
手続きが完了すると、会社の法人格は消滅します。
経営者の方が最も心配されるのが、「経営者保証」や「連帯保証」によって、会社の借金を個人で背負うことになるのではないか、という点だと思います。
原則として、会社の債務と個人の資産は別ですが、中小企業の場合、経営者が会社の借入の連帯保証人になっているケースがほとんどです。
この場合、会社が破産すると、銀行は連帯保証人である経営者個人に返済を請求してきます。



しかし、ここで知っておいてほしいのが「経営者保証ガイドライン」という制度です。
このガイドラインは、一定の要件を満たせば、会社の破産時に経営者の個人資産の一部(生活に必要なお金や、華美でない自宅など)を残せる可能性がある制度です。
ただし、適用されるには厳しい条件があり、専門的な判断が必要なため、必ず弁護士に相談してください。
「破産=終わり」ではない。再起に向けた考え方
「破産」という言葉には、どうしてもネガティブな響きがあります。
しかし、私はそうは思いません。
破産は、事業の失敗を社会的に清算し、経営者が新たな人生を再スタートするための、国が認めた法的な権利でもあるのです。
私が知っている経営者の中にも、一度は事業に失敗し破産を経験しながらも、その経験を糧に再び新しい事業にチャレンジし、見事に成功を収めている方が何人もいます。
破産は決して人生の終わりではありません。
むしろ、過大な債務のプレッシャーから解放され、次のステージへ進むための「区切り」と捉えることもできるのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 銀行に相談に行くタイミングはいつがベストですか?
A: 元銀行員として断言します。資金がショートする「前」です。具体的には、資金繰り表で3ヶ月先の資金不足が見えた時点がデッドラインです。早ければ早いほど、銀行として提案できる選択肢が増えます。決して一人で抱え込まず、まずは取引支店の担当者に「相談」という形で連絡してください。
Q: 返済を一度でも延滞すると、信用情報はどうなりますか?
A: 法人の場合、個人のような信用情報機関への登録とは異なりますが、銀行内での評価は著しく低下します。 いわゆる「要注意先」と分類され、今後の追加融資は原則として不可能になります。また、この情報は銀行間で共有される可能性もあり、他行からの借入も困難になると考えてください。
Q: 経営者保証ガイドラインとは何ですか?個人の資産は守られますか?
A: 経営者保証ガイドラインは、一定の要件を満たせば、会社の破産時に経営者の個人資産の一部(自宅など)を残せる可能性がある制度です。 しかし、適用には誠実な情報開示など厳しい条件があります。 この判断は専門知識が必要なため、必ず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q: どの選択肢を選ぶべきか、判断基準を教えてください。
A: 最適解は会社の状況によりますが、判断基準は「事業に将来性があるか」の一点に尽きます。将来性があるならリスケジュールや事業再生を。事業の継続が困難な場合はM&Aや法的整理を検討します。この見極めは非常に難しいため、客観的な視点を持つ資金繰りコンサルタントのような専門家にご相談ください。
Q: 専門家への相談費用がありません。どうすればよいですか?
A: 費用が厳しい場合でも、諦めないでください。中小企業庁の「早期経営改善計画策定支援事業」などを利用すれば、専門家費用の補助が受けられる場合があります。 また、多くの弁護士やコンサルタントが初回無料相談を実施しています。まずはそうした制度を活用して、現状を話してみることが重要です。
まとめ
銀行融資の返済問題は、経営者にとって孤独で過酷な戦いです。
しかし、本記事でご紹介したように、打つ手は決して一つではありません。
銀行員時代の経験と、コンサルタントとして多くの企業を支援してきた今、私が最も伝えたいのは「決して一人で判断しないでください」ということです。



リスケジュール、事業再生、M&A、そして最終手段としての法的整理。
どの選択肢にもメリットとデメリットがあり、実行すべき最適なタイミングがあります。
今日からすぐに始められることは、まず自社の正確な財務状況を、特にキャッシュフローを把握すること。
そして、信頼できる専門家にその状況を正直に話してみることです。
あなたの会社と従業員、そしてあなた自身の未来を守るために、勇気を持って次の一歩を踏出しましょう。
その一歩が、必ず未来を切り拓く力になります。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる