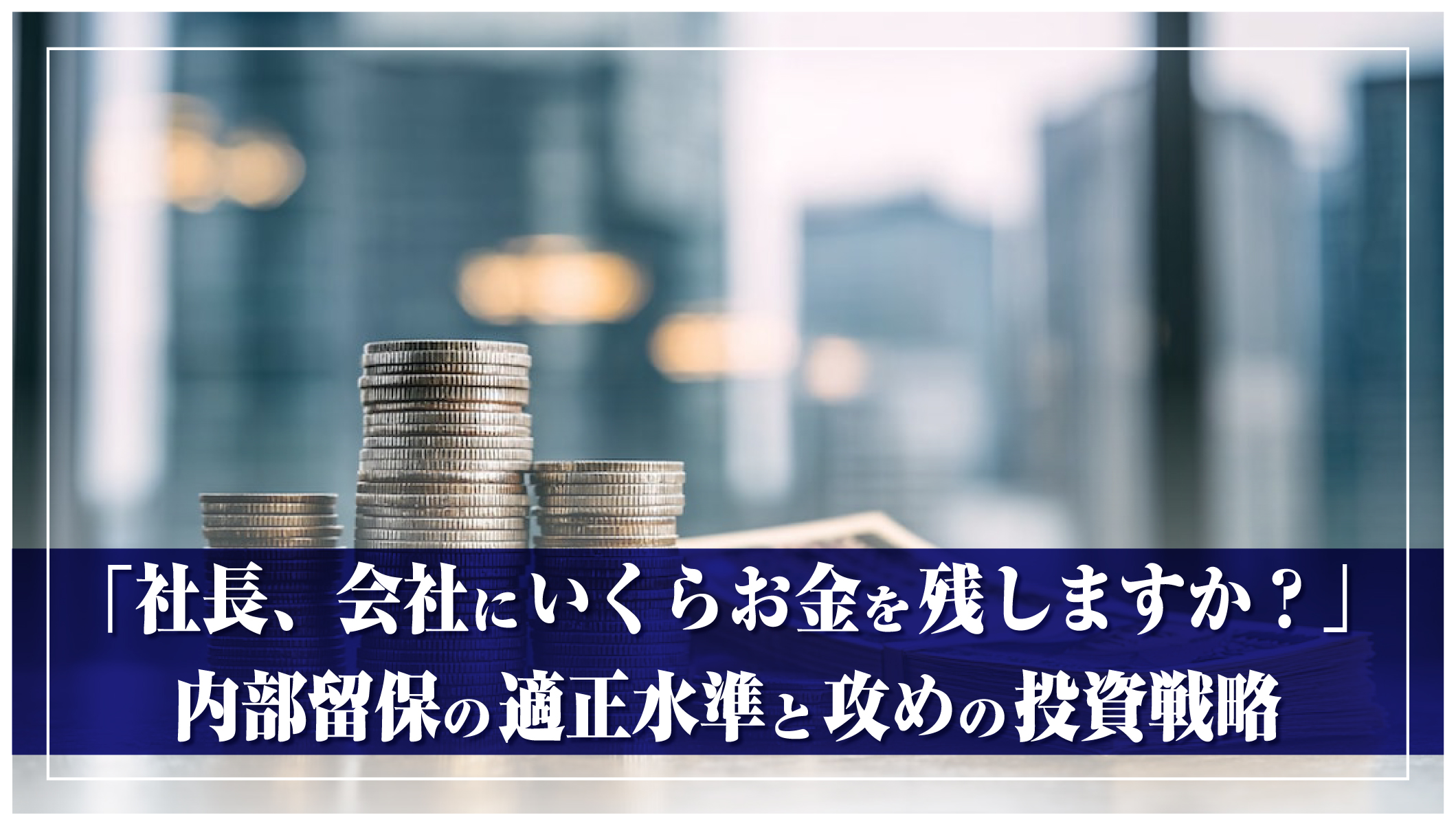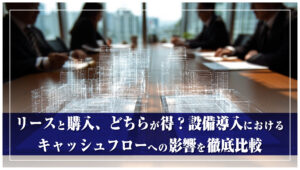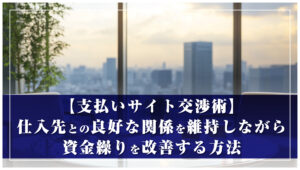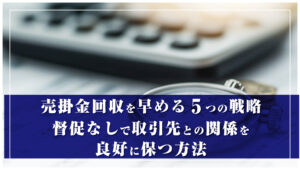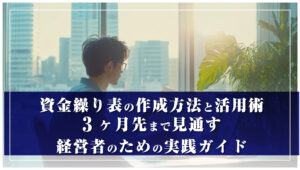「社長、あなたの会社の内部留保、今のままで本当に大丈夫ですか?」
資金繰りコンサルタントの佐々木真帆です。元大手銀行員として数多の決算書を見てきた経験から断言します。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆多くの経営者が、内部留保を単なる「守りの貯金」と考え、その適正水準や未来を創る「攻めの使い方」を知らないために、会社の成長機会を逃しています。
ご安心ください。この記事では、銀行が融資の際に本当に見ているポイントと、私が現場で実践してきた知見を基に、あなたの会社に最適な内部留保の計算方法から、それを会社の成長に繋げる具体的な投資戦略までを徹底解説します。
記事を読み終える頃には、あなたは資金繰りへの漠然とした不安から解放され、「守り」と「攻め」の財務戦略を使いこなす、自信に満ちた経営者になっているはずです。
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ今、内部留保が重要なのか?元銀行員が語る本当の理由
私が銀行員だった頃、内部留保の重要性を痛感した、忘れられない出来事があります。
銀行員時代に見た「内部留保」で明暗が分かれた2社の事例
それは、同じ地域で同じ建設業を営む、A社とB社のことでした。
2社は売上規模も従業員数もほぼ同じ。
どちらも社長は実直な方で、現場の技術力も高い。
しかし、ある年、大型案件の入金遅延が重なり、2社とも運転資金の追加融資を申し込んできました。
決算書を見ると、その差は歴然でした。
- A社: 毎期きちんと利益を出し、それをコツコツと内部留保として積み上げていた。
- B社: 利益は出ていたものの、役員報酬や配当で社外に流出させることが多く、内部留保は薄かった。
結果として、融資判断は大きく分かれました。
A社には希望額通りの融資が実行され、無事に危機を乗り越えました。
一方、B社は減額回答となり、資金繰りに大変なご苦労をされたと聞いています。



同じ業績でも、内部留保という「会社としての体力」が、いざという時の金融機関からの信用を大きく左右したのです。
この経験は、私にとって資金繰りの本質を教えてくれた、原体験の一つです。
内部留保は会社の「体力」を示す通信簿
少し専門的な話をしますが、内部留保は、決算書の「貸借対照表(B/S)」の右下、「純資産の部」にある「利益剰余金」が主な項目です。
難しく考える必要はありません。
これは、会社が創業以来、どれだけ利益を積み上げてきたかを示す「会社の体力」そのものだと考えてください。
この体力があれば、
- 急なトラブル(売掛金の未回収、災害など)が起きても耐えられる
- 金融機関から「この会社は安定している」と信頼される
- 大きなチャンスが来た時に、借入に頼らず自己資金で勝負できる
という、経営における大きな安心と選択肢を与えてくれるのです。
あなたの会社の適正水準は?今すぐできる内部留保の目安計算
では、あなたの会社には、具体的にいくら内部留保があれば良いのでしょうか。
「月商の3ヶ月分」は本当?業種別に見るリアルな基準
多くの経営者が目安にするのが「月商の3ヶ月分」という基準です。
これは一つの分かりやすい指標ですが、私はコンサルタントとして、これだけを鵜呑みにするのは危険だと考えています。
なぜなら、ビジネスモデルによって、お金の出入りのサイクルが全く異なるからです。
例えば、私がこれまで見てきたケースでは、以下のような違いがありました。
| 業種 | ビジネスモデルの特徴 | 推奨される現預金水準(目安) |
|---|---|---|
| 建設業 | 入金サイクルが長い(工事完了後)。外注費など先行支出が多い。 | 月商の3〜6ヶ月分 |
| ITサービス業(SaaSなど) | 毎月安定した収入が見込める。売上の変動が少ない。 | 月商の2〜3ヶ月分 |
| 飲食・小売業 | 日銭商売でキャッシュインは早いが、仕入れや人件費の支払いも早い。 | 月商の1〜2ヶ月分 |
| 製造業 | 材料の仕入れから製品化、販売、入金までの期間が長い。 | 月商の3〜4ヶ月分 |
このように、自社のビジネスモデルに合わせて考えることが非常に重要です。
コンサルタント推奨!「固定費ベース」での計算方法
そこで私が強くお勧めしているのが、「固定費の6ヶ月分」を一つの安全ラインとして考える方法です。
固定費とは、売上がたとえゼロになっても、毎月必ず出ていくお金のことです。
具体的には、
- 家賃
- 人件費(社会保険料含む)
- リース料
- 水道光熱費などの基本料金
などですね。
なぜ固定費を基準にするのか?
それは、コロナ禍のような不測の事態で売上が急減しても、最低半年間は会社を維持できる体力があるという、極めて実践的なセーフティネットになるからです。
まずはあなたの会社の固定費が月々いくらかを計算し、その6倍の金額を、すぐに使える現預金として確保することを目指してみてください。
これが、精神的な安心にも繋がる、強固な財務基盤の第一歩です。
【銀行はココを見ている】融資に有利な内部留保の作り方
内部留保を厚くすることは、銀行からの信用力を高め、いざという時の資金調達をスムーズにします。
元銀行員として、私たちが決算書のどこを見ていたか、少しだけ裏側をお話しします。
決算書で銀行員が真っ先にチェックする3つのポイント
融資審査の際、担当者は決算書の束をめくりながら、頭の中で企業の姿を組み立てていきます。
その時、特に注目しているのが以下の3点です。
1. 純資産の部の厚み(特に利益剰余金)
まず、純資産がプラスか、マイナス(債務超過)かを見ます。そして、その中身である利益剰余金が毎年着実に増えているかを確認します。
「この会社は、ちゃんと利益を出して、それを貯める力があるな」という証明になるからです。
2. 利益剰余金の「増え方」
単に額が大きいだけでなく、「どのように積み上げられてきたか」というプロセスを重視します。
一発大きな利益で増えたものより、たとえ少額でも5期、10期と連続で黒字を達成し、コツコツ積み上げてきた内部留保は、経営の安定性を示すものとして非常に高く評価されます。
3. 自己資本比率
これは総資産(会社の全財産)のうち、返済不要の自己資本(純資産)がどれくらいの割合を占めるか、という指標です。この比率が高いほど、借金に頼らない健全な経営をしていると判断されます。



業種にもよりますが、まずは30%以上を目指したいところです。
「実質無借金経営」がもたらす絶大な信用力
さらに一歩進んだ財務戦略として、「実質無借金経営」があります。
これは、手元の現預金が借入金の総額を上回っている状態のことです。
完全に借入をゼロにする「無借金経営」も立派ですが、銀行との取引実績がなくなってしまうという側面もあります。
その点、「実質無借金」は、銀行との良好な関係を保ちつつも、「いざとなればいつでも全額返済できますよ」という財務的な余裕を示せるため、金融機関から絶大な信用を得ることができます。
この状態を維持できれば、金利交渉も有利に進められますし、大型の設備投資などで融資が必要になった際も、非常にスムーズに話が進むでしょう。
守りから攻めへ!内部留保を活かす3つの「攻めの投資戦略」
さて、ここまで内部留保の「守り」の側面を話してきましたが、その真価は「攻め」に転じた時にこそ発揮されます。
潤沢な内部留保は、会社の未来を創るための最強の武器なのです。
私がコンサルティングで常に経営者にお伝えしているのは、「守りで固めたキャッシュは、未来のために使うことで初めて価値を生む」ということです。
金庫に眠らせておくだけでは、インフレで価値が目減りする可能性すらあります。
会社の成長ステージに合わせて、適切なリスクを取り、未来の利益を生む「攻めの投資」に振り向ける勇気を持つことが、経営者には求められます。
具体的に、私が支援してきた中小企業で成功した3つの投資戦略をご紹介します。
戦略1:未来の利益を生む「設備投資・研究開発」
私がコンサルしたある製造業のA社は、長年使い古した機械の更新をためらっていました。
しかし、積み上げた内部留保を原資に、最新のNC旋盤を導入することを決断。
結果、生産性は1.5倍に向上し、不良品率も大幅に低下。
これまで受注できなかった高精度の案件も獲得できるようになり、2年で投資額を回収し、今では地域のトップ企業に成長しました。
このように、生産性や競争力を直接高める設備投資は、王道かつ効果の高い戦略です。
戦略2:会社の成長を加速させる「人材投資」
「会社は人なり」と言いますが、これは綺麗事ではありません。
あるIT企業のB社は、業界内で人材の引き抜きが激化する中、内部留保を活用して社員の給与ベースを10%引き上げ、さらに資格取得支援や外部研修制度を充実させました。
当初はコスト増を懸念する声もありましたが、結果的に優秀な人材の離職率が劇的に低下。
社員のモチベーションとスキルが向上したことで、顧客満足度も上がり、新たな大型契約に繋がりました。
「人への投資」は、最もリターンの大きい投資の一つだと私は確信しています。
戦略3:事業拡大を一気に実現する「M&A・新規事業」
潤沢な内部留保があれば、M&A(企業の買収)や新規事業への挑戦といった、非連続な成長も視野に入れることができます。
例えば、私のクライアントである広告代理店のC社は、内部留保を元手に、かねてから連携していたWeb制作会社をM&Aでグループに迎え入れました。
これにより、企画提案から制作、運用までを一気通貫で提供できるようになり、大手企業とも渡り合える競争力を手に入れました。
もちろんリスクは伴いますが、自社だけでゼロから立ち上げるよりも、時間と労力を大幅に短縮できる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
Q: 内部留保と現預金は同じものですか?
A: いいえ、異なります。
これは非常に重要なポイントです。内部留保は会計上の利益の蓄積であり、必ずしも現金として会社に残っているわけではありません。
設備や在庫、売掛金などに姿を変えていることもあります。
私が銀行員だった頃も、この違いを理解していない経営者は多かったです。
重要なのは、決算書上の内部留保の額だけでなく、そのうち、どれだけが現預金としてすぐに使える状態にあるか(キャッシュフロー)を把握しておくことです。
Q: 内部留保が多すぎると税金がかかると聞きましたが本当ですか?
A: はい、「留保金課税」という制度があります。
ただし、これは資本金1億円超の特定の同族会社が対象で、多くの中小企業には直接関係ありません。
しかし、税金とは別の観点で、過度な内部留保は資金効率の低下を招くリスクもあります。
先ほどお話ししたように、会社の成長のために「攻めの投資」に回すことを常に検討すべきです。
Q: 赤字決算の年でも、内部留保を意識すべきことはありますか?
A: もちろんです。むしろ、赤字の年こそ重要です。
赤字になると内部留保(利益剰余金)は減少しますが、だからこそ手元の現預金をいかに維持するかが生命線になります。
銀行員は、赤字の理由とその後の改善策、そして自己資本(内部留保を含む)がどれだけ残っているかを厳しく見ます。
たとえ赤字でも、これまで積み上げてきた内部留保のおかげで自己資本比率を高く保てていれば、「体力のある会社だ」と判断され、融資の可能性は残ります。
Q: 個人事業主の場合、内部留保はどう考えればいいですか?
A: 個人事業主には法人としての「内部留保」という会計上の概念はありませんが、考え方は全く同じです。
事業用の資金として、生活費とは別に「事業用の蓄え」をどれだけ確保できているかが重要です。
目安としては、法人の考え方と同じく「固定費の6ヶ月分」を事業用口座に確保しておくことをお勧めします。
これにより、安心して事業に集中することができます。
まとめ
社長、あなたの会社に残すべきお金の額、そしてその使い道は見えてきたでしょうか。
内部留保は、不測の事態に備える「守りの盾」であると同時に、未来の成長を掴むための「最強の武器」でもあります。



元銀行員として、そして現役の資金繰りコンサルタントとして私が最も伝えたいのは、この守りと攻めのバランスです。
まずは、あなたの会社にとっての安全ラインである「固定費の6ヶ月分」を把握し、強固な財務基盤を築いてください。
そして、そこから生まれる余裕を、未来への投資に大胆に振り向けてください。
資金繰りの不安を自信に変え、あなたの会社の成長を加速させる一歩を、今日から踏み出しましょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる