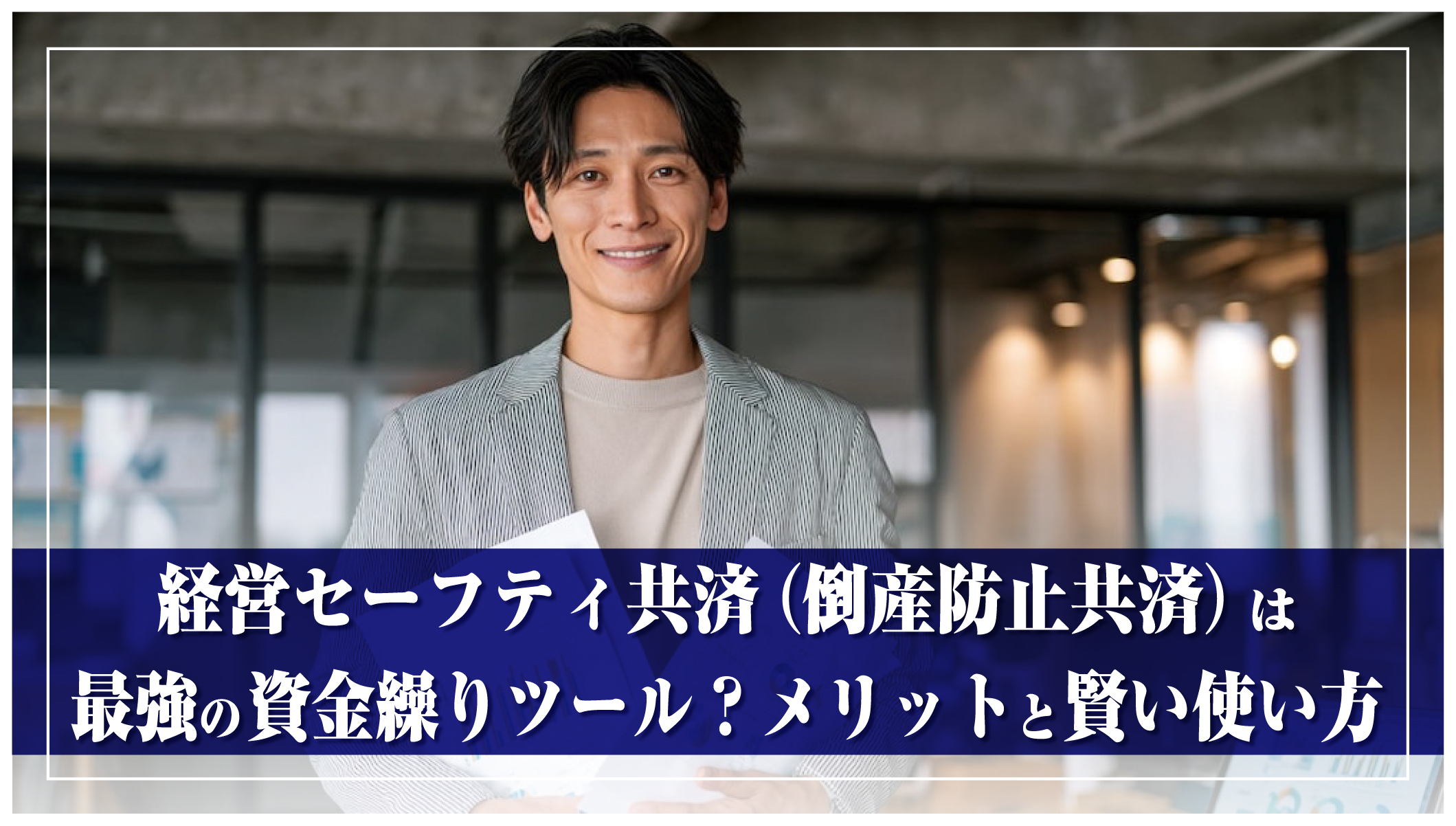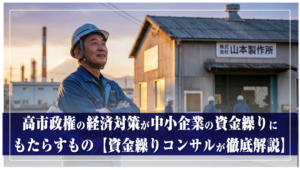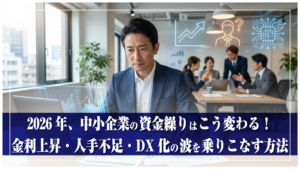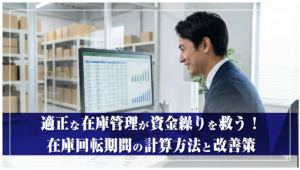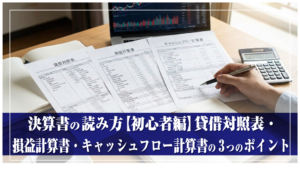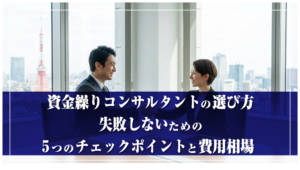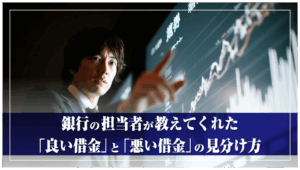「経営セーフティ共済は、ただの節税対策だと思っていませんか?」
もしそうなら、あなたは年間数百万円の利益を逃すだけでなく、いざという時に会社を守る「最強の武器」を見過ごしているかもしれません。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆こんにちは。元銀行員の資金繰りコンサルタント、佐々木真帆です。銀行員時代、私は取引先の連鎖倒産という不運で、素晴らしい会社が涙をのむ姿を何度も見てきました。
その経験から断言します。経営セーフティ共済は、使い方一つで「守りの保険」にも「攻めの資金調達ツール」にもなる、経営者のための制度です。
本記事では、単なる制度解説では終わりません。私がこれまで100社以上の財務改善に携わってきた知見から、「圧倒的な節税効果」「緊急時の無担保融資」「出口戦略まで見据えた賢い使い方」を徹底的に解説します。
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
そもそも経営セーフティ共済とは?元銀行員が3分で要点を解説
まずは、この制度の基本を簡単におさらいしましょう。
難しく考える必要はありません。ポイントは3つだけです。
制度の目的は「連鎖倒産」の防止
経営セーフティ共済は、国が管轄する中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、いわば「経営者のためのセーフティネット」です。
銀行員時代、私は何度も連鎖倒産の悲劇を見てきました。
例えば、ある建設会社は、主要な取引先だった元請け企業が突然倒産したことで、数千万円の売掛金が回収不能になりました。
手元の資金はあっという間に底をつき、従業員の給与も払えない状況に…。
技術力も実績もある素晴らしい会社だったのに、本当に悔しい結末でした。
このような悲劇を防ぐために作られたのが、この制度の本来の目的なのです。
押さえるべき3つの基本機能「積立」「借入」「解約」
この制度の機能は、非常にシンプルです。
1. 【積立】掛金を積み立てて、将来に備える(しかも節税しながら)
毎月コツコツ掛金を積み立てます。この掛金は、税金の計算上「損金」または「必要経費」として扱われるため、節税につながります。
2. 【借入】万が一の時に、積み立てた額以上のお金を借りられる
もし取引先が倒産してしまったら、積み立てた掛金総額の最大10倍(上限8,000万円)まで、無担保・無保証人でスピーディーにお金を借りることができます。
3. 【解約】必要になった時に、積み立てたお金を戻せる
一定期間以上積み立てれば、解約した時に「解約手当金」として、支払った掛金の全額が戻ってきます。
この3つの機能を、会社の状況に合わせてどう使いこなすか。
それが、資金繰りを劇的に改善するカギとなります。
【メリット】資金繰りのプロが語る!経営セーフティ共済の5つの強み
では、具体的にこの制度がどう資金繰りに効いてくるのか、プロの視点から5つの強みをお伝えします。
1. 圧倒的な節税効果:年間最大240万円の損金算入
最大のメリットは、やはり節税効果です。
掛金は年間最大240万円まで、全額を損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)にできます。
例えば、利益が1,000万円出た期に、年間上限の240万円を掛金として支払ったとします。
すると、課税対象となる所得は760万円(1,000万円 – 240万円)に圧縮されます。
法人税率が約30%だとすれば、約72万円(240万円 × 30%)もの税負担を軽減できる計算です。
これは、お金を社外に支払うのではなく、将来のために「積み立て」ながら実現できるのが大きなポイント。
利益が出た期にしっかり活用することで、会社の内部留保を効率的に厚くしていくことができます。
2. 緊急時の資金調達:無担保・無保証での借入
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最大8,000万円)まで、無利子・無担保・無保証人で借入が可能です。
元銀行員として断言しますが、これは本当に破格の条件です。
銀行で緊急の融資を申し込んでも、審査には時間がかかりますし、担保や保証人を求められるケースがほとんどです。
「今すぐ資金が必要なのに…!」という時に、迅速に、かつ誰にも迷惑をかけずに資金を調達できるこの仕組みは、まさに命綱と言えるでしょう。
3. 「もしも」の保険:取引先倒産以外の「一時貸付金制度」
意外と知られていないのですが、私が「最強のツール」と呼ぶ理由の一つが、この「一時貸付金制度」です。
これは、取引先が倒産していなくても、急に資金が必要になった場合に、解約手当金の95%を上限として低金利(年0.9% ※2024年7月時点)で借入れができる制度です。
私がコンサルしたあるIT企業は、大型案件の受注が決まったものの、開発に必要な機材の購入費が一時的に不足しました。
銀行融資を待っていては間に合わない…という状況で、この一時貸付金制度を活用。
わずか数日で資金を調達し、無事にプロジェクトをスタートさせることができました。
このように、緊急時だけでなく、ビジネスチャンスを逃さないための「攻めの資金調達」としても使えるのです。
4. 柔軟な掛金設定:経営状況に合わせた調整が可能
掛金は月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、いつでも増額・減額が可能です。
会社の業績が良い時は増額して節税効果を高め、苦しい時は減額して負担を軽くする、といった柔軟な対応ができます。
このコントロールのしやすさが、中小企業の不安定な経営状況に寄り添ってくれる、非常にありがたい点です。
5. 高い返戻率:40ヶ月以上で元本100%が戻る
40ヶ月(3年4ヶ月)以上、掛金を納付すれば、解約時に支払った掛金の全額が戻ってきます。
つまり、節税しながら積み立てたお金が、掛け捨てにならずに資産として残るのです。



私はこれを「簿外資産(帳簿に載らない資産)」と呼んでいます。
決算書には現れないけれど、いざという時に会社を救う、あるいは将来の大きな投資や経営者の退職金の原資となる、隠れた虎の子です。
【デメリットと注意点】元銀行員だからこそ指摘できる落とし穴
これほど強力な制度ですが、使い方を間違えると大きな落とし穴にはまる危険もあります。
良い面だけでなく、厳しい現実もしっかりお伝えするのが私の役目です。
1. 解約時の税金問題:出口戦略なき加入は危険
これが最大の注意点です。
解約時に戻ってくる解約手当金は、全額がその期の利益(益金または事業所得)として扱われ、課税対象となります。
【要注意】出口戦略がないと、こうなる!
例えば、800万円を積み立てて、利益がほとんどない年に解約したとします。
その年は、いきなり800万円の利益が上乗せされることになり、多額の税金が発生します。
「節税したはずが、結局将来まとめて払うことになった…」これでは本末転倒です。
だからこそ、加入する時から「いつ、何のために解約するか」という出口戦略が不可欠なのです。
具体的には、役員退職金の支払いなど、大きな損金が出るタイミングで解約するのがセオリーです。
2. 短期解約は元本割れのリスク
「40ヶ月以上で100%戻る」ということは、裏を返せば、それ未満での解約は元本割れするということです。
特に12ヶ月未満で解約すると、1円も戻ってこない「全額掛け捨て」になってしまいます。
短期的な資金繰りのために安易に加入・解約を繰り返すのは絶対にやめてください。
3. 借入は実質「有利子」?掛金控除の仕組み
共済金の借入は「無利子」とされていますが、注意が必要です。
借入額の10分の1に相当する金額が、積み立てた掛金から相殺(控除)されてしまうのです。
例えば、800万円を借り入れた場合、80万円分の掛金が消滅します。
これを実質的なコストと考えると、決してゼロコストではありません。
状況によっては、銀行の短期借入の方がトータルコストを抑えられる場合もありますので、冷静な比較検討が必要です。
4. 加入資格の制限:設立1年未満は加入不可
「事業を1年以上継続していること」が加入要件のため、創業したばかりのスタートアップ企業はすぐに利用できません。
まずは事業を軌道に乗せ、1年経ったタイミングで加入を検討しましょう。
【実践編】資金繰りのプロが教える経営セーフティ共済の賢い使い方
では、これらのメリット・デメリットを踏まえ、具体的にどう活用すればよいのか。
私が実際にコンサルティングでお伝えしている3つの賢い使い方をご紹介します。
ケース1:利益の繰り延べと将来への投資原資確保
利益が多く出た年度に、前納制度(1年分を前払いできる)も活用して上限まで掛金を拠出します。
これを数年間続け、数年後に計画している設備投資や新規事業の立ち上げといった大きな支出が見込まれるタイミングで解約するのです。
これにより、税負担を平準化しつつ、将来の成長に向けた投資原資を計画的に確保することができます。
ケース2:銀行融資と組み合わせるハイブリッド資金調達
元銀行員の視点からお話しすると、銀行は融資審査の際、企業の「リスク管理体制」も見ています。
経営セーフティ共済に加入していることは、「万が一の備えをしっかりしている堅実な経営者」というポジティブな印象を与え、審査において心証が良くなる可能性があります。
緊急時には、まずセーフティ共済の一時貸付金で当座をしのぎ、その間に落ち着いて銀行融資の手続きを進める、といったハイブリッドな活用法も非常に有効です。
ケース3:役員退職金と合わせた究極の出口戦略
これは、最も効果的な出口戦略の一つです。
経営者が引退するタイミングに合わせて共済を解約し、その解約手当金を役員退職金の支払いに充てます。
役員退職金は、税制上非常に優遇された大きな損金として計上できます。
そのため、解約手当金という大きな利益と相殺することができ、解約時にかかる税金を劇的に圧縮することが可能なのです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ステップ1 | 長年にわたり掛金を積み立てる(例:上限の800万円) |
| ステップ2 | 経営者の退任時期に合わせて共済を解約する |
| ステップ3 | 解約手当金(800万円)がその期の利益となる |
| ステップ4 | 同時に役員退職金(例:1,000万円)を損金として計上する |
| 結果 | 利益(800万円)と損金(1,000万円)が相殺され、解約手当金にかかる税負担を大幅に軽減できる |
よくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
Q: 個人事業主でも加入できますか?
A: はい、事業を1年以上継続していれば個人事業主の方も加入できます。銀行員時代、多くの個人事業主の方が万一の備えとして活用していました。法人成りした場合も、個人事業主としての事業期間が通算される場合がありますので、専門家にご相談ください。
Q: 赤字の年でも掛金を払い続けるべきですか?
A: 資金繰りに余裕があれば、将来の利益が出る期に備えて積み立てを続ける選択肢もあります。しかし、無理は禁物です。掛金の減額も可能なので、キャッシュフローを最優先に判断すべきです。資金繰りコンサルタントとしては、まず足元の現金を確保することを推奨します。
Q: 解約手当金はいつ振り込まれますか?
A: 手続き完了後、通常は約2週間から1ヶ月程度で振り込まれます。ただし、書類に不備があると遅れることも。銀行融資と違い、比較的スピーディーなのが特徴ですが、急な資金需要に備えるなら、事前に手続きの流れを確認しておくことが重要です。
Q: 2024年10月の制度改正で何が変わりましたか?
A: 主な変更点は、解約後2年以内に再加入した場合、その掛金が損金算入できなくなったことです。 これは短期的な節税目的での利用を抑制するための措置です。長期的な視点での活用がより一層重要になったと言えます。
Q: 銀行融資とセーフティ共済の貸付、どちらを優先すべきですか?
A: 元銀行員としてお答えすると、ケースバイケースです。緊急性や必要額、金利、信用情報への影響などを総合的に判断する必要があります。セーフティ共済の貸付は迅速ですが、掛金が減るデメリットも。まずは顧問税理士や私のような資金繰りの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ:会社の心臓部を守り、未来を創るために
経営セーフティ共済は、単なる節税商品や倒産時の保険ではありません。
使い方次第で、攻守にわたって活用できる、非常に強力な「資金繰りツール」です。
しかし、その力を最大限に引き出すには、出口戦略を含めた長期的な計画が不可欠です。
銀行員として多くの企業の栄枯盛衰を見てきた経験から断言できるのは、「資金繰りは会社の心臓部」であるということ。
この記事を参考に、ぜひ貴社の財務戦略の一つとして、経営セーフティ共済の最適な活用法を検討してみてください。
もし、ご自身の判断に迷う場合は、決して一人で抱え込まないでください。
あの日の私が救えなかった経営者のように、あなたが悔し涙を流すことのないよう、いつでも専門家を頼ってほしいと心から願っています。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる