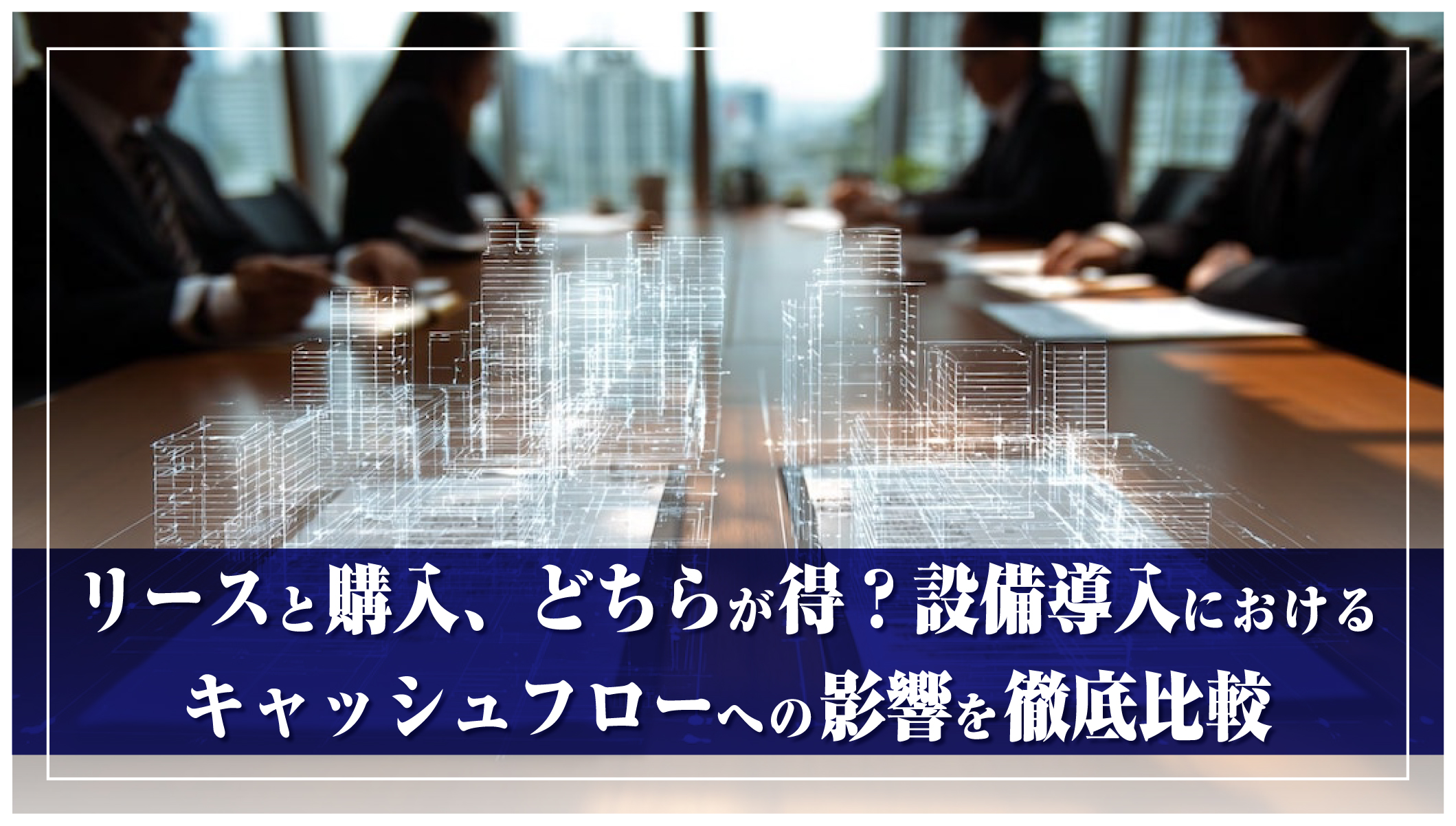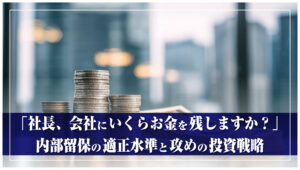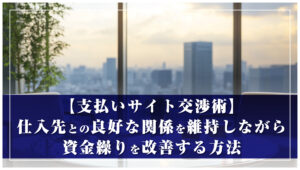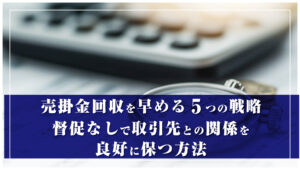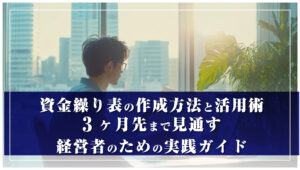「新しい設備は導入したいが、手元の現金は運転資金として絶対に減らしたくない…」
中小企業やスタートアップの経営者様なら、誰もが抱えるこのジレンマ。その選択一つで、会社の心臓部であるキャッシュフローが大きく変わることをご存知ですか?
 佐々木 真帆
佐々木 真帆元銀行員の財務コンサルタント、佐々木真帆です。かつて融資担当者として、素晴らしい技術がありながら資金繰りが原因で成長機会を逃す企業を数多く見てきました。
あなたには、決して同じ思いをしてほしくありません。
結論から言えば、リースか購入かの判断は「キャッシュフローの安定性」「事業計画との整合性」「銀行からの見え方」という3つの軸で決まります。
【この記事の結論】リース vs 購入 メリット・デメリット早わかり表
| 項目 | リースが有利なケース | 購入が有利なケース |
|---|---|---|
| 初期費用 | ◎ とにかく抑えたい 手元資金を温存し、運転資金を確保したい場合に最適。 | △ 多額の現金が必要 自己資金が潤沢でない限り、キャッシュフローを圧迫するリスクがある。 |
| 総支払額 | △ 割高になる 金利や手数料が含まれるため、長期的には購入より総額が高くなる。 | ◎ 最も安く済む 特に自己資金の場合、金利などがかからず総コストを抑えられる。 |
| 所有権 | × 自社の資産にならない 契約終了後は返却か再リースが基本。自由に売却・処分はできない。 | ◎ 自社の資産になる 自由に利用・売却でき、企業の信用力向上にも繋がる可能性がある。 |
| 会計処理 | ◎ シンプル 月々のリース料を「経費」として処理できるため、管理がしやすい。 | △ 複雑 資産計上と毎年の「減価償却」が必要で、会計処理が煩雑になる。 |
| 最新設備 | ◎ 対応しやすい 技術革新が速いIT機器などは、契約満了時に最新モデルへ入れ替え可能。 | △ 陳腐化リスク 一度購入すると、旧式化しても簡単に買い替えられない。 |
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
【結論】リースか購入、どっち?元銀行員が教える判断の3つの軸
設備投資の方法で迷ったら、まずこの3つの軸で自社の状況を整理してみてください。私がいつも経営者の方にお伝えしている、意思決定のための最も重要な視点です。
軸1:キャッシュフローの安定性
- 手元資金を温存したいか?
- 毎月の支出を平準化したいか?
この問いに「YES」と答えるなら、リースが有力な選択肢になります。
特に、創業期や成長期の企業にとって、手元資金は会社の命綱です。銀行員時代、黒字なのに急な売掛金の入金遅れで資金がショート寸前になった会社を何社も見てきました。
多額の初期費用をかけずに設備を導入でき、月々の支払額が一定のリースは、キャッシュフローの安定に大きく貢献します。
軸2:将来の事業計画との整合性
- 導入する設備の陳腐化スピードは速いか?
- 長期的にその設備を使い続けるか?
例えば、数年で性能が劇的に向上するパソコンやIT関連機器の場合、購入してしまうとすぐに旧式化してしまいます。
リースであれば、契約期間を技術の進化サイクルに合わせて設定し、常に最新の設備に入れ替えるといった戦略が可能です。
逆に、10年以上使い続けるような頑丈な工作機械であれば、長期的なコストが安い購入の方が合理的かもしれません。
あなたの事業計画と、設備のライフサイクルを照らし合わせてみてください。
軸3:財務戦略と銀行との関係
- 財務諸表をどう見せたいか?
- 今後の融資戦略にどう影響するか?
これは少し高度な視点ですが、非常に重要です。
リースは、多くの中小企業においてB/S(貸借対照表)に資産・負債として計上しない「オフバランス処理」が可能です。 これにより、B/Sをスリムに見せることができます。
一方、購入(特に借入)はB/Sに資産と負債が計上されます。
どちらが良いかは一概に言えません。後の章で詳しく解説しますが、銀行がこの違いをどう見るかを理解した上で、戦略的に選択する必要があります。
そもそも何が違う?リースと購入の基本を1分でおさらい
言葉は聞いたことがあっても、その違いを正確に説明できる方は意外と少ないものです。まずは基本をしっかり押さえましょう。
所有権・費用・会計処理の違いが一目でわかる比較表
| 項目 | リース(ファイナンス・リース) | 購入(自己資金) | 購入(銀行借入) |
|---|---|---|---|
| 所有権 | リース会社 | 自社 | 自社 |
| 初期費用 | 原則不要 | 多額の現金が必要 | 頭金などが必要な場合も |
| 月額費用 | リース料(定額) | なし | 元本+金利の返済 |
| 総支払額 | 割高(金利・手数料等) | 最も安い | 自己資金よりは高い |
| 会計処理 | 経費処理(賃貸借処理)※ | 資産計上 | 資産計上 |
| 固定資産税 | リース会社が支払い(料込) | 自社で支払い | 自社で支払い |
| 減価償却 | 不要 ※ | 必要 | 必要 |
※多くの中小企業で認められている会計処理です。
【専門用語を噛み砕き解説】減価償却と損金算入
少し会計の話をさせてください。ここを理解すると、キャッシュフローへの影響がよりクリアになります。
購入した場合
設備は会社の「資産」になります。そして、その価値は年々下がっていきます。この価値の減少分を、設備の耐用年数にわたって毎年少しずつ経費として計上していくのが「減価償却」です。
ポイントは、お金が出ていくタイミング(購入時)と、経費になるタイミング(減価償却期間)がズレることです。
リースの場合
多くの中小企業では、毎月支払うリース料をそのまま「経費」として計上できます。 これを「損金算入」と言います。
こちらは、お金が出ていくタイミングと経費になるタイミングが一致するため、非常にシンプルです。
【キャッシュフロー重視派へ】リース導入のメリット・デメリット
メリット:初期投資ゼロで手元資金を確保できる安心感
これが最大のメリットです。
設備購入で数百万円の現金が一気に出ていくと、急なトラブルや大きな受注があった際の運転資金が不足する事態に陥りかねません。
リースなら、その資金を手元に残したまま事業に必要な設備を導入できます。この「手元資金の余裕」は、経営者の精神的な安定にも繋がります。
メリット:支払額が平準化され、資金繰り計画が立てやすい
リース料は毎月定額なので、将来の支出予測が非常に簡単です。
「来月、いくらキャッシュが出ていくか」が明確になるため、どんぶり勘定を防ぎ、精度の高い資金繰り計画を立てることができます。
デメリット:総支払額は割高になる
リース料には、物件価格に加えて金利、手数料、固定資産税、保険料などが含まれています。
そのため、最終的に支払う総額は、自己資金で購入するよりも割高になります。
デメリット:原則、中途解約ができない縛り
ファイナンス・リースは、原則として契約期間中の解約ができません。
もし解約する場合は、残りのリース料に相当する違約金を請求されることがほとんどです。
事業計画が大きく変わる可能性がある場合は、この点がリスクになることを覚えておきましょう。
【総コスト・所有権重視派へ】購入のメリット・デメリット
メリット:長期的に見れば総支払額が最も安い
金利や手数料がかからないため、特に自己資金で購入する場合、総コストを最も抑えられます。
長期間使い続けることが確定している設備であれば、購入のメリットは大きくなります。
メリット:自社の資産となり、自由に使える・売却できる
所有権が自社にあるため、自由に改造したり、不要になった際に売却して現金化したりすることが可能です。
また、B/Sに資産として計上されることは、企業の信用力向上に繋がる側面もあります。
デメリット:初期に多額の資金流出が発生する
これが購入における最大のリスクです。
私がコンサルしたA社は、業績が好調だったため、利益を使って最新の機械を自己資金で購入しました。しかしその直後、想定外の大口受注が舞い込み、材料の仕入れに必要な運転資金が足りなくなってしまったのです。
手元資金の減少が、成長のチャンスを逃すことに繋がりかねないという典型的な事例です。
デメリット(借入の場合):銀行審査と金利負担
銀行から借入を行う場合、当然ながら審査が必要です。事業計画や財務状況を厳しく見られますし、時間もかかります。
また、金利負担が発生し、変動金利の場合は将来の金利上昇リスクも考慮しなければなりません。
【最重要】キャッシュフローへの影響を徹底シミュレーション
言葉の説明だけではイメージが湧きにくいと思いますので、具体的な数字で比較してみましょう。
前提条件:500万円の工作機械を5年間使用する場合
- 対象設備: 工作機械 500万円(法定耐用年数10年、定額法で償却)
- 使用期間: 5年間(60ヶ月)
- 法人税率: 30%(簡略化のため)
パターン別・5年間のキャッシュフロー推移比較
| パターン | ① リース | ② 自己資金で購入 | ③ 銀行借入で購入 |
|---|---|---|---|
| 前提 | リース料率: 2.0% 月額: 100,000円 | – | 借入額: 500万円 金利: 2.5%(元利均等) 月返済: 約90,000円 |
| 初年度のCF | -84万円 (支出120万 – 節税36万) | -485万円 (支出500万 – 節税15万) | -100万円 (返済108万 – 節税8万)※ |
| 5年間の支出合計 | 600万円 | 500万円 | 約540万円 |
| 5年間のCF合計 | -420万円 (支出600万 – 節税180万) | -425万円 (支出500万 – 節税75万) | -448万円 (支出540万 – 節税92万)※ |
| 特徴 | 初期の資金流出が最も少ない | 総支払額は最も安いが、初期負担が非常に重い | 初期負担は抑えられるが、総支払額はリースに近づく |
※借入の返済額のうち、利息部分のみが経費(損金)となります。
分析:あなたの会社はどのパターンを選ぶべきか?
創業期・成長期
手元資金の温存が最優先。初期のキャッシュアウトが圧倒的に少ない「①リース」が最適です。
安定期(資金潤沢)
資金に余裕があり、長期的にコストを抑えたいなら「②自己資金での購入」が最も経済的です。
安定期(資金は運転資金に)
手元資金は残しつつも、資産として保有したい場合は「③銀行借入での購入」が選択肢になります。
元銀行員が明かす!リースと購入が融資審査に与える「本当の影響」
ここは、私がこの記事で最もお伝えしたい部分です。多くの経営者が誤解しているポイントでもあります。
銀行は「オフバランス」をどう見ているか?
リースがB/Sに載らない「オフバランス取引」は、一見すると負債がないように見え、財務指標が良く見えるメリットがあります。
しかし、これは危険な誤解です。
銀行員は融資審査の際、決算書に添付される「リース契約に関する注記」を必ずチェックします。そこに記載されている「未経過リース料」を、私たちは実質的な負債として捉え、企業の返済能力を分析します。
「オフバランスだから銀行にはバレない」という考えは絶対に通用しません。
融資枠(コミットメントライン)への影響
「リースを使えば、銀行からの融資枠を温存できる」という話は、半分は本当です。
設備資金をリースで賄えば、その分、運転資金の融資を銀行に申し込みやすくなるのは事実です。
ただし、リース契約が増えすぎて月々の支払いが大きくなれば、当然ながら返済能力が低いと判断され、新たな融資の審査は厳しくなります。リースも借入も、キャッシュフローを圧迫するという点では同じなのです。
決算書の見え方と格付けへのインパクト
銀行は、決算書の内容を点数化して企業を「格付け」し、融資の可否や金利を判断します。
- リース: B/Sはスリムに見えますが、前述の通り、実質的な負債として評価されます。
- 購入(借入): B/Sの負債は増えますが、同時に「資産」も増えます。自己資本がしっかりしていれば、企業の規模や体力を示すものとしてポジティブに評価されることもあります。
重要なのは、どちらが有利かではなく、自社の財務状況を正直に示し、それを基にした堅実な事業計画を語れるかどうかです。見せかけの数字でごまかそうとすると、かえって信頼を失う結果になります。
よくある質問(FAQ)
Q: リースと購入、結局どちらが節税になりますか?
A: 一概には言えません。短期的な節税効果を狙うなら、支払額をそのまま経費にしやすいリースが分かりやすいです。一方で、購入の場合は「中小企業経営強化税制」などを活用して、初年度に即時償却したり、税額控除を受けたりできる可能性があります。 目先の節税だけでなく、キャッシュフロー全体で判断することが重要です。
Q: リースの審査は購入のための銀行融資より甘いというのは本当ですか?
A: 一般的に、リース会社の審査は銀行融資よりスピーディーで通りやすい傾向があります。 これは、リース会社が物件そのものの価値(万が一の際の売却価値)も担保と見なすなど、銀行とは審査の視点が異なるためです。ただし、その分、金利は銀行借入より高くなる傾向があります。
Q: 中古の設備を導入したいのですが、リースは可能ですか?
A: はい、中古設備に対応したリースも存在します。新品に比べてリース料を抑えられるメリットがありますが、物件の状態やリース会社によって条件が異なります。契約時には、保証やメンテナンスの範囲を必ず確認しましょう。
Q: リース期間が終了した後はどうなりますか?
A: 主に「再リース(契約延長)」「返却」「買取り」の選択肢があります。再リースの場合、年間リース料が以前の10分の1程度になるなど、格安で利用を続けられることが多いです。 どの選択肢があるかは契約によって異なるため、契約前に必ず確認しておくことが資金繰り計画上、重要です。
Q: 最近よく聞く「オペレーティング・リース」と何が違うのですか?
A: 本記事で主に解説しているのは、実質的に分割払いで購入するのに近い「ファイナンス・リース」です。 一方、「オペレーティング・リース」はレンタルに近い性質を持ち、短期利用を前提としています。 中小企業が設備を長期的に使用する場合は、ファイナンス・リースが一般的です。
まとめ
設備投資におけるリースと購入の選択は、単なる損得計算ではありません。
それは、あなたの会社のキャッシュフロー、事業計画、そして未来の財務戦略そのものを左右する重要な経営判断です。



元銀行員、そして資金繰りコンサルタントとして数々の現場を見てきた私からお伝えしたいのは、「自社の今の状況と将来のビジョンに最適な選択をすること」の重要性です。
- 手元資金を何よりも優先したい創業期なら、リース。
- 資金が潤沢で、総コストを抑えたい安定期なら、購入。
この記事のシミュレーションや元銀行員の視点が、皆様の意思決定の一助となれば幸いです。
まずは自社のキャッシュフローを正確に把握することから始めてみてください。それが、成長への確かな一歩となります。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる