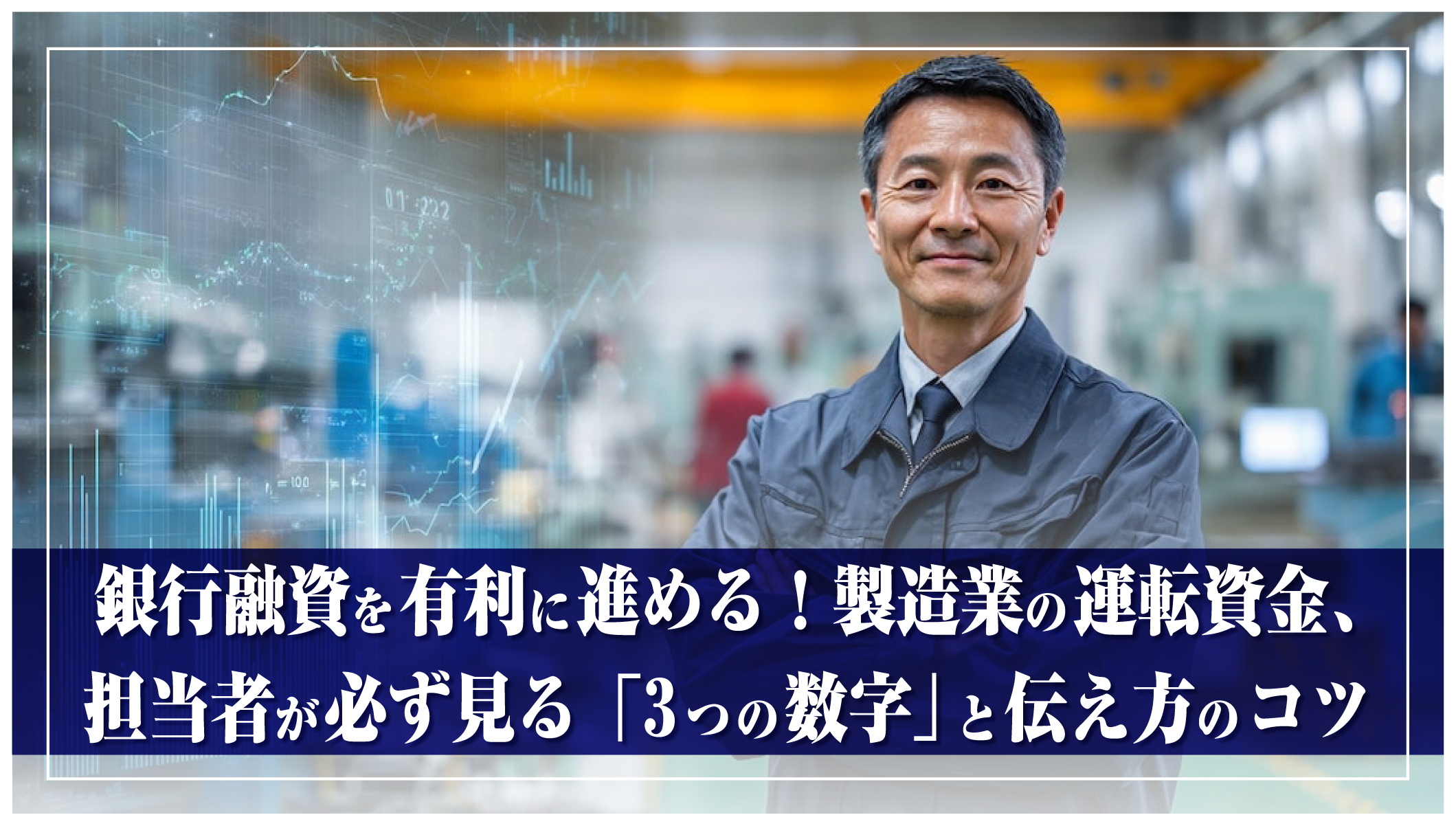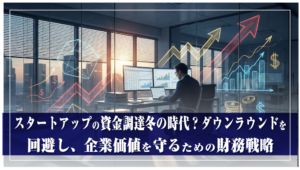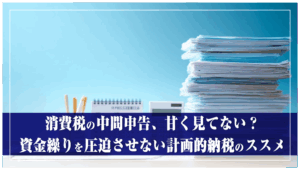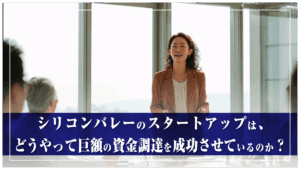「受注は増えているのに、なぜか手元の現金が足りない…」
 佐々木 真帆
佐々木 真帆製造業特有のその悩み、かつて銀行の融資担当だった私には痛いほどわかります。
はじめまして。元銀行員で、現在は中小企業の財務コンサルタントをしている佐々木と申します。銀行員時代、素晴らしい技術がありながら資金繰りが原因で涙をのむ経営者を数多く見てきました。
もう、あなたに同じ思いはしてほしくありません。
この記事では、銀行員が運転資金の融資で必ずチェックする「3つの数字」と、交渉を有利に進める「伝え方のコツ」を徹底解説します。
【この記事の結論】製造業の運転資金|融資審査で銀行が見る3つの重要指標
銀行が製造業の運転資金融資を審査する際、返済能力を判断するために特に重要視するのが以下の「3つの回転期間」です。自社の状況が健全か、以下の視点で確認しましょう。
| 重要指標(3つの数字) | 銀行が注目するポイント(なぜ重要か?) |
|---|---|
| ① 売上債権回転期間 (代金回収の速さ) | 回収が遅すぎないか? 目安は「2ヶ月前後」。これより長いと、資金繰りの悪化や貸し倒れリスクを懸念されます。 |
| ② 棚卸資産回転期間 (在庫の健全性) | 不良在庫を抱えていないか? 期間が長いと、売れ残りの「不良在庫」や、最悪の場合「粉飾決算」の可能性まで疑われます。 |
| ③ 買入債務回転期間 (支払いの適切性) | 支払い期間は適切か? 短すぎると資金繰りを圧迫し、逆に長すぎると「下請けいじめ」と見なされ、企業の信用問題に繋がります。 |
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ製造業は運転資金が枯渇しやすいのか?元銀行員が語る3つの理由
そもそも、なぜ製造業は他の業種に比べて運転資金が不足しがちなのでしょうか。
それは、製造業特有のビジネスモデルに原因があります。
銀行員は、この構造的な課題を深く理解した上で、あなたの会社を見ています。
材料の先行仕入れと支払いサイトの問題
製造業は、製品を作るために、必ず先に原材料を仕入れなければなりません。
例えば、仕入れ代金の支払いは「翌月末」、しかし製品が売れて売上金が入金されるのは「翌々月末」というケースは珍しくありません。
この「支払いが先、入金が後」という時間のズレ(支払いサイトのギャップ)が大きくなればなるほど、手元の現金はどんどん減っていきます。
これが、製造業の資金繰りを圧迫する最大の要因です。
受注増が引き起こす「黒字倒産」のリスク
「売上が増えれば資金繰りは楽になるはずだ」
多くの方がそう思われるかもしれません。しかし、ここには大きな落とし穴があります。
受注が増えれば、当然、仕入れる材料の量も増え、人件費や外注費も増加します。
つまり、売上が増えるほど、先に出ていくお金(増加運転資金)も増えるのです。
このメカニズムを理解していないと、帳簿上は黒字なのに、支払いに必要なお金が足りずに倒産してしまう「黒字倒産」に陥る危険性があります。
私も銀行員時代、この悲しい現実を何度も目の当たりにしてきました。
在庫管理の難しさと資金の固定化
あなたの会社の倉庫にある製品や仕掛品、原材料。
これらは貸借対照表上では「棚卸資産(在庫)」という立派な資産です。
しかし、これらは売れて現金化されるまでは、一円も生み出さない「寝ているお金」に他なりません。



過剰な在庫や、売れる見込みのない不良在庫を抱えることは、運転資金を倉庫に固定化させ、資金繰りを悪化させる大きな要因になります。
銀行員が在庫の量だけでなく、「その在庫は本当に売れるのか?」という中身(鮮度)を気にするのは、まさにこのためです。
銀行担当者が必ず見る!製造業の運転資金審査「3つの重要指標」
では、銀行の担当者は、決算書のどこを見てあなたの会社の資金繰りの状態を判断しているのでしょうか。
それが、これからお伝えする「3つの回転期間」です。
少し専門的に聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。一つひとつ、分かりやすく解説します。
まずは、この表で全体像を掴んでください。
| 重要指標 | 計算式 | この数字が示すこと | 銀行はこう見る! |
|---|---|---|---|
| ① 売上債権回転期間 | 売上債権 ÷ (売上高 ÷ 12) | 売った代金を回収するまでの期間 | 期間が長いと「回収に問題があるのでは?」と懸念 |
| ② 棚卸資産回転期間 | 棚卸資産 ÷ (売上原価 ÷ 12) | 在庫が売れるまでの期間 | 期間が長いと「不良在庫があるのでは?」と懸念 |
| ③ 買入債務回転期間 | 買入債務 ÷ (売上原価 ÷ 12) | 仕入れ代金を支払うまでの期間 | 期間が短すぎると資金繰りを圧迫。長すぎると「下請けいじめでは?」と懸念 |
① 売上債権回転期間:回収サイクルの健全性を示す指標
これは、「売った代金を回収するのに、平均で何か月かかっているか」を示す数字です。
売上債権とは、売掛金や受取手形のことですね。
計算式:売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ (売上高 ÷ 12ヶ月)
この期間が、同業他社や業界平均(製造業では2ヶ月前後が目安)と比べて著しく長い場合、銀行員は「回収の遅い取引先があるのでは?」「貸し倒れのリスクはないか?」と懸念を抱きます。
② 棚卸資産回転期間:在庫の効率性を示す指標
これは、「仕入れた在庫が、製品となって売れるまでに何か月かかっているか」を示す数字です。
計算式:棚卸資産回転期間 = 棚卸資産 ÷ (売上原価 ÷ 12ヶ月)
この期間が長くなっている場合、銀行員は「製品の売れ行きが鈍っているのではないか?」「価値のない不良在庫を抱えているのではないか?」と、在庫の「質」を疑います。
もし意図的に在庫を増やしている場合は、その理由を明確に説明する必要があります。
③ 買入債務回転期間:支払いサイクルの適切性を示す指標
これは、「仕入れ代金を、実際に支払うまでに何か月かけているか」を示す数字です。
買入債務とは、買掛金や支払手形のことです。
計算式:買入債務回転期間 = 買入債務 ÷ (売上原価 ÷ 12ヶ月)
この期間が短すぎると、自社の資金繰りを圧迫していることを意味します。
逆に長すぎる場合は、「取引先に無理な支払い条件を強いているのでは?」と、会社の姿勢を疑われる可能性もある、バランスが重要な指標です。
【実践編】融資面談で担当者を納得させる「伝え方のコツ」
3つの数字を理解したら、次はいよいよ実践編です。
融資面談では、ただ数字を見せるだけでは不十分。その数字の裏側にある「あなたの会社の強み」を伝えることが何より重要です。
数字の「なぜ?」をストーリーで語る
決算書は、会社の過去の成績表にすぎません。
銀行員が本当に知りたいのは、その数字が生まれた背景と、未来に向けた戦略です。
例えば、棚卸資産回転期間が前年より延びていたとします。
その事実だけを伝えれば、ネガティブな印象を与えかねません。
しかし、そこでこう伝えるのです。
「ご指摘の通り、棚卸資産回転期間は延びていますが、これはA社からの大口受注に備えて、戦略的に部品在庫を厚くしているためです。こちらの受注契約書をご覧ください。」
このように、ネガティブに見える数字も、ポジティブな事業戦略の裏付けとしてストーリーで語ることで、担当者の納得感は全く違ったものになります。
「資金使途」と「返済原資」を明確に紐づける
私が銀行員時代、融資の稟議書を書く上で最も重要視していたポイントです。
貸したお金が、何に使われ(資金使途)、何から返ってくるのか(返済原資)。
銀行が見ているのは、突き詰めればこの一点です。
「運転資金が足りないので貸してください」では、担当者は困ってしまいます。
そうではなく、
「今回お借りしたい運転資金500万円は、新規受注案件Bの材料費300万円と外注費200万円に充当します。そして、この案件の売上入金が3ヶ月後に入るため、その売上金800万円の中からご返済します」
というように、「お金の入り口と出口」を具体的かつ明確に説明することが、信頼獲得の鍵となります。
資金繰り表や事業計画書を使って、視覚的に示すとさらに効果的です。
工場見学を積極的に提案し、「現場の強み」を見せる
決算書だけでは伝わらない、あなたの会社の本当の強み。
それは「現場」にあります。
整理整頓された工場、活き活きと働く従業員の皆さん、長年使い込まれた機械、そして独自の生産技術。
これらは、数字には表れない、しかし事業の継続性を支える何よりの証拠です。
「ぜひ一度、当社の工場を見ていただけませんか?」
この一言を、あなたから積極的に提案してみてください。
銀行員は、数字の裏付けとなる企業の「実態」をその目で見ることで、安心し、評価を高めたいと考えています。



私も銀行員時代、綺麗に清掃され、従業員の方々が誇りを持って働く工場を見た後は、稟議書にも自然と熱が入ったものです。
よくある質問(FAQ)
Q: 赤字決算だと運転資金の融資は受けられませんか?
A: 赤字だからといって、必ずしも融資が受けられないわけではありません。
重要なのは赤字の理由と今後の改善策です。例えば、先行投資による一時的な赤字であることを事業計画で合理的に説明できれば、将来性を見込んで融資を受けられる可能性は十分にあります。金融機関は、過去の数字だけでなく未来の返済能力を見ています。
Q: 必要な運転資金の目安はどのくらいですか?
A: 一般的には「月商の3ヶ月分」が一つの目安と言われますが、これは業種や取引条件によって大きく異なります。
より正確に把握するには「(売上債権 + 棚卸資産) – 買入債務」という計算式で「経常運転資金」を算出することをお勧めします。まずは自社の実態をこの式で計算してみましょう。
Q: 融資の相談は、どの金融機関にすれば良いですか?
A: まずは、普段から取引のあるメインバンクに相談するのが基本です。
もし取引がなければ、地域に根差した信用金庫や、中小企業支援に積極的な政府系金融機関(日本政策金融公公庫など)も有力な選択肢です。それぞれ特徴が異なるため、自社の状況に合わせて相談先を選ぶことが大切です。
Q: 融資面談ではどのような書類が必要ですか?
A: 一般的には、決算書(直近3期分)、試算表、事業計画書、資金繰り表などが必要です。
加えて、見積書や受注書など、資金使途の根拠となる資料も準備しておくと説明に説得力が増します。事前に金融機関の担当者に必要書類を確認しておくのが確実です。
Q: 返済期間はどのくらいで設定すれば良いですか?
A: 運転資金の融資は、一般的に返済期間が短期(1年以内)から中期(5年~7年程度)で設定されることが多いです。
月々の返済額が資金繰りを圧迫しないよう、無理のない計画を立てることが重要です。金融機関の担当者と相談しながら、自社のキャッシュフローに合った最適な返済期間を設定しましょう。
まとめ
今回は、製造業の経営者様が銀行融資を有利に進めるための「3つの数字」と「伝え方のコツ」について、元銀行員の視点から解説しました。
最後に、これだけは押さえてください。
重要なのは、
- ① 売上債権回転期間
- ② 棚卸資産回転期間
- ③ 買入債務回転期間
という3つの指標を正しく理解し、その数字の背景にある自社の事業戦略を、自信を持って語ることです。
銀行担当者は、単なる数字の良し悪しだけを見ているのではありません。
経営者であるあなたが、自社の財務状況をどれだけ深く把握し、未来に向けてどのような手を打っているか、その「姿勢」を見ています。
この記事を参考に、まずはご自身の会社の「3つの数字」を計算してみてください。
それが、銀行との良好な関係を築き、力強い事業成長を実現するための、確かな一歩となるはずです。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる