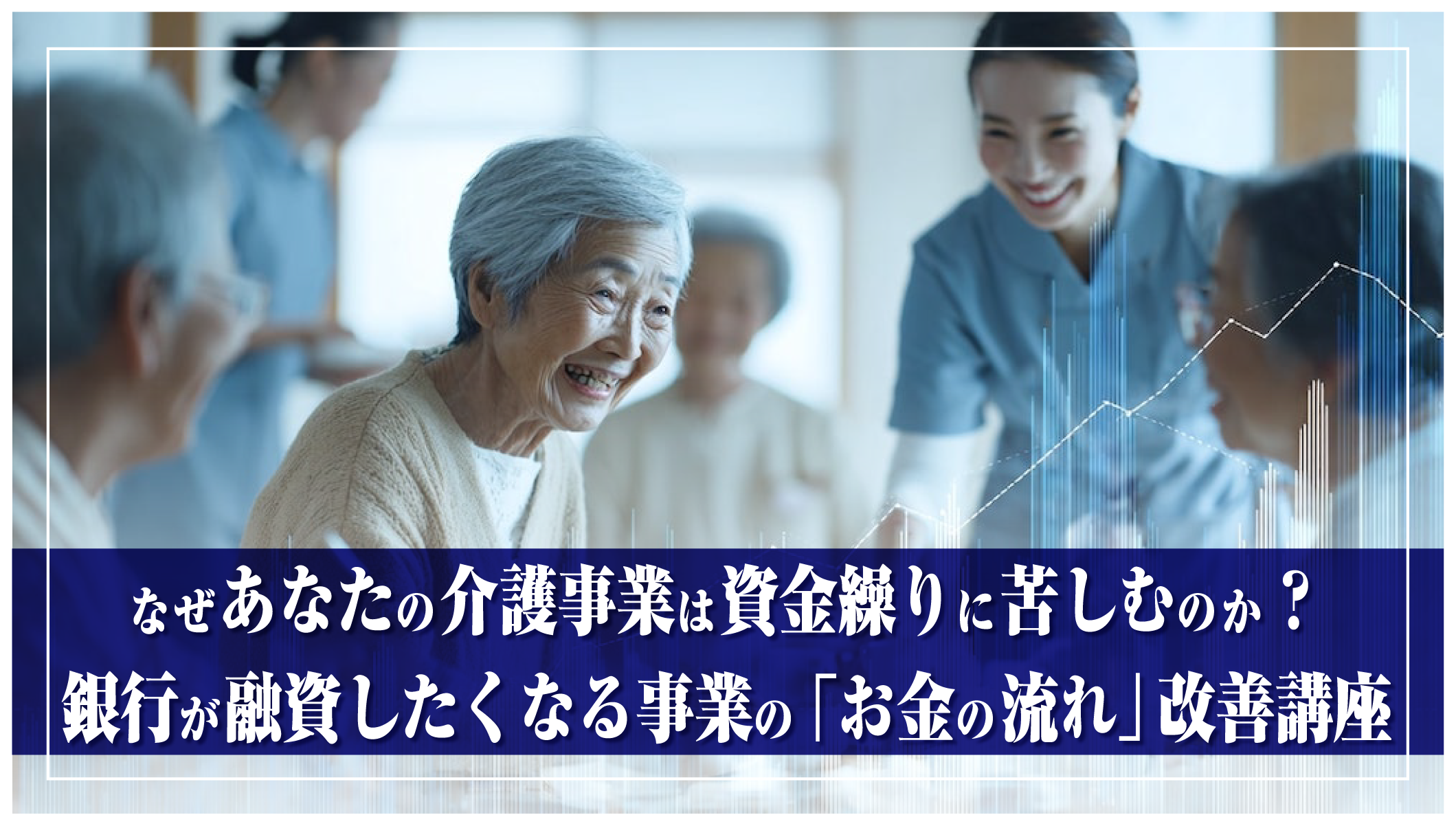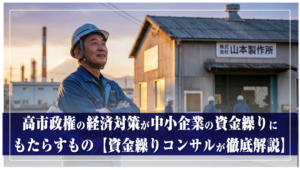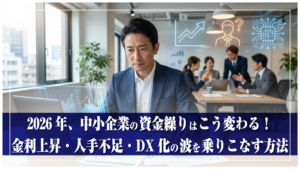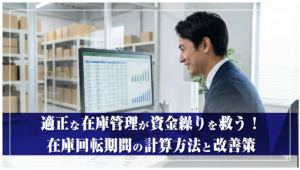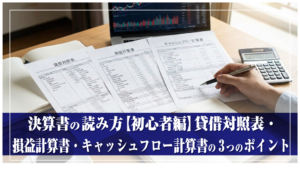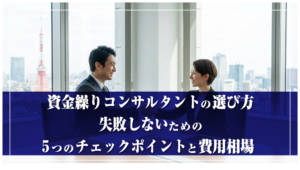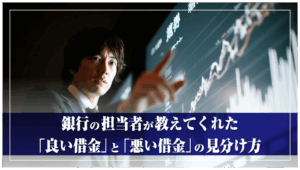「売上は伸びているのに、なぜか月末の資金繰りはいつも苦しい…」
介護事業の経営者様から、このような悲痛なご相談を毎日のように受けます。
はじめまして。元銀行員で、現在は資金繰りコンサルタントの佐々木真帆と申します。
銀行の融資担当として数多くの介護事業を見てきた経験から断言します。介護事業の資金繰りの悩みは、経営能力の問題ではなく、介護事業特有の「構造的な欠陥」が原因です。
ご安心ください。この記事では、銀行が「ぜひ融資したい」と考える事業の秘密を徹底解説します。単なる節約術ではありません。お金の流れを根本から改善し、盤石な経営基盤を築くための具体的な方法です。
【この記事の結論】介護事業の資金繰りを改善する3つの鉄則
「売上はあるのに資金が足りない…」という介護事業特有の悩みを解決し、安定した経営を実現するためのポイントは以下の3つです。
- お金の流れを「見える化」する
まずは「資金繰り表」を作成し、数ヶ月先の入出金を予測することが全ての基本です。これにより、いつ資金が不足しそうかを事前に把握し、対策を打てます。 - 入金までの期間を短縮する
約2ヶ月後に入金される介護報酬を待たずに資金化できる「介護報酬ファクタリング」を緊急時の選択肢として検討しましょう。ただし、手数料がかかるため計画的な利用が重要です。 - 返済不要の資金を活用する
国や自治体が用意している「補助金・助成金」を積極的に活用しましょう。IT導入補助金など、業務効率化とコスト削減に繋がる制度が多数あります。

💰 介護事業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ介護事業の資金繰りは悪化しやすいのか?元銀行員が語る3つの構造的要因
多くの経営者様が「自分の経営能力が低いからだ」とご自身を責めてしまいますが、決してそんなことはありません。
介護事業の資金繰りは、他の業種にはない構造的な要因によって、もともと厳しくなりやすい性質を持っているのです。
まずはその「敵」の正体を、一緒に見ていきましょう。
1. 避けられない「介護報酬の入金タイムラグ」という壁
介護事業の資金繰りを最も圧迫する要因、それは介護報酬がサービス提供から約2ヶ月後に入金されるという時間差です。
例えば、4月に提供したサービスの対価が、実際に入金されるのは6月末。
しかし、その間にもスタッフの給与や事業所の家賃、光熱費といった支払いは毎月発生します。この「収入の空白期間」を自己資金で耐えなければならないのです。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆銀行員だった頃、「この2ヶ月の運転資金を乗り越えられずに、融資相談に来られる企業がいかに多いか」を目の当たりにしてきました。
事業が順調に拡大し、利用者様が増えれば増えるほど、人件費などの支出も増えるため、このタイムラグがより重くのしかかってきます。
2. 「人」が資本だからこそ重い、固定人件費の負担
介護は「人」が全てです。
法律で定められた人員基準を満たす必要があり、人件費が経費の大部分を占める、典型的な労働集約型のビジネスモデルです。
厚生労働省の調査でも、サービス形態によっては売上の70%以上を人件費が占めるケースもあります。利用者様の数が多少変動したからといって、スタッフの数をすぐに調整することはできません。
つまり、売上が不安定でも人件費は固定費として毎月必ず出ていくため、資金繰りを硬直化させる大きな要因となっているのです。
3. 物価高騰と報酬改定のダブルパンチ
近年の光熱費や食材費、ガソリン代などの物価高騰は、介護事業の経営を直撃しています。
しかし、介護報酬は国が定める公定価格のため、仕入れコストの上昇分をサービス料金に自由に転嫁することができません。
さらに、2024年度の介護報酬改定では、特に訪問介護の基本報酬が引き下げられるなど、事業所にとっては厳しい内容も含まれました。
このように、自分たちの努力だけではコントロールしにくい外部環境の変化が、直接的に収益を圧迫し、資金繰りをさらに厳しいものにしているのです。
【銀行はココを見ている】融資審査を100%通過させる「お金の流れ」の作り方
資金繰りが厳しい時、銀行からの融資は生命線です。
しかし、ただ「お金を貸してください」とお願いするだけでは、銀行は決して首を縦に振ってくれません。
では、銀行員は一体どこを見ているのか?
私が審査担当者として、毎日何十社もの決算書や事業計画書を見てきた経験から、融資審査を通過させるための「3つの急所」をお伝えします。
1. 「どんぶり勘定」は即NG!月次の試算表と資金繰り表がすべてを語る
私が審査担当なら、融資相談に来られた経営者様に、まずこの2つの書類を要求します。
- 月次試算表:毎月の経営成績(売上、経費、利益)がわかる書類
- 資金繰り表:将来のお金の出入りを予測する書類
なぜなら、銀行が最も知りたいのは「経営者が自社の数字を正確に把握し、コントロールできているか」だからです。
決算書の数字だけでは、過去1年間の結果しか分かりません。銀行は「今、この瞬間の経営状況」と「未来の返済能力」を知りたいのです。
銀行が最も恐れるのは、経営者が自社の数字を把握していない『どんぶり勘定』です。
「売上は多分これくらいで…」「利益はまあ何とか…」という曖昧な説明では、「この人にお金を貸して、本当に大丈夫だろうか?」と不安にさせてしまいます。
逆に、タイムリーな月次試算表と、根拠のある資金繰り表を提示できれば、それだけで「この経営者は信頼できる」という強力なメッセージになるのです。
資金繰り表の作成方法については以下の記事が参考になります。
2. その設備投資は本当に必要?「投資対効果」を数字で示す事業計画
「新しい送迎車を導入したい」「最新の介護ベッドを導入したい」といった設備投資のための融資申し込みは非常に多いです。
その想いは素晴らしいのですが、銀行はシビアに「その投資が、どう収益に繋がるのか?」を見ています。
例えば、ただ「新しい送迎車が欲しい」ではなく、
「この車両を導入することで、送迎エリアを〇〇まで拡大でき、新たに月5名の利用者様を獲得できます。その結果、月間売上が〇〇円増加し、融資返済後の利益は〇〇円を見込んでいます」
というように、投資とリターンを具体的な数字で示すことが不可欠です。説得力のある事業計画は、融資審査における最強の武器になります。
3. 経営者個人の信用情報も審査対象という現実
意外と見落とされがちですが、法人の融資であっても、銀行は経営者個人の信用情報をチェックします。
なぜなら、中小企業において会社と経営者は一心同体だからです。
- 個人のクレジットカードの支払いを延滞している
- スマートフォンの本体代金の分割払いを滞納したことがある
- 過去に消費者金融からの借入があった
こうした情報は、信用情報機関(CICやJICCなど)に記録されており、審査の際にマイナス評価となる可能性があります。



私が銀行員だった頃も、会社の業績は悪くないのに、経営者個人の信用情報が原因で融資をお断りせざるを得なかったケースがありました。
会社の財務だけでなく、ご自身の信用情報にも常に気を配ることが、経営者の責任の一つと言えるでしょう。
明日からできる!介護事業のキャッシュフローを劇的に改善する5つの処方箋
構造的な問題を理解し、銀行の視点も分かりました。では、具体的に明日から何をすれば良いのでしょうか?
私がコンサルティングの現場で実際に提案し、多くの介護事業所の資金繰りを改善してきた、即効性のある5つの処方箋をご紹介します。
1. まずは現状把握から!「資金繰り表」作成のススメ
全ての改善は、お金の流れを「見える化」することから始まります。
難しく考える必要はありません。Excelなどで、今後3ヶ月〜6ヶ月先までの「入金予定」と「支払予定」を書き出すだけで良いのです。
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 収入 | |||
| 介護報酬(2月分) | 300万円 | ||
| 介護報酬(3月分) | 310万円 | ||
| 介護報酬(4月分) | 305万円 | ||
| 支出 | |||
| 人件費 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
| 家賃 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
| リース料 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 収支 | 60万円 | 70万円 | 65万円 |
| 繰越残高 | 160万円 | 230万円 | 295万円 |
これを作成することで、「いつ、いくら資金が不足しそうか」が事前に予測でき、早めに対策を打つことができます。
銀行に融資を相談する際にも、この資金繰り表があれば、なぜお金が必要なのかを明確に説明できます。
2. 介護報酬ファクタリングの賢い使い方と注意点
2ヶ月後の介護報酬を待たずに、早期に資金化できる「介護報酬ファクタリング」は、緊急時の有効な手段です。
売掛先が国保連という公的機関であるため信用度が高く、一般的なファクタリングに比べて手数料が低いのが特徴です。
ただし、便利な反面、注意点もあります。
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| ・最短数日で資金化できる | ・手数料(0.5%〜2.0%程度)がかかる |
| ・融資ではないため、借入金にならない | ・長期的に利用するとキャッシュフローを圧迫する |
| ・赤字決算や税金滞納でも利用しやすい | ・悪質な業者も存在するため、複数社比較が必須 |
あくまで、急な資金ショートを回避するための「短期的なつなぎ資金」と割り切り、計画的に利用することが重要です。
3. 意外と知らない?返済不要の「補助金・助成金」をフル活用する
国や自治体は、介護事業者を支援するための返済不要の「補助金」や「助成金」を数多く用意しています。これを使わない手はありません。
代表的なものには、以下のような制度があります。
- IT導入補助金:介護記録ソフトや勤怠管理システムの導入費用の一部を補助してくれます。業務効率化と人手不足解消に繋がります。
- 人材確保等支援助成金:介護リフトなどの福祉機器を導入したり、賃金制度を整備したりして、職員の定着率を改善した場合に助成が受けられます。
- 各自治体の補助金:都道府県や市区町村が独自に実施している補助金もあります。(例:介護ロボット導入支援事業など)
申請には手間がかかりますが、返済不要の資金は経営の安定に大きく貢献します。ぜひ一度、ご自身の事業所が使える制度がないか調べてみてください。
4. コスト削減の盲点「社会保険料」と「税金」の最適化
コスト削減というと、つい消耗品費や光熱費に目が行きがちですが、もっと大きなインパクトがあるのが「社会保険料」と「税金」です。
もちろん脱税や違法なことは論外ですが、専門家である社会保険労務士や税理士と連携することで、合法的な範囲で負担を最適化できる可能性があります。
例えば、役員報酬の決め方や、各種控除の活用など、専門家の視点で見直すことで、年間数十万円単位のキャッシュが手元に残るケースも珍しくありません。
信頼できる専門家をパートナーに持つことも、重要な経営戦略の一つです。
5. 銀行との「上手な付き合い方」を身につける
資金繰りが苦しくなってから慌てて銀行に駆け込むのは、最悪のタイミングです。
銀行に「雨の日に傘を貸してもらう」ためには、晴れているうちからのコミュニケーションが何よりも重要です。
具体的には、
- 定期的な情報提供:少なくとも3ヶ月に一度は、月次試算表を持って担当者に業績を報告しに行く。
- 早めの相談:資金がショートしそうになる1〜2ヶ月前には「少し厳しくなりそうなので相談に乗ってください」と伝える。
- ポジティブな報告も忘れずに:良いニュース(利用者様が増えた、新しい取り組みを始めたなど)も積極的に共有する。
こうした日頃からの関係構築が、いざという時の信頼に繋がり、スムーズな融資を引き出す鍵となるのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 介護報酬ファクタリングの手数料はどのくらいが相場ですか?
A: 介護報酬ファクタリングは、売掛先が国保連など公的機関であるため信用度が高く、一般的なファクタリングに比べて手数料が低い傾向にあります。相場としては0.5%~2.0%程度です。
ただし、契約内容によって異なるため、複数の会社を比較検討することが重要です。
Q: 赤字決算でも銀行から融資を受けることは可能ですか?
A: 結論から言うと、可能性はゼロではありません。一時的な赤字であっても、その原因が明確で、今後の改善策を盛り込んだ説得力のある事業計画書を提示できれば、銀行も検討の余地があります。
重要なのは、赤字の理由と今後の黒字化への具体的な道筋を、数字で示すことです。私が銀行員だった頃も、事業の将来性を評価して融資を実行したケースはありました。
Q: 創業したばかりで実績がなくても融資は受けられますか?
A: はい、可能です。特に日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」などは、創業期の事業者を支援するための制度です。
この場合、事業実績の代わりに、経営者のこれまでの経歴や自己資金の額、そして実現可能性の高い事業計画が審査の重要なポイントになります。
Q: 融資の際に、個人保証は必ず必要になりますか?
A: 必ずしも必須ではありません。近年は「経営者保証ガイドライン」の普及により、個人保証を求めない融資も増えています。 ただし、法人の財務状況や事業計画の信頼性など、一定の条件をクリアする必要があります。
保証人が不要な分、事業そのものの評価がより厳しくなると考えておきましょう。
Q: どの銀行に融資の相談に行けばよいですか?
A: まずは、事業所のメインバンクとして取引のある銀行に相談するのが基本です。日頃から取引があれば、事業内容を理解してもらいやすいでしょう。
もし取引がなければ、地元の信用金庫や地方銀行は、地域の中小企業支援に積極的な場合が多いのでおすすめです。また、前述の日本政策金融公庫も創業者や中小企業にとって心強い味方です。
まとめ
介護事業の資金繰りは、介護報酬の入金サイトや高い人件費比率といった構造的な課題を抱えており、決して経営者の能力だけの問題ではありません。
しかし、その構造を正しく理解し、銀行の視点を取り入れ、正しい対策を打つことで、お金の流れは必ず改善できます。



難しく考えすぎず、まずはこの記事でご紹介した「資金繰り表」を作成することから始めてみてください。
自社の数字と真剣に向き合うことで、これまで見えなかった課題と、次の一手が必ず見えてくるはずです。
資金繰りの安定は、会社の心臓部であるキャッシュフローを守り、質の高い介護サービスを継続的に提供するための絶対的な土台です。
この記事が、あなたの事業を盤石なものにするための一助となれば、元銀行員として、そして一人のコンサルタントとして、これほど嬉しいことはありません。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる