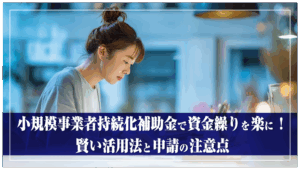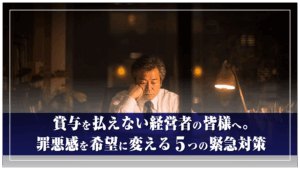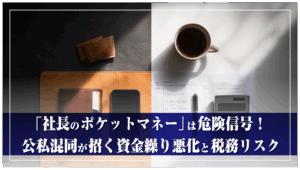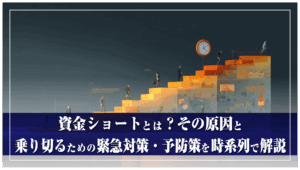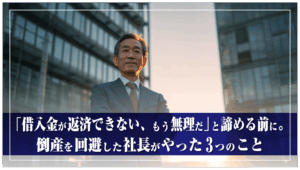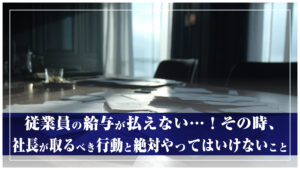「会社更生法の適用条件を知りたいが、うちのような中小企業には関係ない話だろう」
そう思っていませんか?実はそれ、大きな間違いかもしれません。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆私は元大手銀行員として1000社以上の企業融資に携わり、現在は資金繰りコンサルタントとして多くの経営者を支援してきました。その経験から断言します。
会社更生法の適用条件を正しく理解し、そこから学べる再生戦略を知ることは、規模に関わらず全ての企業の経営力強化に直結します。
本記事では、会社更生法の具体的な適用条件と民事再生法との違いを分かりやすく解説し、JALなど大企業の再生事例から中小企業が今すぐ取り入れるべき戦略を徹底分析します。
【要点解説】会社更生法の適用条件と成功の鍵
会社更生法を適用するには、法律上の要件に加え、裁判所に「再建の実現可能性」を認めてもらう必要があります。重要なポイントは以下の3つです。
- ポイント1:対象は「株式会社」のみ
会社更生手続を利用できるのは株式会社に限定されます。個人事業主や合同会社、合名会社などは対象外です。大企業や地域経済への影響が大きい企業の再建を想定した法律であることが背景にあります。 - ポイント2:申立てが可能となる2つの状態
以下のいずれかの「おそれ」がある場合に申立てが可能です。- 破産のおそれがある: 債務超過(負債が資産を上回る状態)や支払不能に陥る具体的な可能性がある状態。
- 事業継続に支障を来すおそれがある: 目前の支払いをすると、その後の事業に必要な運転資金が枯渇してしまう状態。
- ポイント3:最も重視される「事業の更生可能性」
法律上の要件を満たすだけでは不十分です。裁判所は、事業を継続する価値や再建計画の実現性を厳しく審査します。具体的には、「独自の技術力やブランド価値があるか」「信頼できるスポンサーがついているか」といった点が成功の鍵となります。 - 【補足】民事再生法との決定的な違い
混同されやすい民事再生法との最も大きな違いは「経営陣の処遇」です。会社更生法では旧経営陣は原則として退任し、裁判所が選任する管財人が経営を引き継ぎます。
本文では、これらの条件をJALの事例を交えながらさらに深掘りし、再建を成功に導くための具体的な戦略について解説します。
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
会社更生法とは?元銀行員が「民事再生法」との違いから分かりやすく解説
まずは基本から押さえましょう。
言葉は難しく聞こえますが、ポイントさえ掴めば決して難しくありません。
そもそも会社更生法とは?事業再生のための法律です
会社更生法とは、経営が非常に困難になった「株式会社」の事業を、社会的な影響も考慮しながら、裁判所の監督のもとで立て直すための法律です。
大切なのは、会社を消滅させる「破産」とは全く違う、ということです。
破産が会社の「清算」を目的とするのに対し、会社更生法は会社の「再建」を目的としています。
つまり、事業を続けながら再生を目指す、未来に向けた法律なのです。
【ポイントはここ!】会社更生法と民事再生法の決定的な違い
「民事再生法とはどう違うの?」
これは、私が経営者の方から最もよく受ける質問の一つです。
どちらも「再建型」の手続きですが、中小企業の経営者様にとって重要な違いは主に3つあります。
銀行員時代、融資先の経営状況を判断する上でも、この違いは非常に重要なポイントでした。
| 比較ポイント | 会社更生法 | 民事再生法 |
|---|---|---|
| 対象企業 | 株式会社のみ | 法人・個人事業主も対象 |
| 経営陣の処遇 | 原則、退任。管財人が経営権を握る | 原則、経営を継続できる |
| 担保権の扱い | 担保権の実行も停止できる(強力) | 担保権者は権利行使が可能 |
具体的に言うと、民事再生法は、今の経営者様が主体となって事業を続けながら、比較的スピーディーに再建を目指す場合に適しています。
そのため、多くの中小企業にとっては、民事再生法が現実的な選択肢となることが多いのです。
一方、会社更生法は、経営陣を刷新し、担保権のような強力な権利さえも一旦ストップさせて、抜本的な改革を行うための、いわば「大手術」と言えるでしょう。
なぜ会社更生法は「大企業向け」と言われるのか?
私が銀行員だった頃、会社更生法の話が融資先で出るのは、本当に稀でした。
それは、社会的な影響が非常に大きい、いわゆる大企業に限られていたからです。
その理由は主に2つあります。
手続きが非常に複雑で、時間がかかる
利害関係者が非常に多くなるため、再建計画がまとまるまでに数年単位の時間がかかることも珍しくありません。
費用が桁違いに高額
裁判所に納める「予納金」だけでも、会社の負債総額によっては数千万円、時には億単位になることもあります。これに弁護士費用などが加わるため、中小企業がこの費用を捻出するのは極めて困難です。
こうした背景から、会社更生法は「大企業向け」の制度と言われているのです。
あなたの会社は対象?会社更生法の具体的な適用条件
では、具体的にどのような状態になると、会社更生法の適用対象となるのでしょうか。
法律の条文と、元銀行員としての「現場の視点」から解説します。
法律で定められた3つの形式的要件
会社更生法第17条には、申立てができる条件が定められています。
専門用語を噛み砕いて説明しますね。
1. 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
具体的に言うと、「債務超過(負債が資産を上回る状態)」や「支払不能(支払期日の手形が落とせないなど、支払いが継続的にできない状態)」に陥りそうな、危険な状態を指します。
2. 弁済期にある債務を弁済すれば、事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
例えば、月末の支払いのために手元の運転資金を全て使ってしまうと、翌月の仕入れができなくなり、事業そのものが完全にストップしてしまう…といったケースです。資金繰りが極端に悪化している状態ですね。
3. 対象が株式会社であること
これは明確なルールで、個人事業主や合同会社、合名会社などは対象外です。
【元銀行員の視点】裁判所が本当に見ている「実質的な基準」とは
法律の要件を満たすことは大前提ですが、それだけでは会社更生は認められません。
裁判所が最も重要視するのは、「この会社は本当に立ち直れるのか?」という事業の更生可能性です。
これは、銀行の融資審査と全く同じです。
私たちが融資の際に、事業計画の実現可能性や将来性を厳しく見るのと同じで、裁判所も「絵に描いた餅」ではない、具体的な再建の道筋を求めます。
具体的には、
- 事業に将来性や価値があるか
- 支援してくれるスポンサー企業がいるか
- 提出される再建計画に具体性と実現可能性があるか
といった点が、実質的な基準として厳しく審査されるのです。



法律の条文も大切ですが、最終的に会社を救うのは「数字の裏付けがある未来への希望」です。これは法的手続きでも、銀行融資でも、経営の全ての場面で共通する真理だと私は考えています。
【ライター独自視点】JALの事例に学ぶ!中小企業が今すぐ取り入れるべき再生戦略
「やっぱり会社更生法は、うちみたいな中小企業には関係ない話だな」
そう思われたかもしれません。
しかし、ここからが本題です。
会社更生法そのものは遠い話でも、そこから這い上がった企業が実行した再生戦略には、あなたの会社の経営を劇的に改善するヒントが満載なのです。
なぜ今、大企業の再生戦略に学ぶべきなのか
資金繰りコンサルタントとして断言します。
経営危機に陥ってから対策を考えるのでは、あまりにも手遅れです。
本当に強い会社は、経営が健全なうちから、常に危機を想定した「守りの戦略」を徹底しています。
JAL(日本航空)の事例は、その最高の教科書です。
事例:JAL(日本航空)に学ぶ「徹底した採算管理と意識改革」
2010年、巨額の負債を抱えて経営破綻したJALは、会社更生法の適用を申請しました。
そこからわずか2年8ヶ月でV字回復・再上場を果たした原動力は、決して魔法ではありません。
中小企業が今すぐ真似できる、地道で本質的な改革の積み重ねでした。
関連: 株式会社企業再生支援機構による支援決定及び会社更生手続の開始決定等に関するお知らせ
事業ごとの徹底した採算管理
JALは、京セラの稲盛和夫氏が導入した「アメーバ経営」の手法を取り入れ、路線ごと、便ごとの収支を徹底的に可視化しました。
まずは自社の事業や商品をグループ分けし、どれが本当に利益を生んでいて、どれが赤字の原因なのかを明らかにすることから始めましょう。「なんとなく儲かっている」というどんぶり勘定が、一番危険です。
全従業員の意識改革
「JALフィロソフィ」という企業哲学を全社員で共有し、「自分たちの会社を自分たちの手で立て直す」という当事者意識を醸成しました。パイロットや客室乗務員もコスト意識を持ち、どうすれば利益が出るかを真剣に考えるようになったのです。
経営者一人が危機感を持っていても、会社は変わりません。毎月の試算表や資金繰り表を(簡略化したものでも良いので)社員と共有し、「会社が今どういう状況なのか」をオープンに話す場を設けることが、意識改革の第一歩です。
資金繰りコンサルタントが提言する「再生に向けた守りの一手」
JALのような大手術が必要になる前に、中小企業が打つべき「守りの一手」があります。
これは私がコンサルティングの現場で、必ず経営者様にお伝えしていることです。
キャッシュフローの可視化
難しい会計ソフトは必要ありません。まずはExcelの簡単な表で良いので、毎月の「入ってくるお金」と「出ていくお金」を正確に把握し、数ヶ月先の資金の見通しを立てる習慣をつけてください。
会社の心臓であるお金の流れを、経営者自身が誰よりも理解することが全ての基本です。
金融機関との早期相談
「銀行は雨の日に傘を取り上げる」とよく言われます。
しかし、元銀行員として断言しますが、それは手遅れになってから相談するからです。
業績が少し悪化し始めた段階で、「今こういう状況で、こう対策しようと思っている」と正直に、そして早めに相談することが、いざという時に助けてもらえる信頼関係に繋がるのです。
会社更生法を適用するメリット・デメリット
最後に、制度のメリット・デメリットを整理しておきましょう。
いざという時のための知識として、頭の片隅に入れておいてください。
メリット:事業を継続しながら再建できる
最大のメリットは、なんと言っても事業を続けられることです。
また、担保に取られている工場や機械なども、債権者が勝手に売却することができなくなるため、事業に必要な資産を守りながら再建を進められるという非常に強力なメリットがあります。
デメリット:経営権の喪失と信用の低下
経営者にとって最も厳しい現実は、原則として経営陣は退任し、経営権を裁判所が選んだ管財人に譲らなければならないことです。
また、「倒産」というイメージから社会的な信用が大きく低下し、取引先との関係維持が難しくなる可能性も覚悟しなければなりません。
よくある質問(FAQ)
Q: 会社更生法を申請すると、従業員の給料はどうなりますか?
A: ご安心ください。従業員の給料(未払賃金)は「共益債権」という扱いになり、他の借金の返済よりも優先的に支払われることが法律で定められています。 会社の再建には従業員の協力が不可欠なため、給料の支払いは最優先事項の一つとなります。
Q: 民事再生法と会社更生法、中小企業はどちらを選ぶべきですか?
A: 経営権を維持したまま再建を進めたい場合や、手続きを比較的迅速かつ低コストで進めたい場合は、民事再生法が選択されることが一般的です。 会社更生法は、非常に大規模で利害関係者が多い企業の抜本的な改革に適した制度と言えます。まずは弁護士などの専門家に相談し、自社の状況に合った方法を検討することが重要です。
Q: 申請にはどれくらいの費用がかかりますか?
A: 会社の負債総額によって大きく異なりますが、裁判所に納める予納金だけでも最低数百万〜数千万円、大企業では億単位になることもあります。 これに加えて弁護士費用も必要となるため、非常に高額な費用がかかる手続きです。
Q: 会社更生手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A: 手続きが複雑で利害関係者も多いため、更生計画が認可されるまでに数年単位の時間がかかることも珍しくありません。 民事再生が半年程度で進むことが多いのと比べると、非常に長期的な手続きとなります。
Q: 申請を検討し始めたら、誰に相談すれば良いですか?
A: 会社更生法や民事再生法などの法的手続きは非常に専門性が高いため、まずは企業再生に詳しい弁護士に相談することが第一歩です。また、同時に私のような資金繰りコンサルタントや財務アドバイザーに相談し、財務状況の正確な把握と再建計画の策定を進めることも重要です。
まとめ
今回は、会社更生法の適用条件や再生戦略について、元銀行員の視点を交えて解説しました。
この法律は主に大企業向けですが、その再生戦略には、
- 事業ごとの採算管理を徹底すること
- 全社員で危機意識を共有すること
- 早期に財務状況を改善する手を打つこと
といった、すべての中小企業が学ぶべき重要な教訓が含まれています。



最も大切なのは、会社更生法のお世話になる前に、自社の資金繰りを健全に保ち、経営危機の兆候を早期に察知することです。
銀行員時代、そしてコンサルタントとして、私は資金繰りの重要性を後回しにして苦境に陥った企業を数多く見てきました。
この記事が、あなたの会社の財務体質を強化し、持続的な成長を遂げるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
もし、あなたの会社の資金繰りに少しでも不安があれば、決して一人で抱え込まないでください。
手遅れになる前に、私たちのような専門家へお気軽にご相談いただければと思います。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる