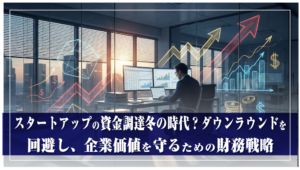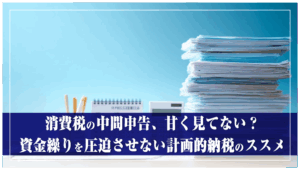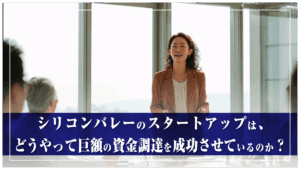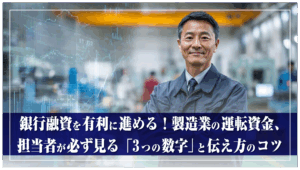2026年1月、日本の中小企業金融が根本から変わります。
改正下請法の施行により、約束手形が原則禁止となり、支払サイトは60日以内に短縮。この歴史的な変化は、ファクタリング業界に劇的な影響をもたらします。
結論から申し上げます。この法改正により、ファクタリングは「つなぎ資金」から「戦略的な資金調達手段」へと進化します。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆私は元大手銀行の融資担当として、手形による資金繰り悪化で苦しむ企業を数多く見てきました。しかし、この改正は正しく理解し対策を講じれば、貴社の資金繰りを劇的に改善する絶好のチャンスとなります。
残り1年半。準備を始めるなら今です。
この記事では、法改正がファクタリング業界に与える3つの具体的影響と、中小企業が今すぐ始めるべき対策を、元銀行員の視点から詳しく解説します。
【この記事の結論】下請法はファクタリングの利用を妨げない
- 法律違反にならない: 下請代金(売掛債権)をファクタリングで資金化することは、下請法には一切抵触せず、法律違反にはなりません。
- 債権譲渡は自由: ファクタリングは「債権譲渡」という契約の一種であり、民法上、債権を誰に売却(譲渡)するかは原則として自由です。
- 親事業者の承諾は不要: 2020年の民法改正により、契約書に「債権譲渡禁止特約」があっても原則無効となりました。そのため、親事業者の承諾なしでファクタリングを利用できます。
- 親事業者への通知は必要: 2社間ファクタリングの場合、親事業者への通知は不要ですが、3社間ファクタリングを利用する場合や、将来のトラブルを防ぐためには「債権譲渡通知」を行うのが一般的です。
本文では、これらの理由や下請法とファクタリングの関係、注意点についてさらに詳しく解説します。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
【結論】下請法改正で、ファクタリングは「より戦略的な資金調達手段」へ進化する
ポジティブな影響:手形割引に代わる「安全な」選択肢として需要が拡大
今回の法改正で、ファクタリングは単なる「つなぎ資金」ではなくなります。
これまで主流だった手形割引に代わる、より安全で確実な資金調達手段としての地位を確立するでしょう。
特に、売掛先の倒産リスクまでファクタリング会社に移転できる「ノンリコース」契約は、単にお金を得る以上の「安心」という価値を提供します。
注意すべき変化:資金繰り計画の根本的な見直しと「業者選びの目」が問われる
一方で、注意点もあります。これまで手形を前提としていた資金繰り計画は、根本から見直す必要があります。
また、ファクタリングの需要増に伴い、残念ながら悪質な業者が現れる可能性も否定できません。
だからこそ、経営者自身が「信頼できるパートナー」を見極める目を養うことが、これまで以上に重要になるのです。
【3分でわかる】2026年施行・下請法改正の核心と3つのポイント
今回の改正の心臓部とも言える、3つの重要ポイントを簡潔に解説します。
参考:(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について
ポイント1:「約束手形」の利用が原則禁止に
政府は2026年度末までに、約束手形の利用を廃止する方針を明確にしました。
なぜ、ここまで強く手形が問題視されてきたのか。



例えば、銀行員時代、私は売上は好調なのに、120日サイトの手形が原因で資金繰りに窮する企業を何社も見てきました。
売上があっても、現金が手に入るのは4ヶ月も先。その間の人件費や仕入費用の支払いができず、本当に苦しそうに相談に来られるのです。
この長年の慣行に、ようやく終止符が打たれます。
ポイント2:支払サイト(期間)が「60日以内」に短縮
下請法では、支払サイトは「受領日から60日以内」と定められています。
これまでは手形の場合、このルールが曖昧に運用される側面がありましたが、今後は現金払いが原則となり、「60日ルール」が厳格に適用されます。
これまで90日や120日が当たり前だった業界にとっては、キャッシュフローが劇的に改善する大きなチャンスです。
ポイント3:適用対象が拡大!「うちも対象?」の確認が必須に
ここが非常に重要なポイントです。
2026年1月1日に施行される改正下請法では、従来の資本金基準に加え、「従業員数」による基準が追加されました。
具体的に言うと、 これまで対象外だった「資本金1000万円超の委託元」と「資本金1000万円以下の委託先」の取引でも、委託元の従業員数が51人以上であれば、新たに対象となる可能性があるのです。
「うちは関係ない」と思わず、自社が「委託事業者」と「受託事業者」のどちらに該当する可能性があるか、必ず確認してください。
法改正がファクタリング業界に与える具体的な影響
この変化の波は、ファクタリングのあり方をどう変えるのでしょうか。
影響1:手形割引からの完全シフトと「ノンリコース」の価値向上
手形割引とファクタリングの決定的な違いは、「償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)」の有無です。
手形割引
償還請求権あり(リコース)。万が一、手形の振出人が倒産したら、あなたが銀行にお金を返さなければなりません。これは実質的に「借金」です。
ファクタリング
償還請求権なし(ノンリコース)が主流。万が一、売掛先が倒産しても、あなたがお金を返す必要はありません。リスクごと売却する「債権売買」だからです。
手形がなくなることで、この「倒産リスクを負わなくてよい」というノンリコース・ファクタリングの価値が、これまで以上に高まります。
影響2:支払サイト短縮による「ファクタリング手数料の低下」への期待
これは経営者の皆さんにとって、朗報かもしれません。
ファクタリングの手数料は、ファクタリング会社が負うリスクの大きさに比例します。



具体的に言うと、 売掛金の回収期間が長ければ長いほど、その間に売掛先が倒産するリスクは高まります。支払サイトが120日から60日に短縮されれば、ファクタリング会社のリスク期間は半分になります。
理論上、これは手数料の低下に繋がる可能性があるのです。
影響3:「でんさい」の普及とファクタリングとの使い分け
政府は手形の代替として「でんさい(電子記録債権)」の利用も推進しています。
しかし、ファクタリングとは性質が異なります。自社の状況に合わせて賢く使い分ける視点が重要です。
| 比較項目 | でんさい割引 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 法的性質 | 金銭消費貸借(融資) | 債権売買 |
| 償還請求権 | あり(未回収リスクは自社) | なし(ノンリコースの場合) |
| 審査対象 | 主に自社の信用力 | 主に売掛先の信用力 |
| 利用の前提 | 取引先もでんさい導入が必要 | 取引先の同意は原則不要 |
| 資金化速度 | 比較的早い | 最短即日も可能 |
【今日から始める】中小企業経営者が今すぐ取り組むべき3つの対策
では、この変革期を乗り切るために、今すぐ何をすべきか。具体的な3つのアクションをお伝えします。
対策1:自社の「入出金サイト」を全て洗い出す
まずはここから始めましょう。難しく考える必要はありません。Excelなどで簡単な一覧表を作るのです。
- 回収サイト → どの取引先から、何日後に売掛金が入金されるか?
- 支払サイト → どの取引先に、何日後に買掛金を支払っているか?
これを可視化するだけで、「A社からの入金が遅いのに、B社への支払いは早い。この間の資金繰りが厳しいな」といった、自社のキャッシュフローの課題が明確になります。
対策2:取引先との「支払条件」に関する事前協議
法改正は、既存の取引条件を見直す絶好の「客観的な理由」になります。これまで「長年の付き合いだから…」と言い出せなかった条件変更も、交渉しやすくなります。
例えば、 このように切り出してみてはいかがでしょうか。
「ご存知の通り、下請法の改正に伴いまして、業界全体で支払条件の見直しが進んでおります。弊社といたしましても、これを機に現在の支払サイトについてご相談させて頂きたく…」
このように、法律を盾にすることで、角を立てずに交渉を進めることが可能です。
対策3:信頼できるファクタリング会社を見極める「3つの視点」
いざファクタリングを検討する際に、どこに頼めばいいのか。悪質な業者に騙されないために、これだけは押さえてほしいポイントがあります。
手数料体系の透明性
上限・下限だけでなく、「債権譲渡登記費用」「事務手数料」などの内訳が全て明確に提示されているか。見積もり以外の追加費用がないかを確認しましょう。
契約内容の明確さ
契約書に「償還請求権なし(ノンリコース)」と明記されているか。債権譲渡登記が必須なのか、任意なのか、その費用負担はどうなるのか、細部までしっかり確認してください。
業界団体への所属や豊富な実績
金融庁の監督指針を遵守する業界団体に所属しているか、また、自社の業種での買取実績が豊富かどうかも、信頼性を測る重要な指標です。
よくある質問(FAQ)
Q: 下請法の対象外の取引でも、何か影響はありますか?
A: はい、直接的な規制対象でなくても、サプライチェーン全体で支払サイトを短縮する動きが加速するため、間接的な影響は十分に考えられます。業界全体の慣行が変わるこの機に、自社の取引条件を見直すことをお勧めします。
Q: でんさいを導入するメリット・デメリットは何ですか?
A: メリットは印紙代が不要で、紛失や盗難のリスクがなく、手続きが電子化される点です。デメリットは、取引先もでんさいを導入している必要があり、銀行の審査が比較的厳しく、万が一相手が不渡りを起こした場合の未回収リスクは自社で負う必要がある点です。
Q: ファクタリング手数料は本当に安くなるのでしょうか?
A: 支払サイトが短縮されれば、ファクタリング会社のリスクが減るため、理論上は手数料が下がる可能性があります。ただし、手数料は売掛先の信用力など、個別の審査内容にもよるため、複数の会社から見積もりを取って比較検討することが重要です。
Q: 銀行融資とファクタリング、どう使い分けるのが賢いですか?
A: 設備投資など計画的な長期資金は低金利の銀行融資、急な資金需要や売掛金の早期現金化には迅速なファクタリング、という使い分けが基本です。ファクタリングは負債にならないため、決算書上の自己資本比率を維持したい場合にも有効な手段です。
Q: 2026年1月施行なら、まだ準備は先でも大丈夫ですか?
A: いいえ、今すぐ始めるべきです。資金繰り計画の見直しや取引先との交渉には時間がかかります。施行直前に慌てないよう、早期に現状把握と対策の検討に着手することが、この変革期を乗り切る鍵となります。
まとめ
今回の下請法改正は、単なるルール変更ではなく、日本の中小企業の資金繰りを健全化するための大きな一歩です。手形の廃止や支払サイトの短縮は、一見すると複雑に感じるかもしれません。
しかし、ファクタリングという柔軟な選択肢を賢く活用することで、むしろキャッシュフローを安定させる絶好の機会に変えることができます。



この記事でお伝えした「入出金サイトの洗い出し」から、ぜひ今日から始めてみてください。
そして、自社の状況に合わせて「でんさい」と「ファクタリング」のどちらが最適か、あるいはどう組み合わせるべきかを見極めることが重要です。
変化の波を乗りこなし、貴社の事業をさらに成長させるために、本記事がその一助となれば幸いです。
資金繰りに関するお悩みは、決して一人で抱え込まないでください。いつでも私たちのような専門家にご相談くださいね。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる