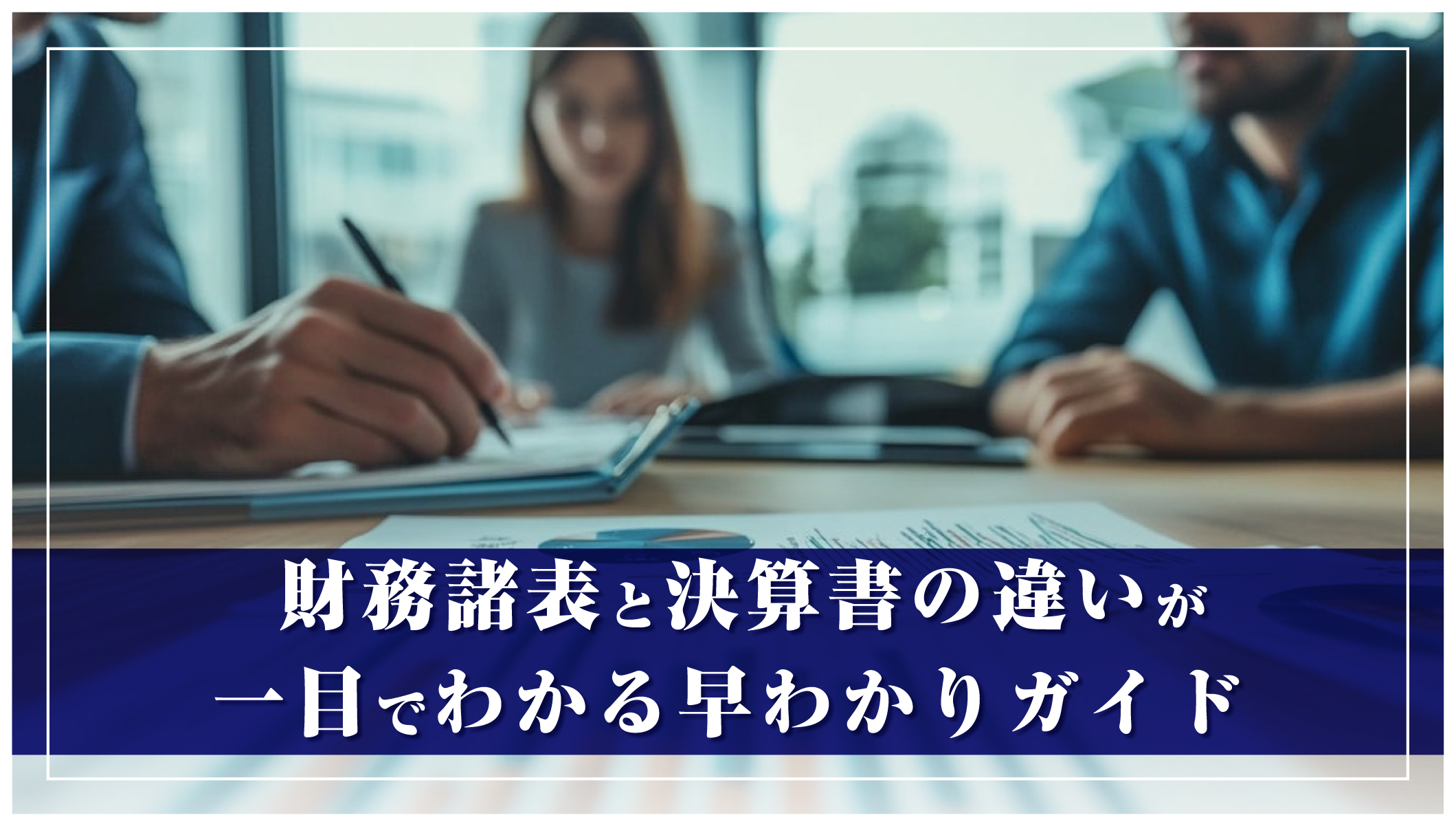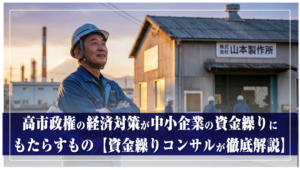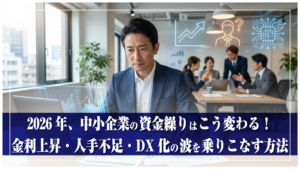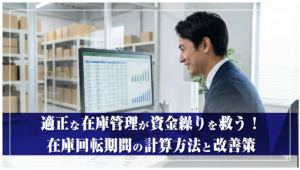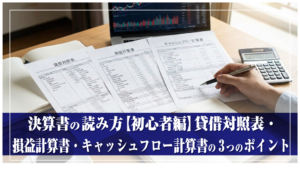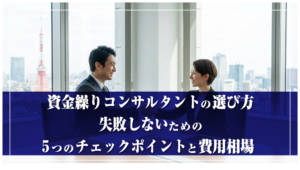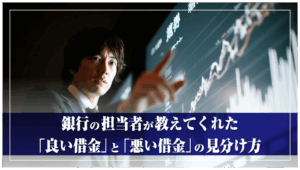「財務諸表と決算書、呼び名が違うだけで中身は同じ?」――そんなモヤモヤを抱えたまま決算資料を作成していませんか。
この記事を読めば、両者の法的ルーツ・提出先・キャッシュフロー計算書の有無までを整理し、今日から迷わず使い分けられる実務ノウハウが手に入ります。
結論から言えば、財務諸表は金融商品取引法に基づく投資家向けの開示書類、決算書は会社法や税法ベースの社内・金融機関向け資料であり、キャッシュフロー計算書の有無が最大の分岐点です。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆延べ1,000社の審査・支援実績を持つ元メガバンク融資担当の筆者が、失敗しないチェックリストと実例を交えて徹底解説します。
さあ、混同しがちな2つの書類の「違い」を理解し、説得力ある数字で経営を前進させましょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
財務諸表と決算書の基本的な違い
名称の違いと法的根拠
財務諸表と決算書の最も基本的な違いは、その法的根拠にあります。
「決算書」は通称であり正式名称ではありません。
一方、「財務諸表」は金融商品取引法に基づく正式名称、「計算書類」は会社法に基づく正式名称です。
この法的根拠の違いが、作成義務のある企業や提出先、記載内容の違いにつながっています。
実務の現場では「決算書」という用語が広く使われていますが、法律上は「財務諸表」と「計算書類」という正式名称が存在します。銀行や投資家との折衝では、正確な用語を使うことで専門性をアピールできます。
具体的に法律の違いを見てみましょう。
- 金融商品取引法: 主に上場企業に対して、投資家保護の観点から詳細な財務情報の開示を求める法律です。
- 会社法: すべての株式会社に対して、株主保護の観点から基本的な計算書類の作成を求める法律です。
このような法律の違いから、同じ企業の決算情報でも、目的によって記載内容や詳細度が異なるのです。
私が銀行で融資審査を担当していた際、上場企業と非上場企業の提出書類に違いがあることに最初は戸惑いました。
しかし、それぞれの法的要件を理解することで、適切な財務分析ができるようになったのです。
対象企業と提出先の違い
財務諸表は主に上場企業が作成し内閣総理大臣(実質的には金融庁)に提出するのに対し、計算書類は上場・非上場を問わずすべての企業が作成し株主総会等に提出します。
この違いは、情報開示の目的と範囲の違いを反映しています。
上場企業は多数の投資家に対する説明責任があるため、より詳細な情報開示が求められます。
① 法律と対象企業の関係
- 金融商品取引法:主に上場企業が対象
- 会社法:すべての株式会社が対象
- 税法:すべての法人が対象
- 中小企業の会計に関する指針:中小企業向けのガイドライン
- 中小企業の会計に関する基本要領:小規模企業向けのガイドライン提出先と期限についても把握しておくことが重要です。
具体的には以下の通りです。
| 区分 | 提出先 | 提出期限 | 主な対象企業 |
|---|---|---|---|
| 財務諸表 (金融商品取引法) | 金融庁 (EDINET) | 事業年度終了後 3ヶ月以内 | 上場企業 有価証券報告書提出会社 |
| 計算書類 (会社法) | 株主 (株主総会) | 定時株主総会開催日 2週間前まで | すべての株式会社 |
| 法人税申告書添付書類 (税法) | 税務署 | 事業年度終了後 2ヶ月以内(原則) | すべての法人 |
私がコンサルタントとして中小企業を支援していた経験から言えることですが、多くの実務担当者は提出期限の管理に苦労しています。
特に3月決算の会社は、5月末の法人税申告期限と6月の株主総会開催が重なるため、計画的な準備が欠かせません。
財務諸表と計算書類の構成要素
財務諸表に含まれる書類
金融商品取引法に基づく財務諸表には、以下の書類が含まれます。
- 貸借対照表(BS)
- 損益計算書(PL)
- キャッシュフロー計算書(CF)
- 株主資本等変動計算書
- 附属明細表
特に、キャッシュフロー計算書は財務諸表にのみ含まれる重要書類です。
🔍 ここがポイント
┗ 財務諸表は「財務三表」と呼ばれるBS・PL・CFを中心とした構成
┗ キャッシュフロー計算書は財務諸表特有の書類
┗ 連結財務諸表の作成が必要な場合も多い
┗ 四半期ごとの開示が求められる
これらの書類は、有価証券報告書の一部として開示され、投資家の投資判断材料となります。



私が銀行で融資審査を担当していた時は、特にキャッシュフロー計算書を重視していました。
利益と現金の動きは必ずしも一致せず、「黒字倒産」というリスクを見極めるためにキャッシュフロー計算書の分析は欠かせないのです。
計算書類に含まれる書類
会社法に基づく計算書類には、以下の書類が含まれます。
- 貸借対照表(BS)
- 損益計算書(PL)
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
財務諸表との大きな違いは、キャッシュフロー計算書が含まれない点です。
以下の項目を必ず確認しましょう。
- 会社法に準拠した様式になっているか
- 重要な会計方針が正しく記載されているか
- 貸借対照表の資産・負債・純資産が一致しているか
- 前期からの数値の変動に説明がつくか
- 税務処理との整合性はとれているか
中小企業では、計算書類の作成負担を軽減するための措置があります。
例えば、「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠すれば、注記事項を簡略化できる場合があります。
ただし、コンサルタントとしての経験から言えることは、簡略化しすぎると金融機関からの評価が下がる可能性があるということです。
融資を受ける予定がある企業は、任意でもキャッシュフロー計算書を作成することをお勧めします。
財務三表の重要性と読み方
貸借対照表(BS)の読み方
貸借対照表は企業の財政状態を表す重要な書類です。
資産、負債、純資産の三要素から構成され、企業の「ある時点での状態」を示します。
具体的には以下の関係式が成り立ちます。
資産 = 負債 + 純資産この等式は必ず成立する会計の基本原則です。
貸借対照表から読み取るべき主要な指標には以下のようなものがあります。
貸借対照表から読み取る重要指標
1. 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100(短期の支払能力)
2. 当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100(即時支払能力)
3. 自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100(財務の安定性)
4. 固定比率 = 固定資産 ÷ 純資産 × 100(資金の固定化度合い)
5. 負債比率 = 負債 ÷ 純資産 × 100(借入依存度)私が融資審査で特に重視していたのは、自己資本比率です。
一般的に20%以上あれば健全と言われますが、業種によって適正値は異なります。
製造業では30%以上、不動産業では10%程度でも許容されるケースもあります。
また、資産の中身も重要です。
売上債権の回収期間が長すぎないか、在庫が過剰になっていないかなど、資産の質も併せて評価することが大切です。
損益計算書(PL)の読み方
損益計算書は企業の経営成績を表す書類で、「一定期間の成果」を示します。
収益、費用、利益の関係性を理解することがポイントです。
損益計算書では、以下のような段階的な利益が示されます。
| 利益の種類 | 計算式 | 意味するもの |
|---|---|---|
| 売上総利益 (粗利) | 売上高−売上原価 | 販売活動による基本的な収益力 |
| 営業利益 | 売上総利益−販管費 | 本業での収益力 |
| 経常利益 | 営業利益+営業外収益−営業外費用 | 財務活動を含めた通常の収益力 |
| 税引前当期純利益 | 経常利益+特別利益−特別損失 | 特殊要因を含めた最終的な収益 |
| 当期純利益 | 税引前当期純利益−法人税等 | 税引後の最終的な利益 |



私がコンサルタントとして企業を分析する際には、特に「営業利益」に注目します。
営業利益は本業の収益力を表すため、企業の持続可能性を判断する上で最も重要な指標です。
経常利益が高くても営業利益が低い場合、本業外の収入に依存していることになり、ビジネスモデルの見直しが必要かもしれません。
🔍 損益計算書分析のポイント
┗ 前年比で大きく変動している項目はないか
┗ 売上高に対する各利益の比率(利益率)は適正か
┗ 販管費の内訳に無駄はないか
┗ 営業外損益が経常利益に与える影響は大きくないか
┗ 特別損益の発生原因は一時的なものか
これらのポイントを押さえることで、企業の収益構造をより深く理解することができます。
キャッシュフロー計算書(CF)の読み方
キャッシュフロー計算書は企業の現金の流れを表す書類で、営業活動、投資活動、財務活動の3つの区分で表されます。
損益計算書では見えない企業の資金繰りの実態を把握するための重要な書類です。
各キャッシュフローの区分と主な内容は以下の通りです。
❶営業活動によるキャッシュフロー
- 本業での現金の動き
- プラスであれば本業で現金を稼いでいる
- 当期純利益とキャッシュフローの乖離に注意
❷投資活動によるキャッシュフロー
- 設備投資や資産売却など
- マイナスであれば将来のための投資をしている
- 過剰投資になっていないか確認
❸財務活動によるキャッシュフロー
- 借入や返済、配当金の支払いなど
- 営業CFがマイナスで財務CFがプラスの場合は要注意
キャッシュフロー計算書を読む際の最大のポイントは、「黒字なのに現金が減っている理由」を探ることです。
私が銀行時代に遭遇した事例では、営業活動でのキャッシュフローが継続的にマイナスだった企業が、最終的に資金ショートで倒産するケースがありました。
当期純利益がプラスでも、売掛金の回収が遅れたり、在庫が過剰になったりすると、現金は減少します。
「黒字倒産」を防ぐには、キャッシュフロー計算書の分析が不可欠です。特に営業キャッシュフローがマイナスの状態が続く場合は、たとえ利益が出ていても危険信号と捉えるべきです。私の経験では、3期連続で営業キャッシュフローがマイナスの企業は、資金繰り改善策を緊急に講じる必要があります。
中小企業では、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられていないため見過ごされがちですが、経営の健全性を測る上で非常に重要な指標です。
コンサルタントとして常に経営者に勧めているのは、たとえ法的義務がなくても、自主的にキャッシュフロー計算書を作成することです。
財務諸表分析の実務活用法
5つの分析視点とその活用法
財務諸表は単に読むだけでなく、分析することで企業の強みと弱みを明らかにします。
以下の5つの視点から財務諸表を分析する方法を見ていきましょう。
1. 収益性分析
- 売上高営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100
- 売上高経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100
- ROA(総資産利益率) = 当期純利益 ÷ 総資産 × 100
- ROE(自己資本利益率) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
収益性分析では、投下した資本に対してどれだけのリターンがあるかを評価します。
特にROEは投資家にとって重要な指標で、一般的に10%以上あれば良好とされています。
2. 安全性分析
- 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
- 当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
- 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
- D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本
安全性分析では、企業の財務体質の健全性を評価します。



私が融資審査で特に注目していたのは、D/Eレシオです。
この値が1.0を超えると、借入金が自己資本を上回っていることを意味し、財務リスクが高まります。
3. 成長性分析
- 売上高成長率 = (当期売上高 ÷ 前期売上高 − 1) × 100
- 経常利益成長率 = (当期経常利益 ÷ 前期経常利益 − 1) × 100
- 総資産成長率 = (当期総資産 ÷ 前期総資産 − 1) × 100
成長性分析では、企業の拡大ペースを評価します。
ただし、急成長している企業は資金需要も旺盛なため、キャッシュフローの状況も併せて確認することが重要です。
4. 効率性分析
- 総資産回転率 = 売上高 ÷ 総資産
- 棚卸資産回転率 = 売上高 ÷ 棚卸資産
- 売上債権回転率 = 売上高 ÷ 売上債権
- 買入債務回転率 = 売上原価 ÷ 買入債務
効率性分析では、資産の活用効率を評価します。
例えば、棚卸資産回転率が低い場合、在庫が過剰である可能性があります。
5. 生産性分析
- 従業員一人当たり売上高 = 売上高 ÷ 従業員数
- 従業員一人当たり付加価値 = 付加価値 ÷ 従業員数
- 労働分配率 = 人件費 ÷ 付加価値 × 100
生産性分析では、人的資源の活用効率を評価します。
この指標は業種による差が大きいため、同業他社との比較が特に重要です。
経営判断への活用ポイント
財務諸表分析の結果を経営判断にどのように活かすべきか、実務担当者の視点から解説します。
❶投資判断への活用
- 設備投資の判断には、ROI(投資収益率)を算出
- 投資額に対する年間キャッシュフロー増加額の比率で評価
- 投資回収期間も併せて検討し、長期的な価値を判断
❷資金調達への活用
- 自己資本比率を考慮した最適な資金調達手段の選択
- 借入よりも増資が適している場合もある
- キャッシュフロー計算書から返済原資を把握
❸コスト削減への活用
- 損益計算書の費用項目を細分化し、無駄を発見
- 同業他社とのコスト構造比較で改善点を特定
- 固定費と変動費のバランスを最適化
❹事業拡大・撤退の判断
- セグメント別収益性分析で強みと弱みを把握
- 低収益事業からの撤退や高収益事業への資源集中を検討
- M&A判断の基礎資料としても活用
私がコンサルタントとして支援した中小企業では、財務分析の結果を経営会議の冒頭で共有し、全ての意思決定の基礎として活用していました。
その結果、感覚的な判断から数値に基づく合理的な判断へと移行し、3年で営業利益率が5%向上した事例があります。
実務担当者として財務諸表分析を行う際に重要なのは、単に数値を算出するだけでなく、その数値が意味することを経営者が理解できるように説明することです。
「自己資本比率が15%です」ではなく、「自己資本比率が15%なので、同業他社平均の25%より財務基盤が弱く、追加融資を受けにくい状況です」と伝えることで、具体的なアクションにつながります。
実務担当者のための財務諸表作成・活用のコツ
正確な財務諸表作成のためのチェックポイント
実務担当者として財務諸表を作成する際の重要なチェックポイントを解説します。
財務諸表作成前の準備
- 月次決算の徹底で期末作業を軽減
- 証憑書類の整理と確認
- 勘定科目体系の整備
- 前期の財務諸表と比較するための準備
- 税理士との事前打ち合わせ
財務諸表作成時のチェックポイント
| 項目 | チェック内容 | よくある誤り |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 資産=負債+純資産の等式が成立しているか | 仕訳漏れや転記ミス |
| 損益計算書 | 売上・経費の計上もれはないか | 期間帰属の誤り |
| 減価償却 | 償却方法と耐用年数は適切か | 固定資産台帳との不一致 |
| 引当金 | 必要な引当金は計上されているか | 引当金の計上漏れ |
| 税効果 | 繰延税金資産・負債の計算は正確か | 回収可能性の検討不足 |
| 注記事項 | 重要な会計方針等の開示は適切か | 注記漏れ |
また、財務諸表作成において特に注意すべきポイントとして、以下の項目があります。
① 会計基準の一貫性
- 会計方針を安易に変更しない
- 変更する場合は理由を明確にし開示する
- 過年度の財務諸表との比較可能性を確保する② データの検証
┗ 前期との著しい変動については必ず理由を確認する
┗ 元帳や補助簿との整合性を確認する
┗ 実地棚卸結果と帳簿残高の一致を確認する
┗ 固定資産台帳と貸借対照表計上額の一致を確認する
③ 開示情報の適切性
┗ 重要な会計方針の開示漏れがないか
┗ 偶発債務などのリスク情報は適切に開示されているか
┗ 関連当事者取引の開示は適切か
┗ 重要な後発事象はないか



私が銀行で融資審査を担当していた際に気付いたのは、財務諸表の数値そのものよりも、その数値に至るプロセスの透明性が信頼性を高めるということです。
例えば、利益が急減した場合でも、その原因を明確に説明できる企業には信頼感が生まれます。
会計ソフトの活用も効率的な財務諸表作成には欠かせません。
特に、クラウド会計ソフトは銀行口座やクレジットカードとの連携機能により、人為的ミスを減らすことができます。
外部専門家との効果的な連携方法
財務諸表の作成や分析において、税理士や公認会計士などの外部専門家とどのように連携すべきかを解説します。
専門家に依頼すべき業務と社内で対応すべき業務の切り分け
❶社内で対応すべき業務
- 日常的な仕訳入力と証憑整理
- 月次試算表の作成
- 預金・売掛金・買掛金の残高確認
- 棚卸資産の実地棚卸
❷専門家に依頼すべき業務
- 決算整理仕訳の指導
- 税務調整と申告書作成
- 会計基準変更への対応
- 複雑な会計処理の相談(M&A、事業再編など)
- 税務調査対応
効果的な連携のためのポイントは以下の通りです。
専門家との効果的なコミュニケーション方法
1. 定期的なミーティングを設定する(月次や四半期ごと)
2. 事前に議題や質問事項をリスト化して送付する
3. 経営上の重要な意思決定の前に相談する
4. 業界動向や税制改正の情報を積極的に求める
5. 単なる数値報告ではなく、経営課題の相談も行う専門家からより有益なアドバイスを引き出すためには、質問の仕方も重要です。
「この処理は正しいですか?」という単純な質問ではなく、「この処理が経営に与える影響はどのように考えるべきでしょうか?」と尋ねることで、より深い洞察を得られることがあります。
税理士や会計士は数字の専門家であると同時に、多くの企業を見てきた経営のプロでもあります。単なる記帳代行や税務申告だけでなく、経営判断の相談相手として活用することで、その専門性を最大限に活かせます。私の経験では、定期的に経営会議に税理士を招く企業は、財務戦略がより洗練されていく傾向がありました。
また、専門家との関係構築のコツとして、情報の透明性が挙げられます。
問題や懸念事項を隠さず共有することで、より適切なアドバイスを受けられるようになります。
私がコンサルタントとして経験した例では、クライアント企業が税理士に対して財務上の懸念点を包み隠さず相談したことで、事前に税務リスクを回避できたケースがありました。
よくある質問(FAQ)
Q: 財務諸表と決算書は実務上どのように使い分ければよいですか?
A: 実務上は、社内での報告や経営判断のための資料として「決算書」という呼称を用いることが多いですが、金融機関や投資家向けの資料としては「財務諸表」または「計算書類」という正式名称を使用するのが適切です。
例えば、銀行融資を申し込む際には「財務諸表」という正式名称を使うことで、専門性と信頼性を示すことができます。
Q: 非上場企業でもキャッシュフロー計算書を作成すべきですか?
A: 法的には非上場企業にキャッシュフロー計算書の作成義務はありませんが、資金繰りの実態を把握し、健全な経営を行うためには作成することを強くお勧めします。
利益が出ていても現金が不足するという「黒字倒産」のリスクを避けるためにも、キャッシュフロー計算書は非常に重要です。
Q: 財務諸表分析で最も重視すべき指標は何ですか?
A: 業種や企業の状況によって重視すべき指標は異なりますが、一般的には「営業利益率」「自己資本比率」「営業キャッシュフロー」の3つは最低限チェックすべき指標です。
営業利益率は本業の収益力を示し、自己資本比率は財務の安全性を示し、営業キャッシュフローは実際の資金創出力を示す重要な指標です。
Q: 経営者に財務諸表の重要性をどのように説明すべきですか?
A: 財務諸表の重要性を経営者に説明する際は、「財務諸表は単なる法的義務ではなく、経営の羅針盤である」という点を強調するとよいでしょう。
具体的なメリットや成功事例を交えて説明することで、経営者の理解を深めることができます。
まとめ
財務諸表と決算書の違いを理解することは、実務担当者として一歩先を行くための重要な知識です。
本記事では、両者の違いを法的根拠から実務上の扱いまで詳しく解説しました。
財務諸表は金融商品取引法に基づく正式名称であり、決算書は通称に過ぎません。
しかし、この違いを理解することで、企業の財務情報をより正確に把握し、適切な経営判断につなげることができます。
特に重要な「財務三表」(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の読み方を習得し、5つの分析視点から企業の健全性を評価する方法を身につけることで、実務担当者としての価値を高めることができるでしょう。
私がコンサルタントとして多くの中小企業の財務改善に携わってきた経験から言えることは、財務諸表の正確な理解が企業の存続と成長に直結するということです。
数字の背後にある企業の実態を読み取る力は、経営の質を大きく左右します。
財務諸表は単なる数字の羅列ではなく、企業の過去・現在・未来を映し出す鏡です。
この知識を活かして、より戦略的な経営判断に貢献していただければ幸いです。
最後に、財務諸表の分析は一朝一夕で身につくものではありません。
日々の実務の中で継続的に取り組み、少しずつスキルを磨いていくことが大切です。
本記事が、そのための第一歩となれば幸いです。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる