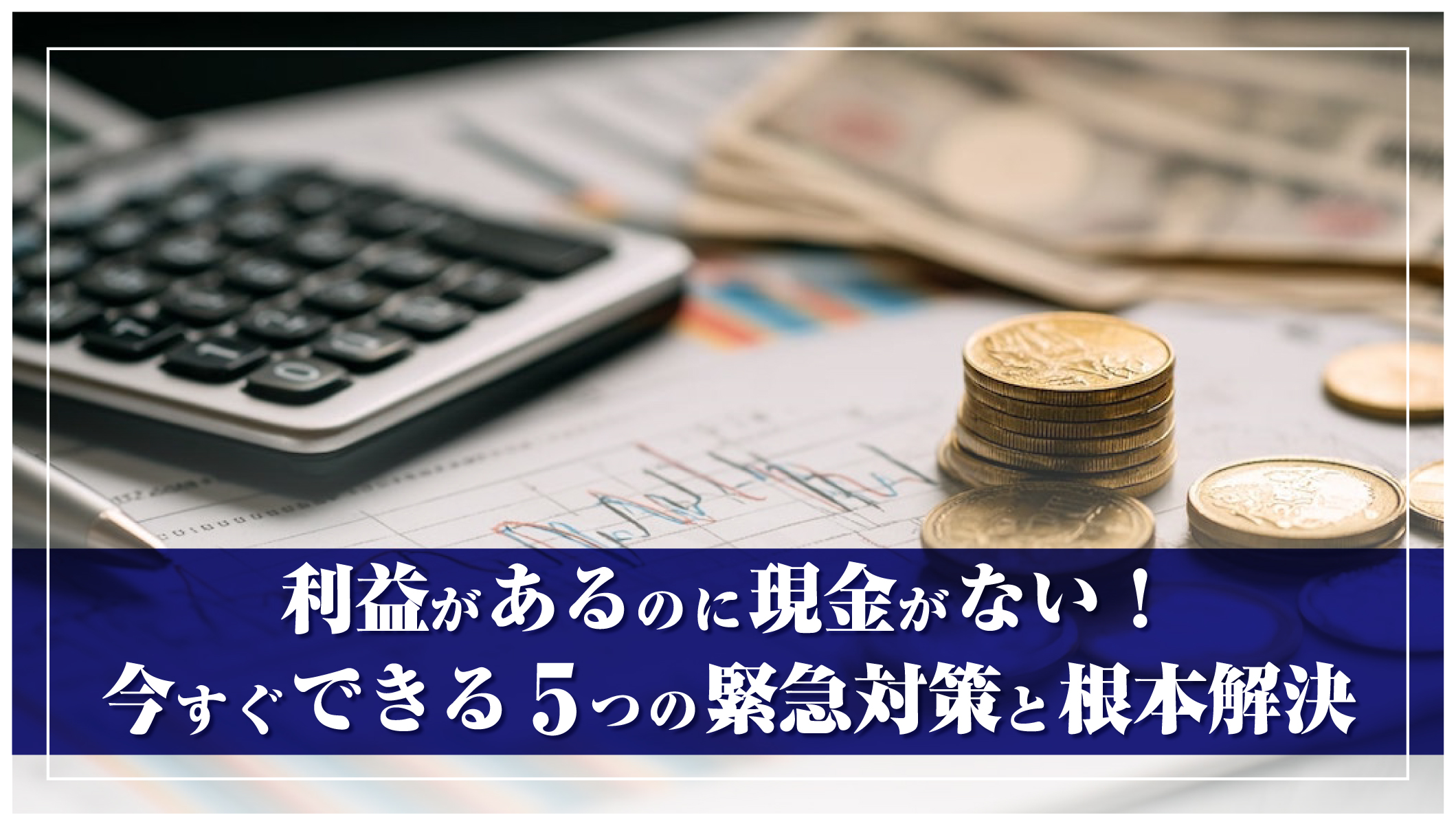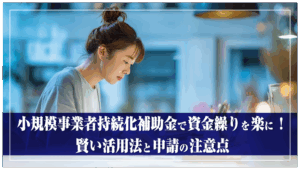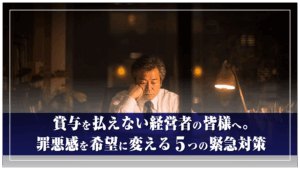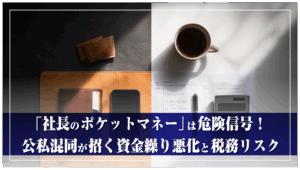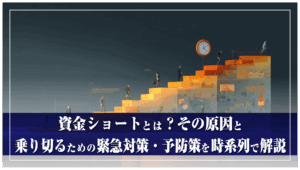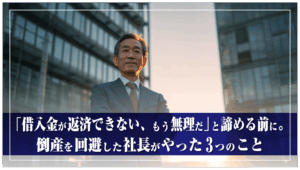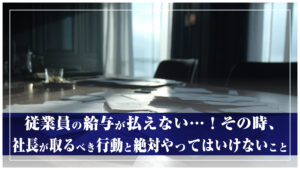「利益は出ているのに、なぜ手元にお金がないんだろう?」
もしあなたが今、こんな資金繰りの悩みを抱えているなら、この記事が必ず解決策になります。
こんにちは、資金繰りコンサルタントの佐々木真帆です。
この記事では、黒字なのに現金がない問題を解決する5つの緊急対策と根本的な解決法をお伝えします。最後まで読めば、資金ショートの不安から解放され、安定した資金繰りを実現できます。
【この記事の結論】利益があるのに現金がない時の原因と対策
会計上の利益と手元の現金にはズレがあり、この問題を放置すると「黒字倒産」のリスクがあります。主な原因と、今すぐ検討すべき対策は以下の通りです。自社の状況と照らし合わせ、すぐに行動に移しましょう。
| 主な原因 | 今すぐできる対策 |
|---|---|
| ① 売掛金の入金が遅い | ・入金サイト(支払い期間)の短縮交渉を行う ・請求書を即時現金化する「ファクタリング」を検討する |
| ② 在庫が多すぎる | ・セールや特別販売で在庫を現金化する ・発注ルールを見直し、適正在庫を維持する仕組みを作る |
| ③ 借入金の返済額が大きい | ・金融機関に返済計画の見直し(リスケジュール)を相談する ・追加融資や新たな資金調達を検討する |
| ④ 急な売上増で支出が先行 | ・資金繰り表を作成し、数ヶ月先の現金の動きを予測する ・売上増を見越して運転資金の融資を申し込む |
各対策の詳しい手順や、資金繰り改善に役立つ具体的なツールは本文で詳しく解説します。

💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ「利益があるのに現金がない」状態に陥るのか?
利益と現金のズレを生む「勘定合って銭足らず」の正体
「利益が出ているのに、お金がない」
この現象を、昔の人は「勘定合って銭足らず」と呼びました。
これは、会計上の「利益」と、実際に手元にある「現金(キャッシュ)」の計算ルールが違うために起こります。
参考: 資金繰りとキャッシュフローの違い
具体的に言うと、ズレを生む主な原因は以下の3つです。
1. 売上の計上と、入金のタイミングのズレ
例えば、商品を100万円で販売した場合、商品を納品した時点で会計上は「100万円の売上」が計上されます。
しかし、その代金が翌月末に入金される契約なら、手元に現金が入ってくるのは1ヶ月以上先です。このタイムラグが、最も大きなズレの原因です。
2. 現金の支出を伴わない費用(減価償却費など)
工場の機械や社用車などを購入した場合、その費用は数年にわたって「減価償却費」として計上されます。
これは会計上の費用ですが、実際に現金が出ていくわけではありません。
3. 費用にはならない現金の支出(借入金返済など)
銀行からの借入金を返済する場合、元本部分は経費にはなりません。
しかし、あなたの会社の口座からは、確実に現金が減っていきます。
このようにお金の「入」と「出」のタイミングが複雑に絡み合うことで、帳簿上の利益と手元の現金にギャップが生まれるのです。
【ケーススタディ】黒字倒産を招く3つの典型的なパターン
私が銀行員、そしてコンサルタントとして見てきた中で、特に多い黒字倒産の典型的なパターンを3つご紹介します。
1. 売掛金の回収遅延・貸し倒れ
あるIT企業A社は、大口の受注が決まり、売上は前年比150%と絶好調でした。
しかし、その大口取引先の業績が急激に悪化。入金が2ヶ月、3ヶ月と遅れ、最終的には倒産してしまいました。
売上は立っているのに、現金が入ってこない。A社は連鎖的に資金繰りに行き詰まり、非常に厳しい状況に追い込まれました。
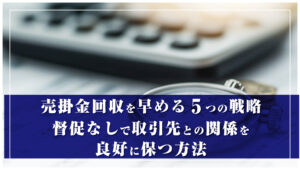
2. 過剰在庫
アパレル系のB社は、ヒット商品を予測して大量に仕入れを行いました。
しかし、トレンドの移り変わりは予想以上に早く、商品は倉庫に山積み。
仕入れ代金の支払いは迫るのに、商品は現金に変わりません。まさに「在庫=寝ているお金」となり、資金繰りを圧迫してしまったのです。
3. 急な設備投資
製造業のC社は、事業拡大を見込んで最新の機械を導入しました。
自己資金と借入でなんとか支払いを終えましたが、想定していたほど受注が伸びず、手元の現金が一気に枯渇。
借入金の返済も始まり、運転資金がショート寸前になってしまいました。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆これらのケースは、決して他人事ではありません。
事業が順調な時ほど、こうした落とし穴にはまりやすいのです。
【緊急度順】今すぐできる5つの資金繰り緊急対策
もしあなたが今、まさに資金ショートの危機に直面しているなら、まずは応急処置が必要です。
即効性のある対策を、緊急度の高い順に5つ紹介します。
1. 支払いサイトの交渉(支払いの先延ばし)
最も早く、元手がかからずにできるのが、買掛金や家賃などの支払いを待ってもらう交渉です。
「そんなことできるわけがない」と思うかもしれません。
しかし、誠心誠意、事情を説明すれば応じてくれるケースは少なくありません。
- 正直に、そして具体的に話すこと → 「大口の入金が1ヶ月遅れており、来月15日には必ずお支払いできます」など、具体的な理由と支払い計画を正直に伝えます。
- 相手のメリットも考える → 「支払いを少しお待ちいただければ、この苦しい時期を乗り越え、今後も御社と取引を継続できます」と、関係維持のメリットを伝えます。
- 約束は必ず守る → 小さな約束でも、一度破れば信頼は失墜します。必ず守れる期日を伝えましょう。
日頃からの信頼関係が何よりも大切です。
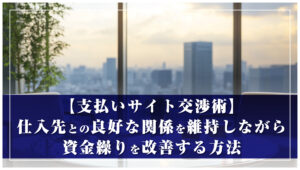
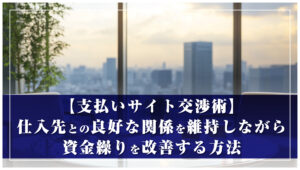
2. 未回収の売掛金を早期に現金化する(ファクタリング・手形割引)
ファクタリングとは入金待ちの請求書(売掛債権)を専門業者に買い取ってもらい、手数料を引いた額を即座に受け取る方法です。
銀行融資よりも早く現金を確保できるのが最大のメリットです。
ただし、利用には注意が必要です。
| 種類 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| ファクタリング | ・最短即日で現金化可能 ・信用情報に影響しにくい(2社間) ・売掛先が倒産しても返済義務なし | ・手数料が高い(売掛金の数%〜20%程度) ・悪徳業者が存在する ・3社間ファクタリングは売掛先に知られる |
| 手形割引 | ・ファクタリングより手数料が安い傾向 | ・手形が不渡りになると買い戻し義務がある ・そもそも手形取引が減少している |
あくまで緊急時の手段と割り切り、手数料や契約内容を十分に比較検討してください。
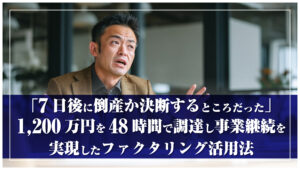
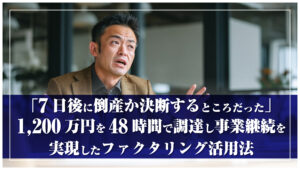
3. 短期的な資金を確保する(ビジネスローン・公的融資)
銀行からの追加融資が難しい場合でも、ノンバンク系のビジネスローンや公的な融資制度が選択肢になります。
ビジネスローン
審査が比較的早く、即日融資を謳うものもあります。しかし、金利は銀行融資に比べて高くなる傾向があるため、返済計画を慎重に立てる必要があります。
公的融資
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」など、業況が悪化した事業者を支援する制度があります。金利が低く、返済期間も長く設定できる可能性がありますが、審査には時間がかかります。
まずは公的融資の窓口に相談し、それが間に合わない場合の選択肢としてビジネスローンを検討するのが良いでしょう。
4. 不要な資産を売却する
事業に使っていない土地や建物、有価証券、ゴルフ会員権などの遊休資産を売却して現金化する方法です。
私のクライアントでも、昔購入したものの全く使っていなかったリゾートマンションを売却し、当面の運転資金を確保した社長がいらっしゃいました。
ただし、不動産などは売却に時間がかかる場合が多く、緊急対策としては間に合わない可能性もあります。
また、将来的に必要になる事業用資産まで焦って手放さないよう、冷静な判断が必要です。
5. 経営者自身が資金を投入する(役員借入金)
経営者個人の資産を会社に貸し付ける方法です。
手続きが簡単で金利もかからないため、最も手軽な方法と言えます。
【佐々木からの警告】役員借入金は最後の手段です
役員借入金は、一見すると便利な方法ですが、公私混同を招き、会社の財務体質を分かりにくくします。
銀行の融資審査では「この会社は社長個人の資金がないと回らないのか」と見なされ、マイナス評価につながることもあります。
また、社長に万が一のことがあった場合、この貸付金は相続財産となり、相続税の対象になることも忘れてはいけません。
あくまで、他の全ての手段を尽くした後の「最終手段」と位置づけてください。
問題を繰り返さないための根本解決法
緊急事態を乗り越えたら、それで終わりではありません。
二度と同じ状況に陥らないための「体質改善」こそが、最も重要です。
1. 現金の流れを「見える化」する:資金繰り表の作成と活用
全ての基本は、会社の現金の流れを「見える化」することです。
そのための最強のツールが「資金繰り表」です。
これは、未来の現金の「入」と「出」を予測し、一覧にしたものです。
難しく考える必要はありません。Excelの簡単な表で十分です。
- 資金ショートを予測できる → 「3ヶ月後に資金がマイナスになりそうだ」と事前に察知でき、先手を打てます。
- 銀行交渉に有利になる → 銀行に融資を申し込む際、具体的な返済計画を示す根拠となり、説得力が格段に増します。
- 経営判断の精度が上がる → 「いつなら設備投資できるか」「あと何人採用できるか」といった判断が、感覚ではなく数字に基づいてできるようになります。



まずは過去3ヶ月分と、未来3ヶ月分の予測から始めてみましょう。
これがあるだけで、経営の景色は一変します。
2. 売掛金の管理を徹底する:与信管理と回収ルールの見直し
売上は、現金として回収して初めて完了です。
そのために、取引先の支払い能力を事前にチェックする「与信管理」と、回収のルール化が不可欠です。
与信管理
新規取引の際は、調査会社を利用したり、業界の評判を確認したりして、相手の支払い能力を必ずチェックしましょう。
回収ルールの確立
「請求書は月末締めの翌月5日までに発行」「入金が確認できない場合は3営業日以内に電話で連絡」など、社内のルールを明確に決め、徹底します。
回収サイト(売上計上から入金までの期間)を短縮する交渉も、重要な資金繰り改善策の一つです。
3. 在庫を最適化する:適正在庫の把握と管理手法
あなたの会社の倉庫に眠っている在庫は、現金が姿を変えたものです。
「在庫=寝ているお金」という意識を常に持ってください。
先日訪れた温泉旅館の女将さんが、
「うちは食材の在庫を3日分以上持たないのが鉄則。新鮮なものをお出しできるし、無駄な仕入れもなくなるから」
と話していました。
これは全ての業種に通じる極意です。
- 定期的な棚卸し: 最低でも月に一度は在庫を数え、どの商品がどれだけあるかを正確に把握します。
- 需要予測: 過去の販売データに基づき、現実的な需要を予測し、それに基づいて仕入れ計画を立てます。
過剰在庫は、資金繰りを圧迫するだけでなく、保管コストや品質劣化のリスクも生みます。
4. 利益率を改善する:価格設定とコスト構造の見直し
そもそも、生み出す利益(キャッシュの源泉)が少なければ、少しのズレで現金は簡単に不足してしまいます。
自社のサービスや商品の価値を正しく見極め、安売りしていないか、価格設定を一度見直してみましょう。
同時に、家賃や人件費などの「固定費」、材料費や外注費などの「変動費」に無駄がないか、一つひとつ精査することも重要です。
利益率の改善は、会社の体力を根本から強くする、最も効果的な処方箋です。
よくある質問(FAQ)
Q: 資金繰りが厳しいとき、最初に誰に相談すればいいですか?
A: まずは顧問税理士に相談することをお勧めします。自社の財務状況を最もよく理解している専門家だからです。その上で、必要に応じて金融機関や私のような資金繰りコンサルタントに相談しましょう。決して一人で抱え込まないことが重要です。
Q: ファクタリングの利用は、銀行からの評価を下げませんか?
A: 2社間ファクタリングであれば取引先に知られることはなく、信用情報にも記録されないため、直接的に銀行評価が下がることはありません。ただし、手数料が高いため常用すると収益を圧迫し、結果的に財務状況が悪化して評価が下がる可能性はあります。あくまで緊急時の手段と捉えましょう。
Q: 資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違いは何ですか?
A: 簡単に言うと、資金繰り表は「未来の現金の動きを予測するための社内資料」、キャッシュフロー計算書は「過去の現金の動きを分析するための決算書類」です。日々の経営で重要なのは、未来の資金ショートを防ぐための「資金繰り表」です。
Q: 銀行に返済の相談(リスケジュール)をすると、今後の融資が受けられなくなりますか?
A: 一時的に新規融資が難しくなる可能性は高いです。しかし、黙って返済を滞納するより、事前に誠実に相談する方が、銀行との信頼関係を維持できます。経営改善計画を具体的に提示できれば、将来的な関係再構築の道も開けます。
Q: 税金や社会保険料の支払いが遅れるとどうなりますか?
A: 絶対に避けるべきです。税金や社会保険料を滞納すると、高い延滞税がかかるだけでなく、最終的には資産の差し押さえといった強制処分に至る可能性があります。他の支払いよりも優先順位を高く設定してください。
まとめ
「利益があるのに現金がない」という問題は、多くの経営者が直面する深刻な課題です。
しかし、その原因は「売上と入金のズレ」や「在庫」といった、管理可能なものがほとんどです。
本記事で紹介した緊急対策でまずは目の前の危機を乗り越え、その後、必ず「資金繰り表」を作成し、お金の流れを「見える化」する根本解決に取り組んでください。



資金繰りは会社の心臓部です。
銀行員、そしてコンサルタントとして多くの企業を見てきた私が断言します。
資金繰りを制する者が、経営を制するのです。
あの日の経営者のような、悔しい思いをする会社を一つでも減らしたい。
その一心で、私はこの仕事を続けています。
この記事が、あなたの会社のキャッシュフローを健全化し、希望を持って明日へ踏み出すための一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる