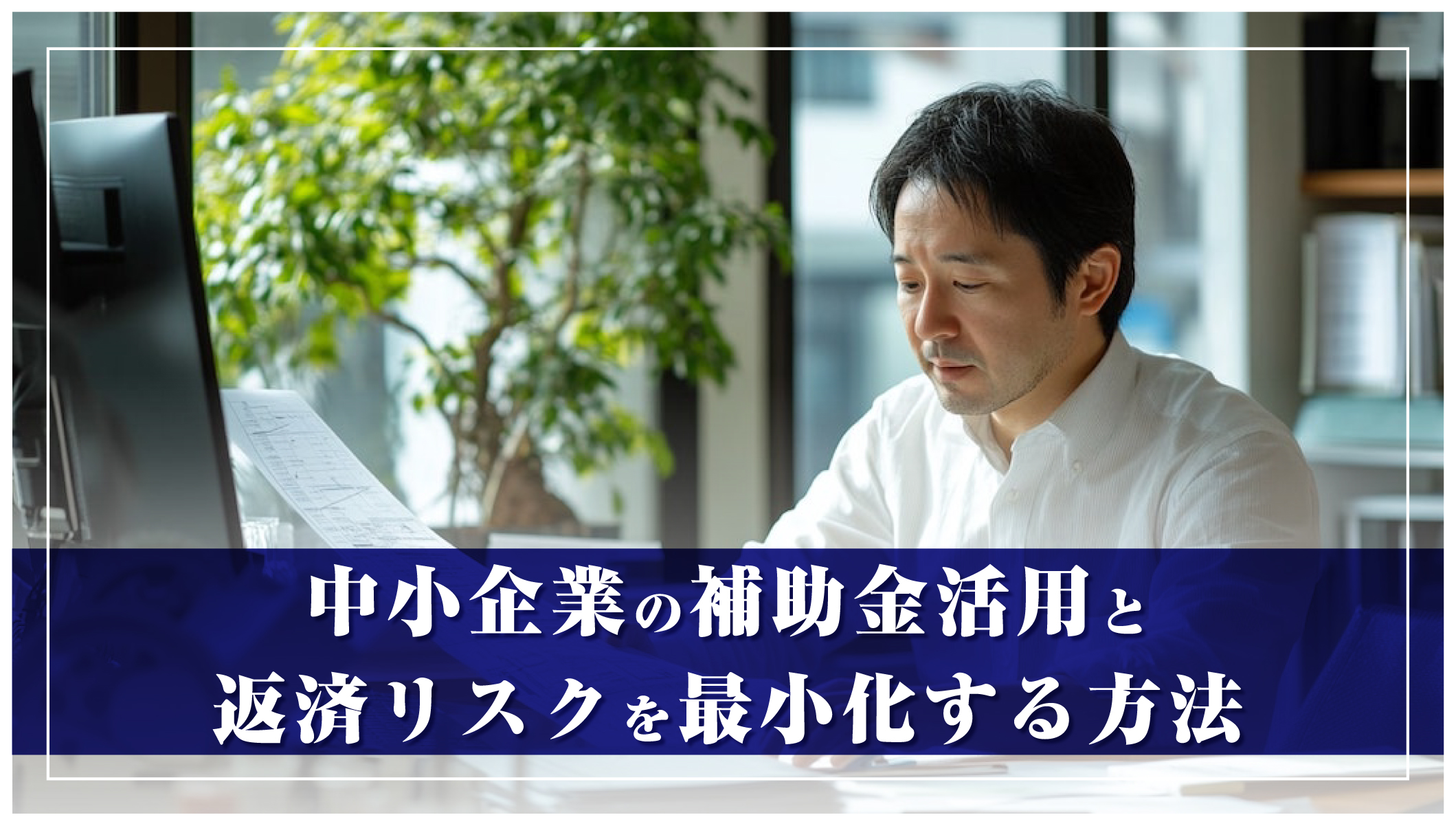「設備投資したいけど、自己資金が足りない…」
「補助金は魅力的だけど、手続きが複雑で、しかも後払いって聞いて諦めかけている」
そんな中小企業の経営者の方、実は年間数千万円の設備投資を、リスクを最小限に抑えながら実現する方法があります。
この記事を最後まで読めば、あなたも補助金と融資を戦略的に組み合わせて、自己負担を3分の1以下に抑えながら最新設備を導入できるようになります。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆さらに、補助金の「後払い問題」を完全に解決する「つなぎ融資」の活用法まで身につきます。
結論から言うと、設備投資成功の鍵は「補助金の採択率を上げつつ、資金繰りリスクをゼロにする組み合わせ戦略」です。
元銀行員として500社以上の設備投資をサポートし、総額50億円以上の資金調達を成功させてきた私が、税理士監修のもと、その全ノウハウを公開します。
さあ、一緒に「資金不足で諦める時代」に終止符を打ち、攻めの設備投資で競合に差をつけましょう。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
補助金と融資の合わせ技!設備投資を成功させる基本戦略
設備投資を成功させるために、補助金と融資をうまく組み合わせることは、資金調達の強力な武器となります。
まずはその基本的な考え方を見ていきましょう。
なぜ組み合わせる?補助金と融資それぞれのメリット・デメリット
私が銀行員時代、多くの中小企業経営者から「補助金と融資、どちらを優先すべきか」という質問を受けてきました。
結論から言えば、それぞれの長所・短所を理解し、組み合わせて使うことが最適解です。
補助金のメリット・デメリット
メリット:
- 返済不要の資金:
これが最大の魅力です。例えば1,000万円の設備投資に対して補助率2/3の補助金が採択されれば、約667万円が実質的に無償提供されます。 - 信用力の向上:
国や自治体の審査を通過したという事実は、金融機関からの評価アップにも繋がります。 - 財務リスクの軽減:
自社負担分が少なくなるため、投資リスクが大幅に減少します。
デメリット:
- 厳しい審査と競争率:
例えば「ものづくり補助金」の直近の採択率は約35%と競争が激しいです。 - 用途の制限:
使途が細かく規定され、予定外の出費に充てられません。 - 原則「後払い」:
最大の落とし穴は、事業完了後の精算払いが基本であること。つまり、一旦全額を自社で立て替える必要があるのです。 - 申請手続きの複雑さ:
書類作成や報告義務など、手続き面の負担が少なくありません。
融資のメリット・デメリット
メリット:
- 迅速な資金調達:
審査さえ通れば、補助金より圧倒的に早く資金を手にできます。 - 使途の自由度:
補助金と比べて資金使途の自由度が高いケースが多いです。 - 計画的な資金繰り:
返済計画が明確に立てられるため、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
デメリット:
- 返済義務:
当然ながら借りた資金は返さなければなりません。 - 金利負担:
低金利時代とはいえ、長期間にわたる利息負担は無視できません。 - 財務状況への影響:
借入金が増えることで、財務状況が悪化する可能性があります。



組み合わせることで、「返済不要の補助金」と「迅速な融資」という両者の長所を生かし、短所を補い合うことができるのです。
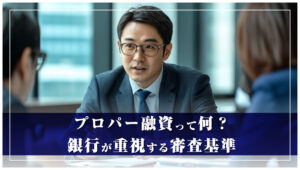
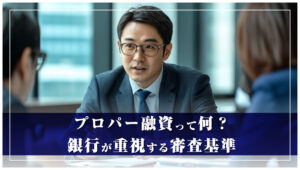
補助金は「後払い」が原則!資金繰りの鍵を握る「つなぎ融資」とは?
補助金活用の最大の落とし穴は、多くの経営者が見落としがちな「後払い」という仕組みです。
具体的には次のような流れになります。
- 補助金の採択を受ける
- 自己資金で設備投資などの事業を実施する
- 事業完了後に実績報告書を提出
- 審査を経て補助金が支給される
この流れの中で、「自己資金で立て替える」という部分が最大のネックとなります。
例えば、私のクライアントだった製造業A社の例では、3,000万円の設備投資に対して2,000万円の補助金採択を得ました。しかし自己資金は1,000万円しかなく、残りの2,000万円をどう工面するかで頭を悩ませていました。
ここで役立つのが「つなぎ融資」です。
つなぎ融資とは、補助金が支給されるまでの期間、一時的に資金を融通する短期融資のことです。補助金の交付決定通知を担保に、金融機関から借り入れを行い、補助金入金後にすぐ返済するという仕組みです。
つなぎ融資の最大のメリットは、設備投資を予定通り進められることです。
また、短期間で返済するため、金利負担も比較的少なく済みます。
一方、注意点としては、必ずしもすべての金融機関がつなぎ融資に積極的とは限らないことです。
補助金の確実性や自社の信用力によって判断されるケースが多いため、事前の相談が欠かせません。
組み合わせで実現する「攻め」と「守り」の財務戦略
補助金と融資を組み合わせることは、単なる資金調達の手段ではなく、「攻め」と「守り」のバランスが取れた財務戦略と言えます。
「守り」の側面:リスク低減効果
- 補助金により自己負担額が減少し、投資リスクが軽減される
- 自己資金の温存につながり、万一の事態に備えた資金的余裕が生まれる
- 借入額の圧縮により、返済負担が軽減される
「攻め」の側面:成長加速効果
- 補助金採択を梃子に、より大規模な設備投資が可能になる
- つなぎ融資により、タイミングを逃さない迅速な投資判断ができる
- 設備投資による生産性向上や販路拡大が早期に実現する
このように、補助金と融資は対立する概念ではなく、相互補完的な関係にあるのです。
次のセクションでは、具体的にどの補助金を選ぶべきかを見ていきましょう。
【2024-2025年最新版】設備投資に使える!主要補助金の種類と賢い選び方
補助金の種類は多岐にわたり、選択を誤ると申請準備に時間を費やしたのに採択されないというリスクもあります。
ここでは2024-2025年に有効な主要補助金と、自社に最適な補助金の選び方を解説します。
代表的な補助金リスト:ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金(後継含む)
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
概要:
- 対象: 中小企業、小規模事業者
- 補助額: 750万円~4,000万円(従業員規模や申請枠による)
- 補助率: 1/2または2/3(小規模事業者など条件によって異なる)
- 用途: 革新的な製品・サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資など
特徴:
直近の採択率は約35%と競争は激しくなっています。設備投資向けの補助金としては最もポピュラーで、製造業を中心に幅広い業種で活用されています。
活用シーン:
例えば、工作機械の更新や自動化設備の導入、生産ライン改善などに最適です。申請には、革新性・生産性向上などの要素が求められます。
小規模事業者持続化補助金
概要:
- 対象: 小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、製造業等は20人以下)
- 補助額: 50万円~250万円(枠により異なる)
- 補助率: 2/3(条件により3/4も)
- 用途: 販路開拓や生産性向上の取り組み、設備投資など
特徴:
比較的小規模な投資向けで、申請のハードルが他の補助金より低めです。ただし、直近の採択率は37%程度と年々競争は激しくなっています。
活用シーン:
小型の機械装置購入、店舗改装、システム導入など小規模な設備投資に向いています。
IT導入補助金
概要:
- 対象: 中小企業、小規模事業者
- 補助額: 150万円~450万円(類型による)
- 補助率: 1/2または2/3(2024年度からの変更あり)
- 用途: ITツール導入、ソフトウェア購入、クラウドサービス利用料など
特徴:
IT化による生産性向上を支援する補助金です。2024-2025年にかけて、セキュリティ対策枠の拡充などの変更があります。
活用シーン:
生産管理システム、顧客管理ソフト、会計システムなどのIT投資に最適です。IT事業者との連携が必要な点が特徴的です。
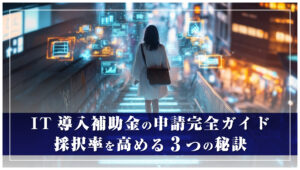
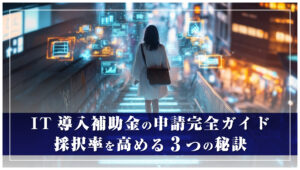
事業再構築補助金(2025年度からは新事業進出補助金)
概要:
- 対象: 中小企業、中堅企業
- 補助額: 最大1億円(企業規模や申請枠による)
- 補助率: 1/2~3/4(条件による)
- 用途: 新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換など
特徴:
大型の投資案件に対応できる補助金ですが、2025年度からは「新事業進出補助金」へ移行し、採択率は約15%と厳しくなる見込みです。
活用シーン:
新規事業立ち上げに伴う大規模設備投資、工場建設なども対象になります。他の補助金と異なり、建物建設費も補助対象になるのが大きな特徴です。
2024-2025年にかけて各補助金制度に変更が予定されています。特に事業再構築補助金の後継となる「新事業進出補助金」は競争が激化する見込みです。最新情報は各補助金の公式サイトで確認することをお勧めします。
自社に最適な補助金を見つける3つの視点(目的・規模・時期)
補助金選びで失敗しないためには、以下の3つの視点から検討することが重要です。
① 投資の目的
投資の目的によって、適した補助金は異なります。
- 生産性向上・効率化が目的:ものづくり補助金が最適
- 販路拡大・集客が主目的:持続化補助金が適している
- ITツール導入による業務改善:IT導入補助金を検討
- 事業転換・新分野進出:事業再構築補助金(新事業進出補助金)が対象
例えば、切削加工業を営むあるクライアントは、「単に同等性能の機械を入れ替えたい」という相談でしたが、これだけでは採択は難しいと判断。
そこで「無人化による生産性向上」という目的に変更し、ものづくり補助金の採択につなげました。
② 投資規模
投資金額に合った補助金を選ぶことも重要です。
- ~300万円程度:持続化補助金(小規模)
- 300万円~2,000万円:ものづくり補助金(標準的な枠)
- 2,000万円~5,000万円:ものづくり補助金(大規模枠)または事業再構築補助金
- 5,000万円以上:事業再構築補助金(新事業進出補助金)
投資規模に対して補助額の上限が小さい補助金を選ぶと、自己負担額が大きくなってしまいます。
逆に、小さな投資に対して申請要件の厳しい大型補助金を選ぶと、採択確率が下がる恐れがあります。
③ 申請タイミング
補助金には公募期間があり、タイミングを逃すと次回公募まで待つ必要があります。
- 持続化補助金:年に数回公募があり、比較的機会が多い
- ものづくり補助金:年2~3回程度の公募
- IT導入補助金:通常年1回だが長期間の公募
- 事業再構築補助金:年2~3回程度、後継の新事業進出補助金は年4回予定



投資の緊急性と補助金公募のタイミングが合わない場合は、無理に補助金を待つのではなく、融資を活用して先行投資し、次回の補助金公募に別の投資計画で応募するという選択肢も検討する価値があります。
申請準備から受給までの流れと注意点
補助金の申請から受給までは一般的に以下のような流れになります。
- 情報収集・検討:最新の公募要領を入手し、自社の適格性を確認
- 計画策定:事業計画書の作成(最も重要なステップ)
- 申請書類作成:各種書類の準備(見積書、決算書、会社概要など)
- 申請提出:期限内に電子申請等で提出
- 審査・採択発表:数週間~数ヶ月後に結果通知
- 交付申請:採択後の正式手続き
- 事業実施:計画に基づく設備導入等
- 実績報告:事業完了後に報告書提出
- 確定検査:書類審査・現地調査
- 補助金受給:審査通過後、指定口座へ入金
この流れの中で、特に注意すべきポイントをいくつか紹介します。
🎯 実践ステップ
- 事業計画書は採択の生命線:
単なる設備更新ではなく、その投資が「なぜ必要か」「どう事業成長につながるか」「具体的な数値目標」を明確に示すことが重要です。- 見積書は複数取得:
少なくとも2社以上から見積もりを取得し、適正価格であることを示しましょう。- 対象経費の確認を徹底:
補助対象外の経費を誤って計上すると、後で補助金額が減額される可能性があります。- 実施期間の遵守:
補助事業の開始・終了日は厳格に守る必要があり、期間外の発注・支払いは補助対象外となります。
私が銀行員時代、あるクライアントは補助金の交付決定前に設備を発注してしまい、全額補助対象外となる事態に陥りました。
補助金のルールは厳格ですので、不明点は必ず事務局に確認するか、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
補助金申請はハードルが高いと感じる方も多いですが、商工会議所や認定支援機関などの支援を受ければ、ハードルはグッと下がります。
特に2024年以降、多くの補助金で認定支援機関の関与が求められるようになっていますので、早めに相談することをお勧めします。
補助金の「後払い」を乗り切る!融資(つなぎ融資含む)活用術
補助金の最大の弱点である「後払い」の問題を解決するためには、融資をうまく活用することが重要です。
このセクションでは、具体的な融資の種類や申込方法、特につなぎ融資の活用術を解説します。
日本政策金融公庫と制度融資(信用保証協会)を使いこなす
中小企業が利用できる公的融資には、主に以下の2種類があります。
日本政策金融公庫(日本公庫)
特徴:
- 国が100%出資する政府系金融機関
- 民間銀行より低金利で融資を受けられる可能性が高い
- 担保や保証人に柔軟な対応が可能
- 長期返済(設備資金なら最長20年)が可能
主な融資メニュー:
- 普通貸付:一般的な事業資金
- 新創業融資制度:創業間もない企業向け
- 設備資金貸付:機械設備等の導入資金
メリット:
私が日本公庫と取引のあるクライアントに共通して感じるのは、「民間銀行では難しい案件でも前向きに検討してくれる」という点です。
例えば、ある製造業のクライアントは創業5年目で担保となる不動産を持っていませんでしたが、事業計画の実現可能性を評価され、3,000万円の設備資金を調達できました。



現在の金利目安は、中小企業向けで1.5%~2.5%程度です(金利は変動します)。
信用保証協会付き制度融資
特徴:
- 地方自治体と信用保証協会が連携した融資制度
- 信用保証協会が「公的保証人」となることで融資を受けやすくなる
- 自治体による利子補給や保証料補助がある場合も多い
- 民間金融機関(地銀・信金など)から融資を受ける
主な制度融資例:
- 小口事業資金:小規模事業者向け
- 設備投資支援資金:生産性向上のための設備投資向け
- 創業支援資金:創業間もない企業向け
メリット:
制度融資の最大の魅力は「借りやすさ」です。
例えば、ある小売業のクライアントは業績不振で民間金融機関からの融資が難しい状況でしたが、県の制度融資を利用し、店舗改装資金1,000万円の調達に成功しました。
補助金を申請する際は、同時に日本公庫や信用保証協会に相談しておくことをお勧めします。補助金採択前でも「採択されたらつなぎ融資をお願いしたい」という事前相談をしておくことで、採択後の融資手続きがスムーズになります。
「つなぎ融資」をスムーズに受けるための交渉術と必要書類
つなぎ融資を受けるには、金融機関との適切な交渉が不可欠です。
私の経験から、成功するポイントをご紹介します。
事前準備と交渉のポイント
- できるだけ早く相談する:
補助金申請前または申請直後から金融機関に相談しておくことが重要です。 - 補助金の採択通知を必ず共有する:
採択通知は融資実行の重要な根拠となります。 - 返済原資を明確に説明する:
「補助金入金後すぐに返済する」という計画を明示します。 - 資金使途を具体的に示す:
補助事業で必要となる設備や経費を明確に伝えます。 - 銀行取引の実績をアピール:
既存取引先なら今までの返済実績をアピールしましょう。
必要書類リスト
つなぎ融資申込時に一般的に求められる書類は以下の通りです。
- 補助金関連書類
- 補助金交付決定通知書(コピー)
- 補助事業計画書(申請時の書類)
- 補助金交付申請書(コピー)
- 会社基本情報
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 決算書(直近3期分)
- 試算表(直近月)
- 会社案内・パンフレット
- 事業計画関連
- 資金繰り表(補助金入金までの見通し)
- 返済計画書
- 設備の見積書・契約書など
私の経験では、特に「資金繰り表」と「返済計画書」は、銀行審査担当者が最も注目する書類です。
補助金入金までの資金繰りと、その後の返済計画を具体的な数字で示すことが、融資承認のカギとなります。



つなぎ融資は「補助金が確実に入るから審査は簡単」と思われがちですが、実際には通常の融資と同様の審査があります。補助金の不正受給リスクや、万一の事業失敗時のリスクも金融機関は考慮しています。
融資審査を有利に進める!事業計画と資金繰り表の作り込み方
融資審査を通過するためには、説得力のある事業計画と緻密な資金繰り表が欠かせません。
銀行員時代の経験をもとに、審査担当者の目線からポイントをご紹介します。
事業計画書のポイント
- 将来性と実現可能性のバランス:
野心的な目標は良いですが、あまりに非現実的な計画は疑問視されます。過去の実績を基にした堅実な成長計画が評価されます。 - 数値の根拠を明示:
「売上が20%アップする」という予測だけでなく、「なぜ20%アップするのか」の根拠(例:新設備導入で生産能力が1.3倍になり、既存の受注残に対応できるようになるため)を示します。 - リスク分析と対策:
計画通りに進まない場合のリスクとその対応策も記載すると、より信頼性が増します。
資金繰り表の作成ポイント
銀行審査では「この会社は確実に返済できるか」を最重視します。
そのため、以下の点に注意して資金繰り表を作成しましょう。
- 月次の詳細な予測:
少なくとも1年分の月次資金繰り予測を作成します。 - 保守的な数字設定:
売上は控えめに、経費は多めに見積もるという姿勢が重要です。 - 季節変動の反映:
業種によっては繁忙期・閑散期の変動を適切に反映させます。 - 返済原資の明確化:
つなぎ融資の返済原資(補助金入金)と時期を明示します。
以下は、資金繰り表の簡易例です。
| 月 | 期首残高 | 売上入金 | 仕入支払 | 経費 | 既存借入返済 | つなぎ融資実行 | つなぎ融資返済 | 補助金入金 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,000万円 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | 50万円 | – | – | – | 1,050万円 |
| 5月 | 1,050万円 | 550万円 | 350万円 | 100万円 | 50万円 | 2,000万円 | – | – | 3,100万円 |
| 6月 | 3,100万円 | 500万円 | 2,300万円 | 100万円 | 50万円 | – | – | – | 1,150万円 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10月 | 1,300万円 | 600万円 | 400万円 | 100万円 | 50万円 | – | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,350万円 |
このように、つなぎ融資の実行時期と返済時期、そして補助金入金のタイミングを明確に示すことで、金融機関に安心感を与えることができます。
銀行審査では、「この融資がなぜ必要か」「どう返済するのか」「事業の将来性はあるか」の3点が最も重視されます。
この点を意識した説得力のある資料作りを心がけましょう。
借りすぎ注意!融資の返済リスクを最小限に抑える方法
設備投資において、補助金と融資を組み合わせることは有効な戦略ですが、最終的に自己負担となる借入金の返済リスクをコントロールすることが重要です。
ここでは、返済リスクの評価と管理方法を解説します。
返済不能リスクは他人事ではない!現状データとリスク評価の基本
返済リスクの現状
私がコンサルティングを行う中で、多くの経営者が「うちは大丈夫」と思いがちな返済リスクですが、実際のデータを見ると決して他人事ではありません。
近年の調査によれば、コロナ禍での融資を受けた中小企業のうち、約18%が「返済に懸念がある」と回答しています。
特にコロナ融資の返済が本格化する2024年以降は、資金繰りの厳しさを訴える企業が増加することが予想されます。
自社の返済能力を客観的に評価する方法
返済リスクを評価する基本的な指標として、以下の3つを確認しましょう。
◎借入金月商倍率:総借入金÷月平均売上高
- 3倍以下が理想的
- 3~6倍はやや注意
- 6倍超は要警戒 例:月商500万円の企業が2,000万円の借入をする場合、借入金月商倍率は4倍
◎返済負担率:年間返済額÷年間売上高
- 5%以下なら健全
- 5~10%はやや負担大
- 10%超は危険水域 例:年商6,000万円の企業の年間返済額が600万円の場合、返済負担率は10%
◎キャッシュフロー余裕度:年間キャッシュフロー÷年間返済額
- 2倍以上あれば安全
- 1.5~2倍はやや注意
- 1.5倍未満は要注意 例:年間キャッシュフロー300万円、年間返済額150万円の場合、余裕度は2倍
中小企業基盤整備機構の調査によれば、借入金月商倍率が10倍を超える中小企業は、5年以内に資金繰り破綻に陥る確率が3倍以上高まるとされています。
これらの指標を定期的にチェックすることで、自社の返済能力の変化を客観的に評価できます。
無理のない返済計画の立て方:据置期間と返済期間の最適バランス
返済リスクを軽減するためには、設備投資の効果が出るまでの期間を考慮した返済計画が重要です。
据置期間の戦略的活用
据置期間とは、融資実行後一定期間は利息のみの支払いで、元金返済が猶予される期間のことです。
据置期間活用のメリット:
- 設備導入初期の資金負担を軽減できる
- 設備の効果が出るまでの時間的余裕ができる
- 運転資金に余裕が生まれる
例えば、ある食品製造業のクライアントは、新生産ラインの導入に3,000万円の融資を受けましたが、設備稼働から本格的な生産開始までに約6ヶ月かかる見込みでした。
そこで6ヶ月の据置期間を設定することで、生産が軌道に乗るまでの資金負担を大幅に軽減できました。
適切な据置期間の目安:
- 機械設備導入:3~6ヶ月
- 生産ライン全体の刷新:6ヶ月~1年
- 新工場建設:1~2年
返済期間の適正化
返済期間は長すぎても短すぎても問題があります。適切なバランスを考えましょう。
長すぎる返済期間のリスク:
- 総支払利息の増加
- 設備の経済的寿命より返済期間が長くなる可能性
- 次の投資機会を逃す恐れ
短すぎる返済期間のリスク:
- 月々の返済負担が重くなる
- 資金繰りが圧迫される
- 想定外の事態に弱くなる
適切な返済期間の目安:
- 機械設備:5~7年
- 大規模生産設備:7~10年
- 建物・構築物:10~20年



重要なのは、設備の経済的寿命と返済期間のバランスです。
例えば、技術革新の早いIT機器に10年返済の融資を組むと、返済途中で設備が陳腐化するリスクがあります。
私のクライアントで成功しているケースは、「設備の経済的寿命の70%程度」を返済期間の目安にしている企業が多いです。
万が一に備える!返済困難時の対処法(リスケジュール交渉など)
どんなに綿密な計画を立てても、予期せぬ事態で返済が厳しくなることもあります。
その場合の対処法を知っておくことも重要です。
早期の金融機関相談が鍵
返済が滞りそうだと感じた時、多くの経営者が犯す最大の過ちは「問題を先送りにする」ことです。
私が銀行員だった頃の経験からも、「返済が厳しくなりそうだ」と3ヶ月前に相談に来た企業と、支払期日の直前になって慌てて相談に来た企業では、対応の幅が大きく異なりました。
早期相談のメリット:
- 金融機関との信頼関係を維持できる
- より柔軟な対応策を検討してもらえる
- 信用情報に傷がつくリスクを回避できる
具体的な対処法
◎返済条件変更(リスケジュール)交渉
- 返済期間の延長
- 一時的な元金据置(利息のみ支払い)
- 月々の返済額減額
◎セーフティネット融資の活用
- セーフティネット保証(信用保証協会)
- 経営安定貸付(日本政策金融公庫)
- 借換保証制度の利用
◎経営改善計画の策定と実行
- 収益改善策の検討
- コスト削減施策の実施
- 事業再構築の検討
ある製造業のクライアントは、大口取引先の倒産により一時的に資金繰りが悪化。しかし、問題発生直後に金融機関に相談し、6ヶ月間の元金据置と、その後の返済期間延長を認めてもらいました。その間に新規取引先を開拓し、半年後には通常返済に戻ることができました。早期相談の重要性を示す好例です。
返済困難な状況は誰にでも起こり得ます。重要なのは「問題を隠さない」「早めに相談する」という姿勢です。
多くの金融機関は、企業の再生・成長を望んでおり、誠実に相談すれば必ず道は開けます。
【実践ステップ】補助金×融資で設備投資をスムーズに進める5つの手順
補助金と融資を組み合わせた設備投資を成功させるために、具体的な5つのステップを解説します。
クライアント企業の成功事例をもとに、実践的なガイドラインをお伝えします。
Step1:投資計画と資金ニーズの明確化
設備投資を検討する際、まず明確にすべきなのは「何のために」「何を」「いくらで」投資するかです。
投資の目的を明確化する
- 生産性向上なのか
- 新製品開発のためか
- 人手不足対応なのか
- 競争力強化なのか
期待する効果を数値化する
- 生産能力○○%向上
- 人件費○○万円削減
- 売上○○%増加
- 利益率○○%改善
必要資金を詳細に洗い出す
- 設備本体費:○○○万円
- 設置・工事費:○○万円
- 運搬費:○○万円
- 研修費:○○万円
- その他諸経費:○○万円
例えば、私のクライアントである金属加工業A社は、設備投資計画の初期段階で以下のような整理をしました。
- 目的:高精度加工への対応と生産性向上
- 導入設備:5軸マシニングセンタ
- 投資額:本体3,500万円、設置工事200万円、研修費100万円、計3,800万円
- 期待効果:高精度部品の受注増(年間1,200万円)、加工時間短縮による生産性30%向上(年間コスト削減800万円)
このように具体的な数字で整理することで、投資の妥当性を客観的に評価できますし、後の補助金申請や融資相談の際にも説得力が増します。
Step2:補助金リサーチと融資の事前相談
投資計画が固まったら、次は資金調達の検討です。
補助金情報の収集と融資の事前相談を並行して進めましょう。
補助金情報の収集
- 経済産業省や中小企業庁のウェブサイトチェック
- 最新の公募要領ダウンロード
- 商工会議所や金融機関での情報収集
- 過去の採択事例調査
補助金の比較検討
- 自社の投資内容と各補助金の親和性
- 補助率・補助額の比較
- 申請難易度の把握
- 申請タイミングのチェック
融資の事前相談
- メインバンクへの投資計画説明
- 日本政策金融公庫への相談
- つなぎ融資の可能性確認
- 概算での返済シミュレーション依頼
この段階では、まだ具体的な融資申込みや補助金申請はせず、情報収集と関係構築を主な目的とします。
複数の金融機関に相談することで、より良い条件を引き出せる可能性もあります。
- 補助金は公募開始後、募集期間が短いケースも多いため、常に最新情報をチェック
- 融資相談は補助金申請の前から始めておくと、採択後の手続きがスムーズに
- 補助金と融資の両方を視野に入れた資金計画を金融機関に示すと好印象
Step3:補助金申請と融資(つなぎ含む)の同時並行準備
補助金を申請しながら、融資準備も同時に進めるのがこのステップです。
ここが最も重要な局面と言えます。
補助金申請書類作成
- 事業計画書の準備(最重要)
- 必要書類の収集(見積書、登記簿謄本、決算書など)
- 認定支援機関への相談(必要な場合)
- 電子申請の準備
融資申込の準備
- 事業計画書のブラッシュアップ(補助金用と融資用で微調整)
- 資金繰り表の作成
- 返済計画書の作成
- 必要書類の準備
つなぎ融資の手配
- 金融機関との具体的な交渉
- 補助金採択を条件とした融資の事前審査依頼
- 必要な保証や担保の確認



例えば、私のクライアントであるB社では、ものづくり補助金の申請と並行して、日本政策金融公庫と地元信用金庫の両方にアプローチしました。
最終的に日本公庫から設備資金(長期)とつなぎ資金(短期)の両方の融資内諾を得ることができ、補助金採択後スムーズに資金調達を進めることができました。
補助金申請書と融資用事業計画書は、基本的な内容は同じでも微妙に異なる点があります。
例えば、補助金申請では「革新性」や「独自性」をアピールする一方、融資申請では「堅実な返済計画」や「リスク対策」をより詳細に示すといった調整が必要です。
Step4:採択後の実行フェーズ(契約・発注・支払い・資金繰り管理)
補助金採択の通知を受けたら、いよいよ実行段階です。
この段階では綿密なスケジュール管理が重要になります。
補助金関連手続き
- 交付申請書の提出
- 交付決定の受領
- 事業開始届の提出(必要な場合)
融資実行手続き
- つなぎ融資の正式申込と契約
- 長期融資(残額分)の手続き
- 融資実行日の確認
設備発注と支払い
- 発注書・契約書の作成(補助金ルールに準拠)
- 納品・検収の実施
- 支払い(融資金からの支出)
資金繰り管理の徹底
- 日次の資金繰り確認
- 予定外の支出への対応
- 補助金事務局とのやり取り
この段階で最も注意すべきなのは、補助金のルール遵守です。
例えば、交付決定前の発注、補助対象外経費の混同、支払い証拠の不備などがあると、補助金が減額されるリスクがあります。
補助金関連の支払いは、原則として銀行振込で行い、支払い証拠(振込依頼書、通帳の写し、請求書など)をすべて保管しておきましょう。現金払いや相殺は原則認められません。
また、つなぎ融資から設備代金を支払った後は、補助金入金までの期間、資金繰りに余裕を持たせることが重要です。予期せぬトラブルで補助金支給が遅れるケースもあるからです。
Step5:補助金受領と借入金の計画的返済
最終段階は、補助金受領とその後の借入金返済です。
ここまで来れば大部分の山は越えていますが、まだ気を抜かないことが大切です。
補助金実績報告の準備
- 実績報告書の作成
- 支払い証拠書類の整備
- 導入設備の稼働状況記録
- 事業成果の整理
補助金受領と借入金返済
- 補助金確定通知の受領
- 補助金の入金確認
- つなぎ融資の一括返済
- 残りの長期借入金の返済開始
投資効果のモニタリング
- 当初計画との効果比較
- 必要に応じた運用改善
- 金融機関への経過報告
- 次の投資計画への反映
補助金入金後は、計画通りつなぎ融資を一括返済することが最優先です。
そして、残りの長期借入金について返済計画通りに返済を続けます。
投資効果のモニタリングも重要です。
定期的に「投資は期待通りの効果を生んでいるか」を確認し、金融機関にも報告することで信頼関係が強化されます。
そして、この経験を次の投資計画に活かすことで、企業としての投資判断力が向上していきます。
失敗談から学ぶ!補助金・融資活用の落とし穴と回避策
成功事例だけでなく、失敗事例からも多くのことを学べます。
私がコンサルティングを通じて見てきた典型的な失敗例とその対策を紹介します。
事例1:「補助金頼み」で資金ショート!計画段階での甘さが命取りに
失敗事例
印刷業を営むD社は、デジタル印刷機の導入に際して事業再構築補助金への申請を計画していました。
投資総額5,000万円に対し、補助金で3,000万円、残り2,000万円は自己資金で賄う予定でした。
しかし、実際に申請準備を進める中で、自社には十分な自己資金がないことが判明。
「補助金が採択されれば何とかなる」という楽観的な見通しのまま申請し、見事採択されたものの、設備発注時点での資金調達に行き詰まりました。
急遽、銀行に融資を相談しましたが、突然の相談に対して銀行側も慎重になり、結局融資実行までに時間がかかり、補助事業の実施期限に間に合わず、補助金を辞退せざるを得なくなりました。
失敗の原因
- 資金計画の甘さ:「補助金が採択されれば大丈夫」という楽観的な見通し
- 自己資金の過大評価:実際の手元資金を正確に把握していなかった
- 銀行との関係構築不足:事前相談なしに突発的な融資依頼
回避策
- 資金計画の事前策定:補助金申請前に、全体の資金計画(自己資金・融資・つなぎ融資)を明確にする
- 複数のシナリオ検討:「補助金採択」「補助金不採択」両方のケースを想定した計画を立てる
- 金融機関との早期相談:補助金申請と並行して融資の事前相談を行う
あなたの会社で大型の設備投資を検討する場合、「補助金が採択されなかった場合」と「採択されたが一時的な資金が足りない場合」の両方について、どんな対策を立てられますか?
事例2:ルール違反で補助金減額!?対象経費と時期の見落とし
失敗事例
金属部品製造業のE社は、ものづくり補助金を活用したCNC工作機械導入を計画していました。
補助金申請は無事採択され、交付決定も受けました。
しかし、補助事業を進める中で複数のミスが発生しました。
まず、交付決定前に一部の付属機器を発注してしまい、その分が補助対象外に。
次に、支払いの一部を手形で行ったため、さらに対象外に。
最後に、機械本体とは別に導入した検査機器が「補助事業計画書に具体的記載がない」という理由で対象外となりました。
結果として、当初予定していた2,000万円の補助金が1,200万円に減額されてしまいました。
失敗の原因
- ルールの理解不足:補助金の細かなルール(発注時期、支払方法など)を十分理解していなかった
- 計画書の曖昧さ:補助事業の範囲を計画書に明確に記載していなかった
- 進捗管理の甘さ:誰が責任を持って補助事業を管理するか不明確だった
回避策
- 公募要領の徹底理解:公募要領や交付規程を詳細に読み込み、不明点は必ず事務局に確認する
- 計画書の具体的作成:補助対象となる設備や経費を計画書に具体的かつ詳細に記載する
- 責任者の明確化:社内で「補助金管理責任者」を決め、ルール遵守を徹底する
- 専門家の活用:認定支援機関や補助金申請のプロに相談・支援を依頼する
「採択されたら後は自由に使える」と思っている経営者は多いですが、実際には補助事業の実施方法や経費の支払い方法まで細かなルールがあります。特に「発注時期」「対象経費」「支払方法」の3点は最もトラブルが多い項目です。
事例3:返済計画が破綻…投資効果の過信と無理な借入れ
失敗事例
食品製造業のF社は、生産性向上のため、新たな生産ラインを導入しました。
投資総額8,000万円のうち、ものづくり補助金で3,000万円を賄い、残り5,000万円を銀行融資で調達。返済期間は5年としました。
当初の計画では、新ラインの導入により生産能力が2倍になり、月商が500万円から800万円に増加、年間利益も1,200万円増える見込みでした。
これなら年間1,000万円の返済も十分可能と判断しました。
しかし実際には、新ラインの本格稼働まで想定より時間がかかり、また新規顧客の開拓も計画通りに進まず、結局月商は600万円程度にしか増加しませんでした。
その結果、2年目から返済が厳しくなり、資金繰りに窮するようになってしまいました。
失敗の原因
- 投資効果の過大評価:新設備による売上増加や利益改善を楽観的に見積もり
- 返済期間の短さ:効果が十分に出る前に重い返済負担が始まった
- リスク想定の甘さ:「計画通りいかない場合」の対策を考えていなかった
回避策
- 保守的な収益予測:投資効果は控えめに見積もり、余裕を持った計画を立てる
- 適切な返済期間の設定:設備の効果が十分に出るまでは据置期間を設けるなど柔軟な返済計画を交渉
- 定期的な計画見直し:四半期ごとに計画と実績を比較し、必要に応じて早めに対策を講じる
- 金融機関との定期的な情報共有:良い状況も悪い状況も隠さず共有し、信頼関係を構築



私は銀行員時代、返済が厳しくなった企業を数多く見てきましたが、最も大きな違いは「早期に相談してきた企業」と「問題を隠して後手に回った企業」です。
前者は柔軟な対応ができることが多く、後者は選択肢が狭まってしまいます。
投資計画が多少狂っても、早めの対応と誠実さがあれば、必ず道は開けます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 補助金と融資は、本当に併用できるのですか?
A: はい、可能です。多くの補助金では自己負担分を融資で賄うことを想定しています。ただし、補助金の種類や金融機関によっては条件がある場合もあるため、事前に確認が必要です。この記事で解説した「つなぎ融資」も併用の一形態です。
最近では、補助金を活用した設備投資に対して、金融機関も積極的な姿勢を示しています。補助金採択は、事業の将来性や計画の信頼性を第三者が認めたことになるため、融資審査においてもプラス評価されることが多いです。
Q2: 「つなぎ融資」はどこで相談すれば良いですか?金利は高いですか?
A: 主な相談先は取引のある銀行や信用金庫、日本政策金融公庫です。自治体によっては専用のつなぎ融資制度がある場合もあります。例えば東京都では「補助金・助成金つなぎ融資制度」があり、優遇条件で借入れることができます。
金利は通常の事業資金融資と同程度か、やや高めの場合もありますが、借入期間が短いため総支払利息は抑えられます。現在の相場では年1.5%~3.0%程度が一般的です。複数の金融機関に相談してみることをお勧めします。
つなぎ融資の申込みには、補助金の交付決定通知書や事業計画書など、補助金採択を証明する書類が必要になります。事前に準備しておくとスムーズです。
Q3: 補助金が不採択になった場合、融資はどうなりますか?
A: 補助金採択を前提に融資を申し込んでいた場合、不採択となれば融資実行も難しくなる可能性があります。そのため、申請前に「不採択の場合、計画をどうするか(中止するのか、自己資金+融資だけで実行するのか)」を金融機関と相談しておくことが重要です。
私のクライアントでは、「補助金不採択の場合は、投資規模を縮小して実施する」という代替案を事前に金融機関と共有し、不採択になっても縮小版の計画で融資を実行してもらえたケースもあります。
不採択になった場合でも、すぐに諦めるのではなく、次回の公募に向けて計画をブラッシュアップするという選択肢も検討する価値があります。
Q4: 設備投資後に思ったような効果が出ず、返済が苦しくなったらどうすれば?
A: まずは正直に、できるだけ早く融資を受けている金融機関に相談することが最も重要です。返済計画の見直し(リスケジュール)や、追加融資、他の支援制度の活用など、状況に応じた解決策を一緒に検討してもらえます。決して一人で抱え込まず、専門家や支援機関に助けを求めましょう。
銀行員時代の経験から言えば、返済が厳しくなった企業への対応で最も重視されるのは「誠実さ」と「現実的な改善策」です。問題を隠したり先送りにしたりするのではなく、現状を正直に伝え、実現可能な改善策を一緒に考える姿勢が大切です。
また、中小企業再生支援協議会やよろず支援拠点など、公的な支援機関の専門家に相談するのも有効な方法です。
まとめ
設備投資は中小企業の成長に不可欠ですが、資金調達には不安が伴います。
しかし、この記事で解説したように、補助金と融資を戦略的に組み合わせ、特につなぎ融資を活用し、返済リスクをしっかり管理すれば、そのハードルは決して高くありません。
重要なのは、
①事前の綿密な計画(事業計画・資金計画)
②補助金・融資制度の正しい理解と活用
③金融機関との良好な関係構築
④万が一のリスクへの備え
です。
今日からできることとして、まずは自社の投資計画を具体化し、利用できそうな補助金情報を集め、信頼できる相談先(金融機関や商工会議所、専門家)にアポイントを取ることから始めてみませんか?
この記事が、あなたの会社の未来を切り拓く設備投資への第一歩を、力強く後押しできれば幸いです。
資金繰りの悩みは、正しい知識と行動で必ず乗り越えられます。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる