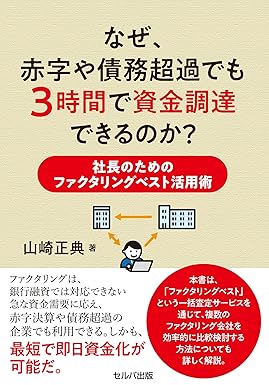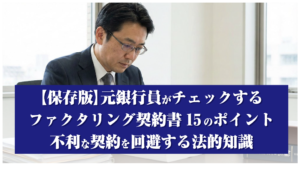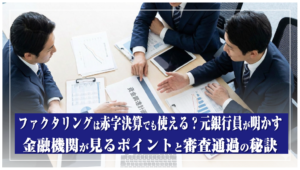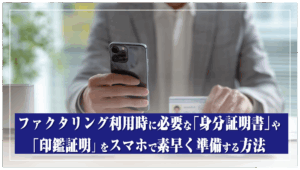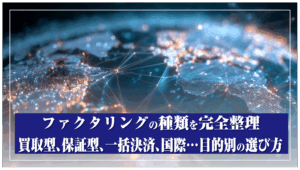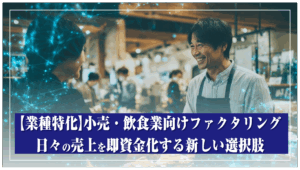「資金繰りの〆切が迫るのに、銀行の融資は断られた…。このままでは本当にマズい…」
そんな、誰にも相談できない焦りを抱える経営者の方へ。今、あなたの目の前には「ファクタリング」と「手形割引」という2つの選択肢があるはずです。
しかし、この2つを安易に選んではいけません。両者の“決定的な違い”を知らないまま契約すると、一時的に資金を手にできても、かえって経営を悪化させる危険な罠に繋がりかねないからです。
 山崎正典
山崎正典ご安心ください。この記事では、元銀行員として数百社の決算書を見てきた私が、あなたの会社にとって本当に最適な資金調達法を見抜くための「3つの判断基準」を徹底解説します。
【この記事の結論】ファクタリングと手形割引の決定的な違い
- 契約の性質
- ファクタリング:売掛債権の「売買契約」であり、負債にならない。
- 手形割引:手形を担保にした「融資(借入)」であり、負債として扱われる。
- 審査の対象
- ファクタリング:主に「売掛先の信用力」が審査される。
- 手形割引:「自社の信用力」も厳しく審査される。
- 回収不能リスク
- ファクタリング:貸倒れリスクをファクタリング会社に移転できる(償還請求権なし)。
- 手形割引:手形が不渡りになった場合、自社で買い戻す義務がある(償還請求権あり)。
- 資金化のスピード
- ファクタリング:最短即日も可能。
- 手形割引:数日〜1週間程度かかるのが一般的。
本文では、これらの違いが経営に与える影響や、あなたの会社がどちらを選ぶべきかをケース別に詳しく解説します。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認
まずはファクタリングと手形割引の仕組みの違いを理解しよう
資金調達を検討する上で、ファクタリングと手形割引の最も根源的な違いは、その「契約の性質」にあります。
ここを理解することが、最適な選択への第一歩です。
ファクタリング:売掛債権の「売買契約」
ファクタリングとは、貴社が保有する「売掛債権(請求書)」をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた代金を早期に受け取る取引です。
【ファクタリングの仕組み】
- 貴社が取引先に商品・サービスを提供し、売掛債権(請求書)が発生。
- 貴社がファクタリング会社に売掛債権を売却。
- ファクタリング会社から手数料を引いた代金が入金される。
- 期日になったら、ファクタリング会社が取引先から代金を回収する。(※3社間の場合)
重要なのは、これが債権の「売買」であるという点です。
つまり、借金ではありません。
私が銀行員時代に決算書を拝見する際にも、この点は非常に重要でした。
ファクタリングで得た資金は負債として計上されないため、貸借対照表(B/S)をスリムに保ち、今後の融資審査における評価を悪化させにくいというメリットがあります。
手形割引:約束手形を担保にした「融資(金融取引)」
一方、手形割引は、貴社が受け取った「約束手形」を支払期日前に銀行や手形割引業者に持ち込み、期日までの利息に相当する「割引料」を支払って現金化する方法です。
【手形割引の仕組み】
- 貴社が取引先から約束手形を受け取る。
- 貴社が銀行等に手形を持ち込み、割引を依頼(審査あり)。
- 銀行等から割引料を引いた代金が入金される。
- 期日になったら、銀行等が手形振出人(取引先)から代金を取り立てる。
これは手形を担保にした「融資」の一種であり、金融取引に分類されます。
そのため、貸金業法の規制対象となる場合があり、会計上も短期借入金として負債に計上されるのが一般的です。
【5つの視点で徹底比較】ファクタリングと手形割引の違い一覧
両者の違いをより明確にするため、5つの重要な視点で比較してみましょう。
一目でわかるように、まずは比較表をご覧ください。
| 比較項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 1. 契約の性質 | 債権の売買 | 手形を担保にした融資 |
| 2. 審査の対象 | 売掛先の信用力 | 自社と手形振出人の信用力 |
| 3. 回収不能リスク | 原則なし(ノンリコース) | あり(リコース) |
| 4. 手数料・コスト | 売買手数料(2%~18%) | 割引料(年利1.5%~15%) |
| 5. 資金化スピード | 最短即日~数日 | 数日~1週間程度 |
それでは、各項目について詳しく解説していきます。
1. 契約の性質:「債権売買」か「手形担保融資」か
前述の通り、ファクタリングは「債権の売買」、手形割引は「手形を担保とした融資」です。
この法的な性質の違いが、他のすべての違いの根源となっています。
【山崎の視点】
「売買」か「融資」かという違いは、単なる言葉の綾ではありません。
融資であれば、当然ながら会社の借入枠や信用情報に影響します。
一方、ファクタリングは資産(売掛債権)のオフバランス化(現金化)であり、財務体質を改善する効果も期待できるのです。
2. 審査の対象:「売掛先の信用力」か「自社の信用力」か
審査の重点が異なる点も、大きな違いです。
- ファクタリング
→ファクタリング会社が重視するのは「売却される売掛債権が、期日通りに支払われるか」です。そのため、審査の対象は主に売掛先の支払い能力や信用力となります。 - 手形割引
→金融機関は「万が一、手形が不渡りになった場合に、割引依頼者が買い戻せるか」を重視します。そのため、手形振出人の信用力はもちろん、割引を依頼する自社の信用力も厳しく審査されます。
この違いにより、赤字決算や税金滞納、創業間もないといった理由で銀行融資を断られた企業でも、売掛先の信用力が高ければファクタリングを利用できる可能性があります。
3. 回収不能リスク(償還請求権):「原則なし」か「あり」か
ここが両者を比較する上で、最も重要かつ決定的な違いと言えるでしょう。
償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)とは?
売掛先や手形振出人が倒産するなどの理由で支払い不能に陥った場合に、債権や手形を買い取った側(ファクタリング会社や銀行)が、元の所有者(利用者)に対して支払いを請求できる権利のこと。リコースとも呼ばれます。- ファクタリング
→日本で一般的なファクタリングは、この償還請求権がない「ノンリコース契約」です。万が一、売掛先が倒産しても、その損失はファクタリング会社が負担します。貴社が代金を返済する義務はありません。 - 手形割引
→償還請求権がある「リコース契約」です。手形が不渡りになった場合、貴社は金融機関からその手形を買い戻さなければなりません。
【最重要ポイント】
手形割引を利用するということは、取引先の倒産リスクを自社で引き受け続けることを意味します。
一方、ファクタリングは、手数料を支払うことで、その貸し倒れリスクごとファクタリング会社に移転する取引なのです。
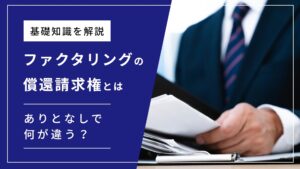
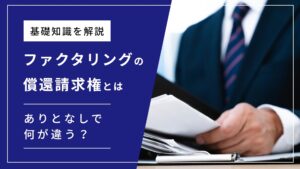
4. 手数料・コスト:「売買手数料」か「割引料(金利)」か
コストの構造も異なります。
ファクタリング手数料
相場は2社間(8%~18%)、3社間(2%~9%)程度です。この手数料には、審査費用や事務コストに加え、前述の「貸し倒れリスクに対する保険料」が含まれています。
手形割引料
銀行で年利1.5%~5.0%、手形割引業者で年利4.0%~15.0%程度が相場です。これはあくまで期日までの金利であり、貸し倒れリスクは利用者が負う前提の料金設定です。



一見するとファクタリングの手数料は割高に感じられるかもしれません。
しかし、それは「貸し倒れリスクの移転」という保険的な機能に対する対価が含まれているためとご理解ください。
5. 資金化までのスピード:「最短即日」か「数日~1週間」か
緊急時の資金調達においては、スピードも重要な判断基準です。
- ファクタリング
→特に利用者とファクタリング会社の2社間で行う「2社間ファクタリング」の場合、最短即日での資金化も可能です。これは売掛先への通知・承諾が不要なため、手続きが迅速に進むからです。- 手形割引
→銀行での割引は、自社の与信審査も伴うため、数日から1週間程度を要するのが一般的です。
急な支払いや資金ショートの回避など、一刻を争う場面ではファクタリングのスピードが大きな強みとなります。
【元銀行員が解説】手形割引が減少し、ファクタリングが注目される背景
私が銀行に在籍していた頃と比べ、近年、資金調達の現場では大きな構造変化が起きています。
手形割引の利用が減少し、ファクタリングが注目される背景には、国策や商習慣の変化が深く関わっています。
手形取引の減少と電子記録債権(でんさい)への移行
最も大きな要因は、政府が2026年度末をめどに紙の約束手形の利用を廃止する方針を打ち出していることです。
これに伴い、手形に代わる決済手段として、電子記録債権、通称「でんさい」への移行が急速に進んでいます。
「でんさい」はオンラインで完結するため、印紙税が不要で、紛失や盗難のリスクもありません。
この流れは今後さらに加速し、手形割引の対象となる「紙の手形」そのものが市場から減少していくことは確実です。


中小企業の商習慣の変化と売掛金の多様化
手形取引が減少する一方で、中小企業間の取引では、請求書を発行して後日入金を待つ「掛け取引」が主流となっています。
これにより、手形割引の対象となる債権が減り、ファクタリングの対象となる「売掛債権(請求書)」が増加するという構造的な変化が起きているのです。
こうした背景から、売掛債権を迅速に資金化できるファクタリングの重要性が、今後ますます高まっていくと私は見ています。
あなたの会社はどっち?ケース別・資金調達の選び方
それでは最後に、これまでの比較を踏まえ、どのような場合にどちらの手段が適しているのか、具体的なケース別に整理してみましょう。
ファクタリングがおすすめなケース
- とにかく早く資金が必要な場合(急な支払い、資金ショート対策など)
- 銀行融資を断られた、または審査に不安がある場合(赤字決算、税金滞納、創業初期など)
- 取引先の経営状況に不安があり、倒産リスクを回避したい場合
- 決算書上の負債を増やしたくない、財務体質を改善したい場合
- 取引先に資金調達の事実を知られたくない場合(2社間ファクタリング)
手形割引がおすすめなケース
- 受け取った「紙の約束手形」を現金化したい場合
- とにかく手数料・コストを低く抑えたい場合(貸し倒れリスクは自社で許容できる前提)
- 自社の信用力に自信があり、銀行の審査に通る見込みがある場合
- 今後の融資のために、銀行との取引実績を積みたい場合
よくある質問(FAQ)
Q: 償還請求権(リコース)とは、具体的にどういう意味ですか?
A: 売掛先が倒産などで支払い不能になった場合に、売却した債権を買い戻す(返金する)義務のことです。
手形割引にはこの義務がありますが、一般的なファクタリング(ノンリコース)にはありません。
この有無が、資金調達における最大のリスクの違いと言えるでしょう。
Q: 手形が不渡りになったら、どうなりますか?
A: 手形割引を利用していた場合、銀行や割引業者から手形の買い戻しを請求されます。
これに応じられない場合、自社の信用情報に傷がつき、今後の融資が非常に困難になる可能性があります。
まさに、連鎖倒産のリスクをはらんでいるのです。
Q: ファクタリングの手数料が高く感じるのですが…
A: ファクタリングの手数料には、ファクタリング会社が負う「売掛先の貸倒リスク」の保険料が含まれています。
そのため、融資の金利と比較すると高く感じられるかもしれません。
しかし、貸倒リスクを移転できるメリットを考慮すれば、一概に高いとは言えないケースもあります。
状況に応じた判断が重要です。
Q: 2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いは何ですか?
A: 3社間ファクタリングは売掛先の承諾を得て行い、手数料が安いのが特徴です。
一方、2社間ファクタリングは売掛先に通知せずに利用でき、スピーディーですが手数料は割高になります。
売掛先との関係性や資金調達の緊急度によって使い分けるのが一般的です。
Q: 個人事業主でも利用できますか?
A: はい、どちらも利用可能です。
ただし、手形割引は銀行取引が前提となることが多く、審査のハードルがやや高い傾向にあります。
一方、ファクタリングは個人事業主向けのサービスも豊富に存在します。
まとめ
ファクタリングと手形割引、二つの資金調達方法の違いについてご理解いただけたでしょうか。
両者は単に「どちらが優れているか」という問題ではなく、その「性質」が全く異なります。
・手形割引は「融資」
・ファクタリングは「債権売買」この本質を理解し、自社の信用力、資金調達の緊急性、そして最も重要な「回収不能リスクを誰が負うのか」という点を考慮することが、最適な選択に繋がります。
特に、償還請求権の有無は、万が一の際に経営を揺るがしかねない重大なポイントです。
本記事が、皆様の健全な資金繰りの一助となり、ご自身の会社に最適な一手を見極めるための材料となれば幸いです。
一度、ご自身の会社の状況を客観的に見つめ直し、最適な資金調達方法を考えてみてはいかがでしょうか。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認


-300x300.jpg)