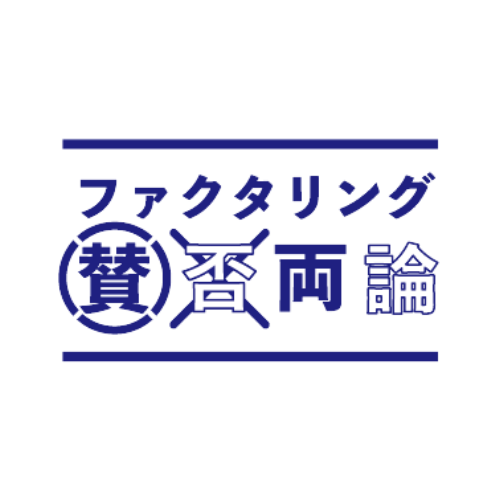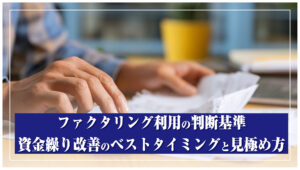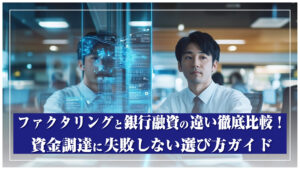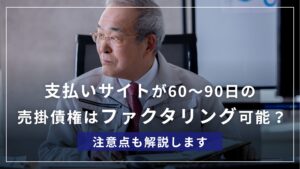「ファクタリングの仕訳、このままで本当に大丈夫だろうか――」
税務調査での指摘や決算書の信頼性低下を想像して、胸がざわつくことはありませんか?経理の現場では、融資とはまるで違う“債権売買”という特殊性ゆえに、勘定科目や税区分で迷いがちな場面が後を絶ちません。
この記事では 「2者間」「3者間」「保証型」それぞれのファクタリング取引を、仕訳から税務まで一気通貫で整理。読み終えるころには、
どの勘定科目を使えばよいか
消費税と法人税をどう扱えば安全か
税務調査で見られるポイントはどこか
――が、スッと腑に落ちるはずです。
 山崎正典
山崎正典結論を先にお伝えすると、ファクタリングは借入ではなく「売掛債権の売却」。したがって負債計上は不要で、手数料は「売上債権売却損」として処理するのが最も実態に即しています。
この記事では、その理由と仕訳フローを、元銀行員でファクタリング実務の最前線を経験した筆者が、税理士監修のもとでわかりやすく解説します。
さあ、正しい「ファクタリング仕訳」を身につけ、税務リスクに怯えない経理体制を手に入れましょう。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認
まずはおさらい!ファクタリング会計処理の基本原則
具体的な仕訳方法に入る前に、なぜその処理になるのか、という根本的な原則を理解することが重要です。
ここを押さえるだけで、応用的なケースにも迷わず対応できるようになります。
ファクタリングは「借入」ではなく「債権の売買」
最も重要なポイントは、ファクタリングは銀行融資のような「借入」ではなく、会社が保有する「売掛金(売掛債権)」という資産を売却する取引であるという点です。
- 銀行融資: 会社がお金を借り、将来返済する義務(負債)を負う取引。
- ファクタリング: 会社が持つ売掛金をファクタリング会社に売却し、対価として現金を受け取る取引。
この違いにより、会計処理には大きな差が生まれます。
借入ではないため、原則として貸借対照表(B/S)に負債が計上されません。
これを「オフバランス取引」と呼び、財務体質をスリムに見せる効果も期待できます。
なぜ正確な仕訳が重要なのか?税務リスクと経営判断への影響
「少しぐらい処理を間違えても大丈夫だろう」と考えてしまうのは危険です。
不正確な会計処理は、会社に二つの大きなリスクをもたらします。
- 税務リスク
→税務調査で会計処理の誤りを指摘された場合、修正申告が必要となり、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が発生する可能性があります。 - 信用の低下
→決算書の数値が実態と異なると、金融機関や取引先からの信用が低下し、将来の融資や取引に悪影響を及ぼす恐れがあります。
正確な会計処理は、会社を守り、健全な経営判断を行うための土台となるのです。
【ケース別】これで完璧!ファクタリングの仕訳方法を徹底解説
それでは、実際のケースに沿って具体的な仕訳方法を見ていきましょう。
自社の利用ケースに合わせてご確認ください。
ケース1:【2者間ファクタリング】の仕訳フロー
利用者とファクタリング会社の2社間で行う、最も一般的な契約形態です。
ここでは「売掛金100万円、手数料10%(10万円)」の例で解説します。
① 売掛金発生時
まずは通常通り、売上と売掛金を計上します。
【借方】売掛金 1,000,000円 / 【貸方】売上 1,000,000円② ファクタリング契約時
売却する売掛金を、管理上「未収入金」に振り替えます。これにより、どの売掛金がファクタリング対象か明確になります。
【借方】未収入金 1,000,000円 / 【貸方】売掛金 1,000,000円③ ファクタリング会社からの入金時
手数料を差し引かれた金額が振り込まれます。この手数料は「売上債権売却損」として費用計上します。
【借方】普通預金 900,000円 / 【貸方】未収入金 1,000,000円
【借方】売上債権売却損 100,000円 /④ 取引先からの入金とファクタリング会社への送金時
期日通りに取引先から売掛金が入金されたら、それをファクタリング会社へ送金します。このとき、一時的に預かったお金として「預り金」勘定を使います。
(取引先からの入金)
【借方】普通預金 1,000,000円 / 【貸方】預り金 1,000,000円(ファクタリング会社への送金)
【借方】預り金 1,000,000円 / 【貸方】普通預金 1,000,000円
ケース2:【3者間ファクタリング】の仕訳フロー
取引先の承諾を得て、利用者・ファクタリング会社・取引先の3社間で行う契約です。
「売掛金100万円、手数料5%(5万円)」の例で見ていきましょう。
3者間の場合、取引先が直接ファクタリング会社へ支払いを行うため、2者間のような「預り金」の処理が不要となり、仕訳がシンプルになります。
① 売掛金発生時
2者間と同様に、売上と売掛金を計上します。
【借方】売掛金 1,000,000円 / 【貸方】売上 1,000,000円② 契約・入金時
契約と同時に入金されるケースが一般的です。手数料を差し引いた金額が入金され、売掛金が消滅します。
【借方】普通預金 950,000円 / 【貸方】売掛金 1,000,000円
【借方】売上債権売却損 50,000円 /ケース3:【保証ファクタリング】の仕訳フロー
これは資金調達ではなく、取引先の倒産に備える「売掛金の保険」のようなサービスです。
① 保証契約時(保証料の支払い)
支払った保証料を費用として計上します。
【借方】支払手数料(または保証料) 50,000円 / 【貸方】普通預金 50,000円② 売掛金回収成功時
無事に取引先から入金があれば、通常の売掛金回収の仕訳を行うだけです。
【借方】普通預金 1,000,000円 / 【貸方】売掛金 1,000,000円③ 売掛金回収不能時(貸倒処理と保証金入金)
万が一、取引先が倒産して売掛金が回収不能になった場合の処理です。
(貸倒れの処理)
【借方】貸倒損失 1,000,000円 / 【貸方】売掛金 1,000,000円(保証金の入金)
【借方】普通預金 900,000円 / 【貸方】雑収入 900,000円
仕訳で迷わない!ファクタリングで使う勘定科目ガイド
どの勘定科目を使うべきか、改めて整理しておきましょう。
「売上債権売却損」とは?支払手数料との違い
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 売上債権売却損 | (推奨)売掛債権という資産を売却した際に生じた損失を示す科目。営業外費用に区分され、ファクタリングの実態に最も即している。 |
| 支払手数料 | 銀行振込手数料など、一般的な役務提供の対価を支払う際に使う科目。間違いではないが、債権売却の実態を示すには売上債権売却損がより適切。 |



会計ソフトに「売上債権売却損」がない場合は、新規で作成することをお勧めします。
もし難しい場合は、「支払割引料」や「雑損失」などで代用し、摘要欄に「ファクタリング手数料」と明記して、後から誰が見ても分かるようにしておくことが重要です。
「未収入金」「預り金」はどんな時に使う?
未収入金
2者間ファクタリングで、売却したもののまだファクタリング会社から入金されていない売掛金を管理するための科目です。通常の売掛金と区別する目的で使います。
預り金
2者間ファクタリングで、取引先から入金された売掛金を、ファクタリング会社に送金するまで一時的に預かっておくための科目です。あくまで一時的な負債となります。
経理担当者必見!ファクタリングの税務処理【消費税・法人税】
会計処理とセットで理解しておくべき税務のポイントです。特に消費税の扱いは間違いやすいので注意しましょう。
【消費税】ファクタリング取引は原則「非課税」
結論から言うと、ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。
これは、消費税法において、金銭債権の譲渡は「非課税取引」と定められているためです。
商品やサービスの提供ではないため、消費税の課税対象にはなりません。
【注意】課税対象となる付随費用
ファクタリング取引自体は非課税ですが、契約に付随して発生する以下の費用は課税対象となる場合があります。
- 債権譲渡登記にかかる司法書士への報酬
- 契約書の作成にかかる行政書士への報酬
【法人税】手数料は損金算入OK!節税効果と注意点
ファクタリング会社に支払う手数料(売上債権売却損)は、法人税法上、全額を「損金」として費用計上できます。
損金が増えることで、会社の利益(課税所得)が圧縮され、結果として法人税の負担を軽減する効果があります。
ただし、節税になるからといって安易に利用するのは禁物です。
ファクタリングはあくまで資金繰りを改善するための手段です。手数料負担は利益を確実に圧迫しますので、その必要性を慎重に判断することが肝要です。
【リスク回避】プロが教える会計処理の注意点と税務調査のポイント
最後に、私の実務経験から、経理担当者様が特に注意すべき点と、万が一の税務調査に備えるためのポイントをお伝えします。
経理担当者が陥りがちな3つの間違い
- 借入金として処理してしまう
ファクタリングを融資と混同し、「短期借入金」などで処理する誤りです。財務諸表の実態が歪むため、絶対に避けましょう。 - 手数料の計上時期を間違える(期ズレ)
手数料は、原則として契約が成立した事業年度に費用計上する必要があります。決算期をまたぐ取引では、入金が翌期でも費用は当期に計上する「発生主義」を徹底してください。 - 消費税を課税仕入れとしてしまう
手数料を非課税ではなく課税仕入れとして処理すると、消費税の納税額を不当に少なく申告することになり、税務調査で厳しく指摘されます。
税務調査でチェックされるポイントと準備すべき書類
税務調査官は、取引の「実態」が会計処理と一致しているかを重点的に見ます。
ファクタリングに関しては、特に以下の点がチェックされます。
- 本当に債権の売買か(実質的な貸付ではないか)
- 契約書と実際の入金額、手数料に相違はないか
- 売上債権売却損の金額は社会通念上、妥当な範囲か
- 消費税の区分は正しく「非課税」で処理されているか
これらの点について明確に説明できるよう、以下の書類は必ず整理・保管しておきましょう。
- ファクタリング会社との契約書
- 売却した売掛金の存在を証明する請求書や納品書の控え
- ファクタリング会社からの入金、取引先からの入金、ファクタリング会社への送金が確認できる通帳の記録
- (該当する場合)債権譲渡登記の登記事項証明書
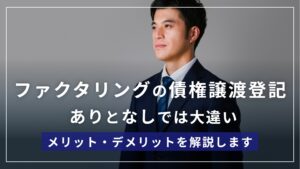
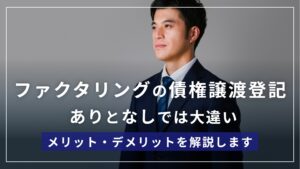
よくある質問(FAQ)
Q: ファクタリング手数料の勘定科目は「支払手数料」や「雑損失」ではダメですか?
A: 会計基準上は「売上債権売却損」が最も実態に即しており推奨されます。しかし、金額的な重要性が低い場合など、社内ルールとして「支払手数料」で継続的に処理することも実務上は認められています。重要なのは、一度決めたルールを継続し、勘定科目を統一することです。
Q: 個人事業主の場合、仕訳や税務は法人と異なりますか?
A: 仕訳の基本的な考え方(債権の売買として処理する点)は全く同じです。税務面では、法人の場合は「法人税」の計算上で損金になりますが、個人事業主の場合は「所得税」の計算上で「必要経費」として計上することになります。
Q: 会計ソフトに「売上債権売却損」の科目がありません。どうすれば良いですか?
A: 最も望ましいのは、ご利用の会計ソフトで勘定科目を新規作成することです。それが難しい場合は、「支払割引料」や「雑損失」といった既存の営業外費用科目で代用し、摘要欄に「ファクタリング手数料」と必ず明記して、取引内容が後から追跡できるようにしておくことを強くお勧めします。
まとめ
最後に、この記事の最も重要なポイントを3つにまとめます。
- ファクタリングは「借入」ではなく「債権の売買」。負債を増やさずに資金化できる。
- 2者間では「未収入金」「預り金」の処理が発生するが、3者間では不要でシンプル。
- 手数料は法人税の「損金」になるが、消費税は「非課税」。この区別が最重要。
ファクタリングの会計処理は、一見すると複雑に感じるかもしれません。
しかし、一度基本原則を理解してしまえば、決して難しいものではありません。
経理担当者の皆様の正確な仕事が、会社の信用と未来を支える土台となります。
この記事が、あなたの実務における不安を解消し、自信を持って業務に取り組むための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認

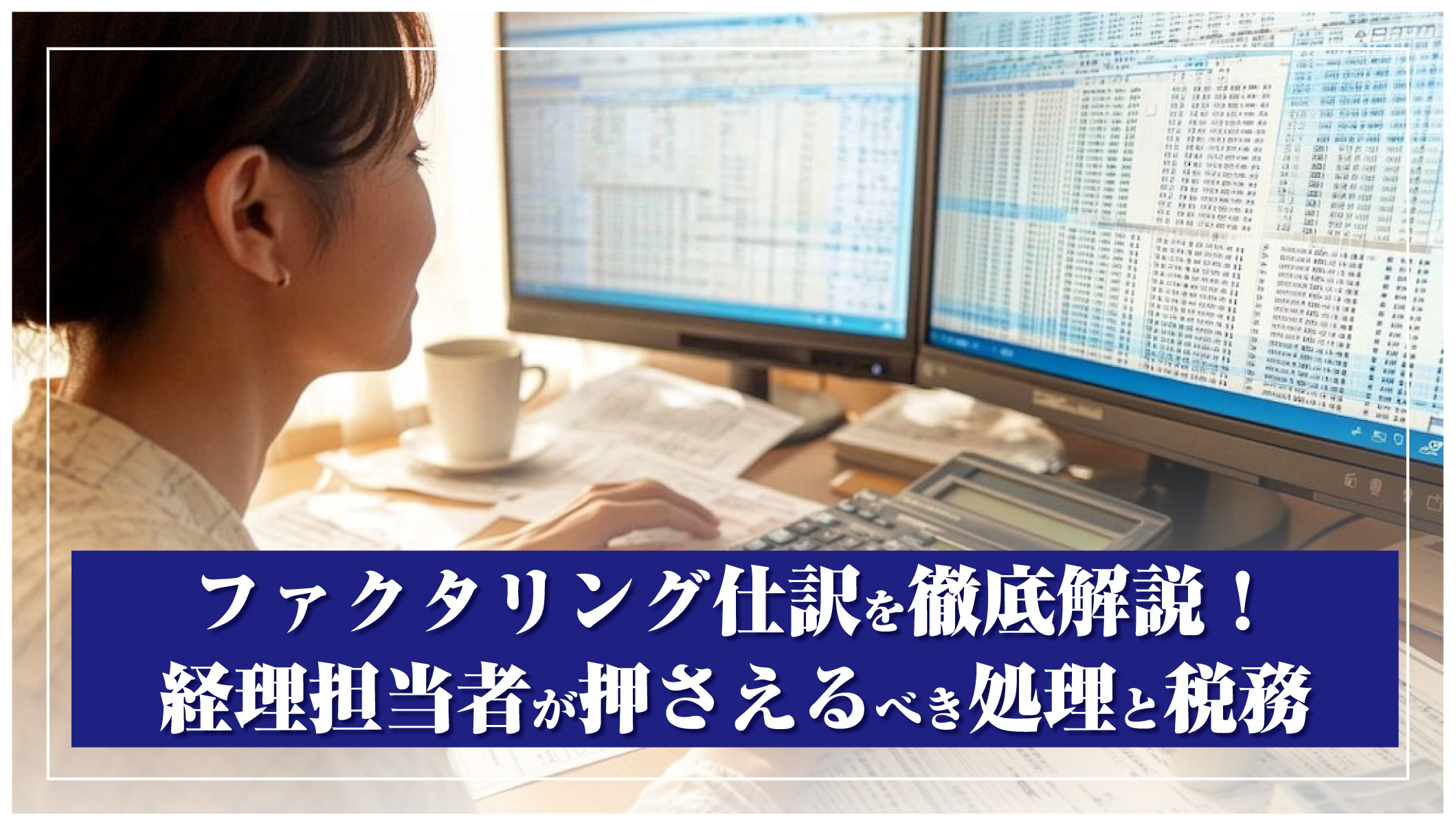
-300x300.jpg)