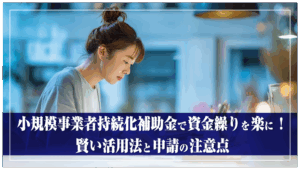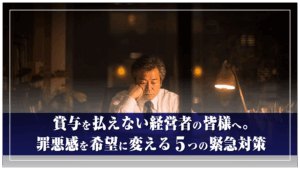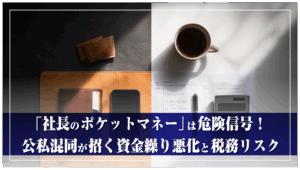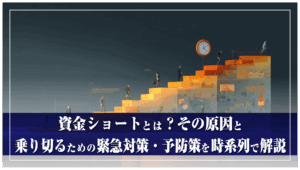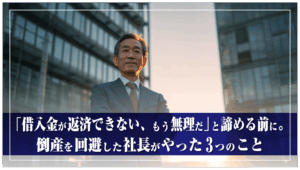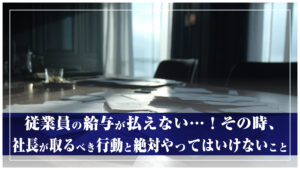「債務超過」――この言葉の重みに、眠れない夜を過ごしていませんか?「もう、打つ手はないのか…」と一人で不安を抱えているかもしれません。
ご安心ください。元銀行の融資審査担当で、現在は資金繰りコンサルタントとして多くの企業を再生に導いてきた私が断言します。債務超過でも、融資の道は決して閉ざされていません。
 佐々木 真帆
佐々木 真帆実は、民間の銀行が難色を示しても、政府系金融機関や公的制度を活用するといった突破口が存在します。
本記事では、私の経験のすべてを注ぎ込み、債務超過からでも融資を引き出すための「3つの具体的なルート」と、銀行担当者の心を動かす「経営改善計画書の書き方」を徹底解説します。
【この記事の結論】債務超過でも融資を受ける3つの鉄則
- 鉄則1:融資は可能。ただし「経営改善計画書」が生命線
債務超過でも融資の道はあります。しかし、なぜ債務超過に陥り、今後どのように3〜5年以内に解消するのかを具体的に示す「経営改善計画書」の提出が絶対条件です。 - 鉄則2:政府系金融機関・制度融資から検討する
民間の銀行が厳しい場合でも、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付や、信用保証協会を利用する地方自治体の「制度融資」は、事業の将来性を重視するため比較的相談しやすい窓口です。 - 鉄則3:金融機関には「誠実な情報開示」を徹底する
不利な情報も隠さず伝え、最新の月次試算表を持参するなど、改善に向けた行動を「行動で示す」ことが信頼獲得の鍵です。熱意だけでなく、数字的根拠に基づいた説明を心がけましょう。
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ債務超過だと融資は絶望的なのか?元銀行員が語る金融機関の本音
まず、敵を知ることから始めましょう。
なぜ金融機関は「債務超過」という言葉に、これほど敏感に反応するのでしょうか。
銀行員だった頃の経験から、その「本音」をお話しします。
貸借対照表(B/S)が示す危険信号
経営者の方なら、決算書はもちろんご覧になっていると思います。
その中でも、銀行員が融資審査で真っ先に、そして最も厳しくチェックするのが貸借対照表(B/S)の「純資産の部」です。
ここがマイナスになっている状態、つまり会社の資産をすべて売却しても、借入金などの負債を返しきれない状態が「債務超過」です。
これは、単に一時的な「赤字」とは全く意味が違います。
赤字は損益計算書(P/L)上の話で、一時的な投資がかさんだ結果かもしれません。
しかし債務超過は、これまでの赤字が積み重なった結果、会社の体力が完全に失われていることを示す、極めて危険なシグナルなのです。
損益計算書など財務諸表については以下の記事が参考になります。
銀行が恐れる「返済不能リスク」と「追加融資の罠」
銀行のビジネスは、極論すれば「貸したお金を、利息とともにきちんと返してもらう」ことで成り立っています。
債務超過の企業は、その大前提が崩れる「返済不能リスク」が極めて高いと判断されます。
さらに、私たち銀行員にはもう一つの恐れがありました。
それは「追加融資の罠」です。
安易に追加融資をした結果、それが根本的な経営改善に繋がらず、ただの延命措置になってしまう。
そして、最終的により大きな貸し倒れとなって銀行に返ってくる…
この事態を、私たちは何よりも恐れていました。
取引先からの信用失墜という二次被害
問題は銀行融資だけにとどまりません。
「あの会社は債務超過らしい」という噂は、あっという間に業界に広がります。
そうなると、仕入れ先から「支払いを現金にしてほしい」と言われたり、新規の取引を断られたりと、事業そのものの継続が困難になる二次被害が発生します。



私が担当していたある製造業の会社も、素晴らしい技術力がありながら債務超過に陥ったことで主要な取引先を失い、非常に苦しい状況に追い込まれてしまいました。
融資が受けられないことは、事業の根幹を揺るがす事態に直結するのです。
債務超過でも融資の可能性はある!検討すべき3つの資金調達ルート
絶望的な話ばかりしてしまいましたが、ここからが本題です。
民間の銀行が厳しい姿勢を見せる中でも、まだ道は残されています。
私がコンサルタントとして、多くの経営者とこじ開けてきた3つのルートをご紹介します。
ルート1:政府系金融機関(日本政策金融公庫など)のセーフティネット貸付
まず最初に相談すべきは、日本政策金融公庫などの政府系金融機関です。
これらの機関は、民間の金融機関とは異なり、中小企業の支援や国の政策実現を目的としています。
そのため、一時的に業況が悪化している企業向けの「セーフティネット貸付」や、事業再生に取り組む企業を対象とした「企業再生貸付」といった制度が用意されています。
私が支援したあるIT企業は、先行投資が重なり債務超過に陥っていましたが、事業の将来性を評価され、日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」を活用して資金調達に成功しました。
民間の銀行では「過去の数字」で判断されがちですが、公庫は「未来の計画」をより重視してくれる傾向があります。
ルート2:地方自治体の「制度融資」と信用保証協会の活用
次に検討したいのが、都道府県や市区町村が設けている「制度融資」です。
これは、自治体が金融機関の貸付原資の一部を負担したり、利子の一部を補助したりすることで、中小企業が融資を受けやすくする制度です。
この制度の最大のポイントは「信用保証協会」の存在です。
信用保証協会が公的な保証人となることで、万が一返済が滞っても、協会が金融機関に代位弁済してくれます。
これにより、金融機関のリスクが大幅に軽減されるため、プロパー融資(銀行が100%リスクを負う融資)に比べて審査のハードルが格段に下がるのです。
ルート3:ビジネスローンやファクタリングの賢い使い方
最後の手段として、ノンバンク系のビジネスローンや、売掛債権を売却して現金化するファクタリングがあります。
正直に申し上げて、これらは金利が高かったり、手数料がかかったりと、財務を圧迫するデメリットもあります。
しかし、「あと数日を乗り切れば黒字化の目処が立つ」といった、短期的な資金繰りを改善するための「つなぎ資金」としては、非常に有効な選択肢となり得ます。
ファクタリングを利用する際は、必ず複数の会社から見積もりを取り、手数料を比較検討してください。また、契約内容を十分に理解し、将来のキャッシュフローを圧迫しないか冷静に判断することが重要です。安易な利用は、かえって状況を悪化させる可能性もあります。
融資実現の生命線!元銀行員が教える「経営改善計画書」の書き方
どのルートを辿るにせよ、絶対に必要になるのが「経営改善計画書」です。これは、あなたの会社が融資を実現するための、まさに生命線と言えます。
なぜ計画書が重要なのか?銀行は「未来」を見ている
銀行員だった頃、私は数え切れないほどの計画書を見てきました。
その経験から断言できるのは、銀行は「未来」を見ているということです。
過去の決算書がどんなに悪くても、「この計画なら再生できる」と担当者を納得させることができれば、道は開けます。
根性論や精神論ではなく、数字的根拠のある計画こそが、担当者の心を動かすのです。
銀行担当者が必ずチェックする5つの必須項目
私がコンサルタントとしてクライアントに指導している、銀行担当者が必ずチェックする計画書の必須項目は以下の5つです。
1. 現状分析
なぜ債務超過に至ったのか。市場の変化、競合の動向、自社の弱みなどを客観的に分析します。
責任転嫁ではなく、真摯な自己分析が信頼の第一歩です。
2. 具体的な改善策
コスト削減、売上向上策など、誰が・いつまでに・何をするのかを具体的に記述します。
「経費を削減します」ではなく、「〇〇の仕入れ先を見直し、年間△△万円のコストを削減します」といったレベルまで落とし込みます。
3. 数値計画
改善策を実行した結果、損益や資金繰りがどう変化するのかを、具体的な数字で示します。最低でも3〜5年分の計画は必要です。
4. 返済計画
今回借り入れる資金を、どのように返済していくのか。数値計画と連動した、現実的なシミュレーションが不可欠です。
5. モニタリング体制
計画が順調に進んでいるか、誰がどのようにチェックするのかを示します。毎月、試算表を銀行に提出するなど、進捗報告の体制を明確にすることで、銀行は安心します。
ケーススタディで学ぶ!NG計画書とOK計画書の違い
言葉だけでは分かりにくいので、私が実際に見てきた例を基に、NG計画書とOK計画書の違いを比較してみましょう。
| 項目 | NG計画書(これでは通らない…) | OK計画書(これで融資を引き出せた!) |
|---|---|---|
| 原因分析 | 「景気の悪化により売上が減少した」 | 「主要取引先A社の海外移転に伴い、売上が前期比30%減少。加えて、新規開拓営業が不足していたことが原因」 |
| 改善策 | 「全社一丸となって営業努力を徹底し、売上をV字回復させる」 | 「①不採算のB事業から撤退し、年間500万円の固定費を削減。②強みであるC事業に経営資源を集中し、既存顧客へのアップセルで単価を15%向上させる」 |
| 数値計画 | どんぶり勘定で、希望的観測に基づいた売上予測が並んでいる | 過去の実績や市場データに基づいた、現実的な売上・利益計画が月次単位で詳細に作成されている |
違いは一目瞭然だと思います。
NG計画書は、気持ちは分かりますが、具体性と客観性に欠けています。
一方、OK計画書は、痛みを伴う改革(不採算事業からの撤退)にも言及し、実現可能なアクションプランと数字的な裏付けが明確です。
これこそが、銀行が「この経営者は本気だ」と感じる計画書なのです。
これで突破口を開く!金融機関との交渉を成功させる3つの秘訣
完璧な計画書ができたら、次はいよいよ交渉のテーブルにつきます。
ここでも、元銀行員だからこそ分かる「担当者の心を動かす」秘訣があります。
秘訣1:「試算表」を毎月持参し、改善の意思を行動で示す
決算書は年に一度の結果報告書に過ぎません。
銀行が本当に知りたいのは「今、会社がどうなっているのか」です。
ですから、交渉の場には必ず最新の月次試算表を持参してください。
たとえわずかでも業績が上向いていれば、それは計画が順調に進んでいる何よりの証拠になります。
「口だけでなく、行動で示している」という姿勢が、担当者の信頼を勝ち取るのです。
秘訣2:専門用語を避け、自分の言葉で「事業の強み」を語る
時々、難しい財務用語を並べて説明しようとする経営者の方がいらっしゃいます。
しかし、忘れないでください。
担当者は財務のプロですが、あなたの事業のプロではありません。
彼らが本当に聞きたいのは、あなたの会社のサービスや製品が、顧客のどんな課題を解決し、市場でどんな強みを持っているのか、という事業の本質的な価値です。



難しい言葉は不要です。経営者であるあなた自身の、熱意ある言葉で事業の将来性を語ってください。その熱意は、必ず相手に伝わります。
秘訣3:隠し事をせず、最悪の事態も想定していると誠実に伝える
これが最も重要かもしれません。
自社にとって不利な情報、例えば「主要な取引先から取引縮小の打診を受けている」といったことを隠してはいけません。
こうした情報は、銀行はいずれ必ず掴みます。後から発覚する方が、よほど心証を悪くします。
むしろ、「実はこういう厳しい状況もあります。だからこそ、この融資でこう立て直したいのです。もし、万が一この融資が通らなければ、法的整理も視野に入れています」と、誠実に、そして覚悟を持って伝えるのです。
一見、不利な交渉に見えるかもしれません。
しかし、腹を割って話すことで、「この経営者は信頼できる」と担当者は感じます。
そして、「ここで見捨てたら倒産してしまう。何とか支援する方法はないか」と、真剣にあなたの会社の再生を考えてくれるようになるのです。
これが、私が銀行員時代に何度も見てきた、土壇場からの逆転劇でした。
よくある質問(FAQ)
Q: 債務超過はどのくらいの期間で解消すべきですか?
A: 元銀行員の視点から言うと、理想は3年、最長でも5年以内に解消する計画を示すことが望ましいです。 計画の実現可能性を示す上で、この期間設定は非常に重要なポイントになります。なぜ5年で解消できるのか、具体的な収益改善策とセットで提示することが不可欠です。
Q: すでに返済のリスケジュール中ですが、追加融資は可能ですか?
A: 非常に厳しい状況ですが、可能性はゼロではありません。 リスケジュール中に、当初提出した経営改善計画通り、あるいは計画以上に業績が改善していることを明確なデータ(月次試算表など)で示せれば、金融機関も追加支援を検討する余地が出てきます。
実際に私がコンサルしたケースでも、リスケ中に利益率が大幅に改善したことを示し、追加の運転資金を引き出すことに成功した事例があります。
Q: 経営者個人の資産を担保に入れれば、融資を受けやすくなりますか?
A: はい、融資の可能性は高まります。しかし、それは経営者個人が会社の債務をすべて背負うことを意味します。 安易に個人資産を担保に入れる前に、事業の再生可能性を冷静に見極めることが重要です。
近年は「経営者保証に関するガイドライン」が整備され、一定の要件を満たせば経営者保証なしで融資を受けられる可能性もありますので、まずはその道を模索すべきです。
Q: 専門家(コンサルタント)に相談するメリットは何ですか?
A: 金融機関が納得するレベルの経営改善計画書を、自社だけで客観的に作成するのは非常に困難です。私のような元銀行員のコンサルタントは、金融機関がどこをチェックし、どんな言葉を求めているのかという「審査の視点」を熟知しています。そのため、審査を通過しやすい計画書の作成や、交渉のシミュレーションが可能です。
何より、孤独な戦いになりがちな経営者にとって、客観的な第三者の視点と精神的な支えを得られることが最大のメリットだと考えています。
まとめ:あなたの行動が、未来を切り拓く
債務超過は、企業にとって深刻な危機ですが、決して「終わり」を意味するものではありません。
元銀行員として、そして今、多くの経営者と伴走するコンサルタントとして確信しているのは、誠実な姿勢と、数字に裏付けられた具体的な再建計画こそが、金融機関の心を動かし、未来を切り拓く力になるということです。
本記事でご紹介したステップと交渉術は、明日からすぐに実践できるものばかりです。
まずは自社の現状を正確に把握し、実現可能な経営改善計画の策定から始めてみてください。
一人で抱え込まず、必要であれば日本政策金融公庫や地域の商工会議所、そして私のような専門家の力も借りながら、この困難を乗り越えていきましょう。
あなたの会社の未来は、あなたの今日の行動にかかっています。


💰 企業の資金繰り改善を最短ルートで実現
┗ 最短3時間での資金調達が可能
┗ 経営状況に合わせた最適な調達方法を提案
┗ 専門アドバイザーによる無料相談サービス
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金調達の選択肢を広げる