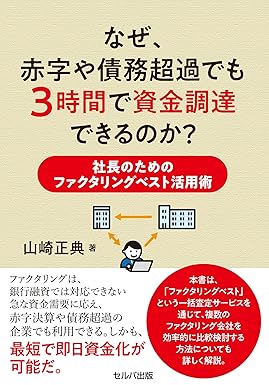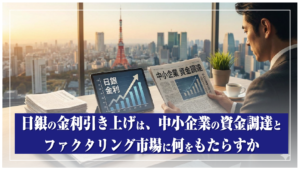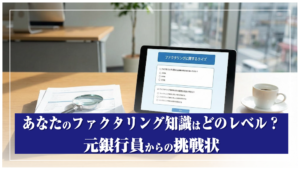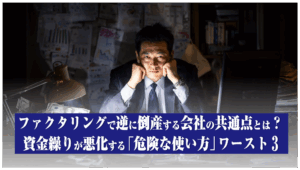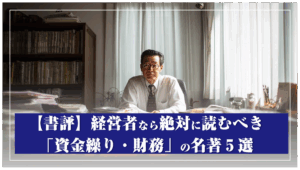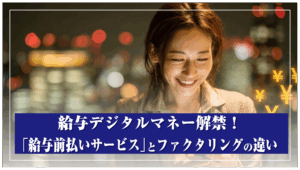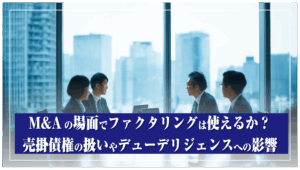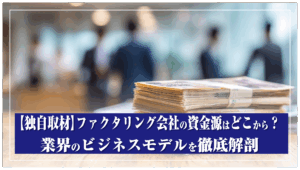こんにちは。
「ファクタリング賛否両論事務局」の山崎 正典(やまざき まさのり)です。
 山崎正典
山崎正典元銀行員として、またファクタリング会社の現場を経験した者として、日々多くの中小企業経営者様から資金繰りに関するご相談をいただきます。
その中で、近年「ファクタリングは経済産業省が推奨しているから安心だ」というお話を耳にする機会が増えました。
確かに、国は中小企業の資金調達手段を多様化させるため、売掛債権の活用を力強く推進しています。
しかし、なぜ国がそこまで注目するのか、その本当の狙いはどこにあるのでしょうか。
そして、最も重要なことですが、国の推奨は「すべてのファクタリング会社が安全である」というお墨付きを意味するものでは決してありません。
本記事では、経済産業省がファクタリングを含む債権流動化を推奨する本当の理由、その背景にある中小企業金融の根深い課題、そして今後の法整備の展望について、私が現場で見てきた実例も交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認
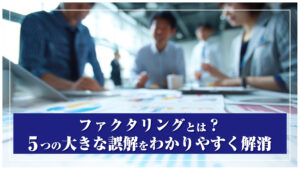
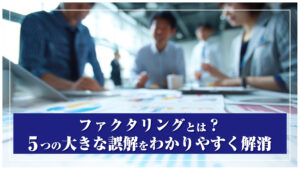
なぜ今、ファクタリングが「国策」として注目されるのか?
「国が推奨している」と聞くと、何か特別な、新しい制度のように聞こえるかもしれません。
しかし、その背景には、日本の中小企業金融が長年抱えてきた、構造的な課題が存在します。
中小企業金融の現状と、国が抱える課題意識
私が銀行員として融資の最前線にいた頃、痛感していたことがあります。
それは、日本の中小企業金融がいかに「銀行融資への過度な依存」と「不動産担保至上主義」に縛られているか、という現実です。
「担保になる不動産はお持ちですか?」
「保証人になっていただける方は…」
事業の将来性や素晴らしい技術力があっても、この二つの壁に阻まれ、涙をのむ経営者を何人も見てきました。
この状況は、リーマンショックや近年のコロナ禍といった経済危機を経て、さらに深刻化します。
経済が不安定になると、銀行は融資の審査をより厳しくせざるを得ません。
結果として、本当に資金を必要としている中小企業にお金が届かない「目詰まり」が起きてしまうのです。
【山崎の視点:元銀行員の本音】
銀行も営利企業ですから、貸し倒れリスクは絶対に避けたい。だからこそ、回収の確実性が高い不動産担保を重視するのは、ある意味で当然の判断です。
しかし、その結果、経済の毛細血管である中小企業に血液(資金)が巡らなくなり、日本経済全体の活力が失われてしまう。
国が抱えるのは、まさにこの点に対する強い危機感なのです。
この危機感から、国は「銀行融資」という一本足打法から脱却し、中小企業の資金調達手段を多様化させる必要性を強く認識しました。
その答えの一つが、企業が持つ「売掛債権」という眠れる資産の活用だったのです。
経済産業省(中小企業庁)が売掛債権の活用を推し進める真意
経済産業省、特にその外局である中小企業庁は、公式サイトでも明確に「売掛債権の利用促進」を掲げています。
ここで重要なのは、国が「ファクタリング会社を推奨している」のではなく、「『売掛債権』という資産を流動化させ、企業のキャッシュフローを改善すること」を目的としている点です。



ファクタリングは、その目的を達成するための、あくまで有効な選択肢の一つとして位置づけられています。
つまり、国のメッセージを正確に翻訳するならば、
「中小企業の皆さん、銀行から借りるだけが資金調達ではありませんよ。皆さんが持っている『売掛金』も立派な資産です。それを売却(ファクタリング)したり、担保に入れたり(ABL)して、もっと積極的に事業資金として活用してくださいね」
ということなのです。
追い風となった2020年の民法(債権法)改正
この国の後押しをさらに加速させたのが、2020年4月1日に施行された民法(債権法)の改正です。
それ以前は、取引先との契約書に「この売掛金は、他人に譲渡してはいけません(譲渡禁止特約)」という一文が入っていると、ファクタリングの利用が非常に困難でした。
しかし、この民法改正によって、たとえ譲渡禁止特約が付いていても、原則として債権の譲渡(ファクタリング)は有効とされたのです。
これは、中小企業がファクタリングを利用する上での、非常に大きな障壁が取り払われたことを意味します。
この法改正は、まさに国が中小企業の資金調達を本気で後押ししようとしている姿勢の表れと言えるでしょう。
国の推奨 ≠ すべての業者が安全。潜むリスクと見極めの重要性
さて、ここからが本記事で最もお伝えしたい、重要なパートです。
国が売掛債権の活用を推奨しているからといって、すべてのファクタリング会社が善良で、安全なわけでは決してありません。
ファクタリング業界が抱える「無法地帯」という側面
最大の問題は、ファクタリング業を直接的に規制する「業法」が存在しないことです。
例えば、消費者金融などの貸金業者は「貸金業法」という厳しい法律によって、登録制度や金利の上限などが厳しく定められています。
しかし、ファクタリングは「債権の売買」という扱いのため、この貸金業法の規制対象外なのです。
【山崎の警告】
業法がないということは、極端に言えば、誰でも「明日からファクタリング会社です」と名乗れてしまうということです。
そのため、残念ながら法律の知識に乏しい経営者を狙った悪質な業者が参入しやすい「無法地帯」という側面があるのは否定できない事実です。
実際に金融庁や消費者庁も、ファクタリングを装ったヤミ金業者に対して、繰り返し厳しい注意喚起を行っています。
「国が推奨しているから」という言葉を鵜呑みにし、安易に業者を選んでしまうことほど危険なことはありません。
【事例で解説】悪質業者の手口と見分け方
私がファクタリング会社に勤務していた頃、同業の悪質な手口に関する相談を数多く受けました。
その中でも特に注意すべき点と、安全な業者を見分けるためのチェックポイントをお伝えします。
| 悪質業者の手口 | 安全な業者を見分けるチェックポイント |
|---|---|
| ①法外な手数料 年利に換算すると貸金業法の上限をはるかに超える手数料を請求する。 | 手数料の内訳が明確か? 「審査料」「事務手数料」など、内訳をきちんと説明してくれるか確認する。相見積もりを取り、相場から逸脱していないかチェックする。 |
| ②償還請求権(リコース)付き契約 売掛先が倒産した場合、利用者が返済義務を負う契約。実質的な「借金」と同じ。 | 「ノンリコース契約」か? 契約書に「償還請求権なし」「ノンリコース」と明記されているか必ず確認する。これが本来のファクタリングの形です。 |
| ③契約書の内容が不透明 契約書を渡さなかったり、不利な条項を小さな文字で記載したりする。 | 契約書を事前に確認できるか? 契約前に必ず契約書のひな形をもらい、不明な点は一つ残らず質問する。誠実な業者なら丁寧に説明してくれます。 |
| ④資金の預かり 「債権の回収を代行する」と称して、売掛先からの入金を自社の口座に振り込ませ、そこから手数料を差し引いて利用者に渡す。持ち逃げのリスクがある。 | 入金口座は自社名義か? 売掛先からの入金は、あくまで自社の口座で受け取るのが原則です(3社間ファクタリングで、債権譲渡登記を行う場合などを除く)。 |
これらのポイントは、経営者自身が会社を守るための「鎧」となります。必ず覚えておいてください。
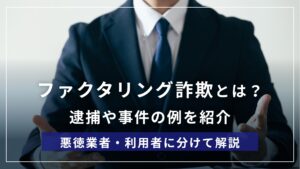
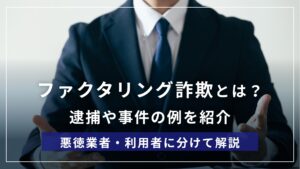
「国が推奨しているから」という安易な判断の危険性
繰り返しになりますが、これが最も重要な心構えです。
国の推奨は、あくまで「売掛債権の活用」という大きな方針です。
個別のファクタリング会社に、国がお墨付きを与えているわけでは断じてありません。
この違いを正しく理解し、国の施策は追い風と捉えつつも、最終的な業者選びは自分自身の責任で行うという「自衛の意識」を持つことが不可欠です。
ファクタリングの今後の展望と中小企業が取るべきスタンス
では、今後ファクタリング業界はどのようになっていくのでしょうか。
そして、経営者である私たちは、どう向き合っていくべきなのでしょうか。
期待される法整備と業界の健全化
現在、ファクタリングに関する法整備の議論が水面下で進んでいます。
無法地帯となっている現状を問題視し、利用者保護を目的としたルール作りが検討されているのです。
将来的には、
- 業者の登録制度の導入
- 手数料の上限設定
- 契約内容に関する説明義務の強化
といったルールが定められる可能性があります。
もし法整備が実現すれば、悪質な業者は淘汰され、業界全体の信頼性が向上します。
そうなれば、経営者の皆様がより安心してファクタリングサービスを選べる時代が来るでしょう。
手形廃止の流れとオンライン化の加速
もう一つの大きな変化が、政府が推進する2026年度末を目標とした「紙の約束手形の廃止」です。
これまで手形割引で資金繰りを行ってきた企業にとって、その代替手段は喫緊の課題となります。
その有力な受け皿として、ファクタリングの需要は今後ますます高まっていくと予測されます。
同時に、手続きのオンライン化も急速に進んでいます。
かつては対面での面談や書類の郵送が必須でしたが、今では申し込みから入金まで、すべてWeb上で完結するサービスも珍しくありません。
この利便性の向上も、ファクタリングの普及を後押しする大きな要因となるでしょう。


経営者として今、どう向き合うべきか?
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
最後に、プロフェッショナルとしての私の結論をお伝えします。
ファクタリングは、正しく理解し、信頼できるパートナーを選びさえすれば、貴社のキャッシュフローを劇的に改善し、事業成長のアクセルとなり得る、非常に強力なツールです。
しかし、その一方で、リスクも伴う諸刃の剣でもあります。
大切なのは、経営者であるあなた自身が、
- 自社の資金繰りの状況を正確に把握すること
- 銀行融資、公的融資、ファクタリングなど、複数の選択肢のメリット・デメリットを理解すること
- その上で、自社にとって最適な手段を「自ら選ぶ」リテラシーを持つこと
この3つです。



「国が推奨しているから」と鵜呑みにするのではなく、あくまで数ある選択肢の一つとして冷静に捉え、賢く活用する。
その視点こそが、これからの時代を乗り切る経営者に求められる姿勢だと、私は確信しています。
よくある質問(FAQ)
Q1: 経済産業省が推奨しているなら、どのファクタリング会社も安全ですか?
A1: いいえ、安全とは限りません。経済産業省(中小企業庁)が推奨しているのは「売掛債権の活用」という方針であり、個別の業者を保証するものではありません。
ファクタリングには法規制が未整備な面もあるため、悪質な業者が存在するのも事実です。契約内容をよく確認し、信頼できる業者を自身で見極める必要があります。
Q2: ファクタリングと、国が推進する「売掛債権担保融資(ABL)」との違いは何ですか?
A2: 最も大きな違いは、ファクタリングが売掛債権の「売買(譲渡)」であるのに対し、売掛債権担保融資(ABL)は売掛債権を「担保」にした「融資(借入)」である点です。ABLは金融機関からの借入なので返済義務がありますが、ファクタリング(ノンリコース契約の場合)は売掛先が倒産しても返済義務は生じません。
Q3: 国が推奨することで、ファクタリングの手数料は安くなりますか?
A3: 直接的に安くなるわけではありません。国の推奨は市場の活性化を促しますが、手数料は各社のサービス内容や売掛先のリスク評価によって決まります。ただし、今後法整備が進めば、不当に高い手数料を請求する業者は淘汰され、市場全体として手数料が適正化される可能性は考えられます。
Q4: 今後、法規制が強化されると、ファクタリングは利用しにくくなりますか?
A4: 一概にそうとは言えません。法規制は、悪質業者を排除し、利用者を保護することが目的です。適正な運営をしている会社にとっては大きな影響はなく、むしろ業界全体の信頼性が高まることで、利用者はより安心してサービスを選べるようになる可能性があります。
Q5: 個人事業主でも、国の推奨する流れの恩恵を受けられますか?
A5: はい、受けられます。国の施策は中小企業全般を対象としており、個人事業主も含まれます。実際に個人事業主向けのファクタリングサービスも多数存在します。ただし、法人と同様に、業者選びは慎重に行う必要があります。
まとめ:国策の風を読み、自社の舵を取る
本記事では、経済産業省がファクタリングを含む売掛債権の活用を推奨する真意と、その背景、そして今後の展望について、私の経験を交えながら解説しました。
国の狙いは、銀行融資に偏りがちな中小企業の資金調達を多様化し、日本経済全体の血流を良くすることにあります。
民法改正や手形廃止の流れは、間違いなくファクタリング業界にとって追い風です。
しかし、その風に乗るためには、まず「羅針盤」と「海図」が必要です。
羅針盤とは、自社の財務状況を正確に把握する力。
海図とは、ファクタリングのメリット・デメリットを正しく理解する知識です。
国の推奨という追い風を過信して、羅針盤も海図も持たずに航海に出れば、悪質業者という暗礁に乗り上げてしまいかねません。
今回の内容を参考に、国策の大きな流れを理解しつつも、常に冷静な目で自社に最適な選択肢を見極める。
そのお手伝いができたのであれば、これに勝る喜びはありません。
資金繰りの悩みは、経営者にとって最も孤独で、心細い戦いだと思います。
もし一人で抱え込んでいるのであれば、ぜひ一度、私たち「ファクタリング賛否両論事務局」にご相談ください。
元銀行員、そしてファクタリングのプロとして、あなたの会社の明日を切り拓くための最適な一手を見つけるお手伝いをさせていただきます。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認

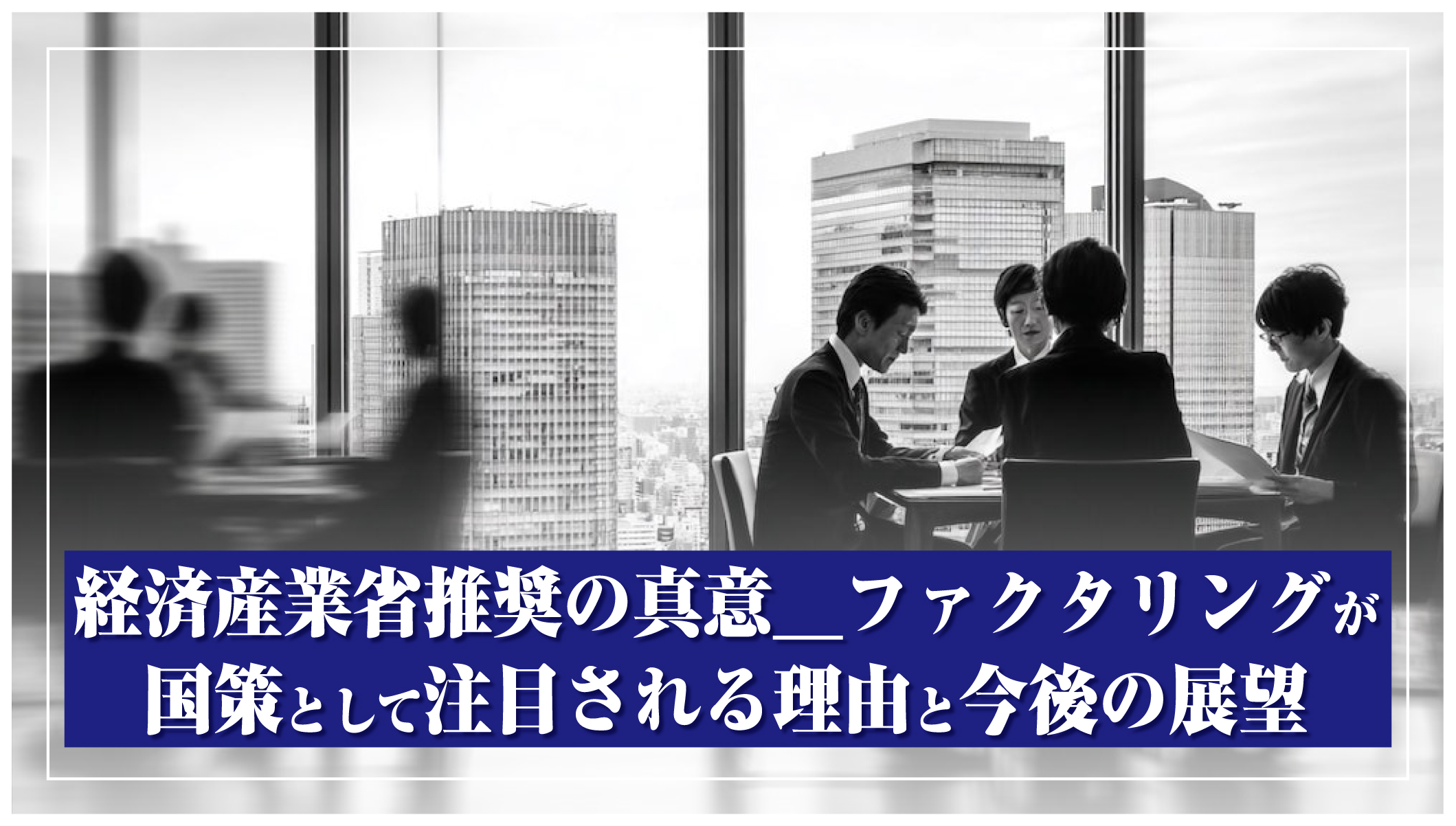
-300x300.jpg)