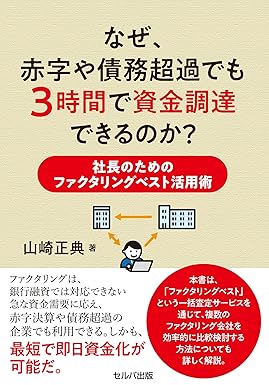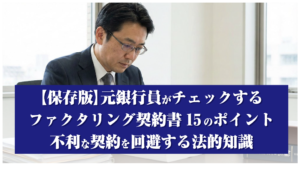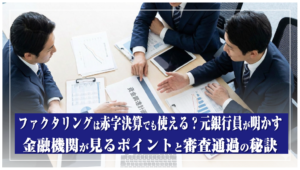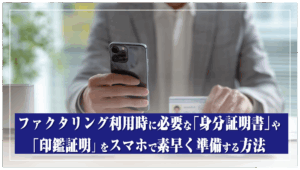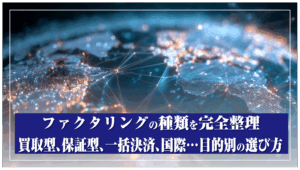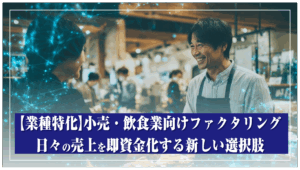「ファクタリングの返済期間はどのくらい?」
結論から言うと、ファクタリングに「返済期間」という概念は存在しません。なぜなら、ファクタリングは借入ではなく債権売却だからです。
 山崎正典
山崎正典多くの経営者が「返済期間」と誤解している期間は、実は売却済み債権の「支払期日」であり、この違いを理解していないことが重大なトラブルの原因となっています。
こんにちは。「ファクタリング賛否両論事務局」の山崎正典です。
私は大手都市銀行での融資業務とファクタリング専門会社での実務経験を通じて、この「返済期間」という誤解が引き起こす深刻な契約違反を数多く目撃してきました。
「支払期日までに払えなかったらどうなるんだろう…」そんな不安を抱えている方も多いでしょう。
本記事では、ファクタリングの正しい支払い仕組みから期日管理、遅延時の対処策まで、現場で培った実践的なノウハウを全てお伝えします。
この記事を読めば、あなたは「返済期間」という誤解から解放され、失敗しないための支払い計画を立て、安心してファクタリングを事業成長の力に変えることができるようになるでしょう。
そもそもファクタリングに「返済」はない?銀行融資との根本的な違い
まず、最も重要なことからお伝えします。
結論から言うと、ファクタリングに「返済」という概念は存在しません。
これは、銀行融資との根本的な違いを理解する上で、絶対に押さえておかなければならないポイントです。
「返済」ではなく「支払い」:債権譲渡という仕組みの理解
なぜ「返済」ではないのか。
それは、ファクタリングが「借金(融資)」ではなく、貴社が持つ「売掛債権(請求書)という資産の売却(譲渡)」だからです。



私が銀行員だった頃、融資の契約書には必ず「金銭消費貸借契約」と書かれていました。
これは文字通り「お金を借りて、消費し、そして返済する」という契約です。
だからこそ、借りた側には元本と利息を返す「返済義務」が生じます。
一方で、ファクタリングは「債権譲渡契約」です。
これは、例えるなら、あなたが持っている車や不動産を中古業者に売却するのと同じです。
売却したのですから、当然、後からそれを「返済する」義務はありませんよね。
ファクタリングは、この「売る」対象が、車や不動産ではなく「売掛債権」に変わっただけなのです。
| 項目 | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 契約の種類 | 金銭消費貸借契約(借入) | 債権譲渡契約(売買) |
| 資金の性質 | 負債(借金) | 資産の現金化 |
| 義務 | 返済義務 | 支払い義務(2社間の場合) |
| 信用情報 | 登録される | 原則、登録されない |
このように、両者は全くの別物です。
この違いを理解することが、ファクタリングを正しく活用するための第一歩となります。
2社間と3社間で異なる「支払い」の流れ
ファクタリングには、主に「2社間」と「3社間」の2つの契約形態があり、それぞれでお金の流れが異なります。
2社間ファクタリング
- 貴社がファクタリング会社に売掛債権を売却し、資金を受け取る。
- 期日通り、売掛先から貴社に売掛金が入金される。
- 貴社は、入金された売掛金をファクタリング会社に「支払う」。
3社間ファクタリング
- 貴社がファクタリング会社に売掛債権を売却する(この際、売掛先の承諾を得る)。
- 期日通り、売掛先が直接ファクタリング会社に売掛金を支払う。
お分かりでしょうか。
3社間ファクタリングの場合、貴社はファクタリング会社への「支払い」という行為自体が発生しません。
そのため、横領などのリスクがなく、手数料も安くなる傾向にあります。
一方で、売掛先に知られずに資金調達ができる2社間ファクタリングでは、貴社が一旦受け取った売掛金をファクタリング会社に送金する、というプロセスが発生します。
【プロの視点】なぜ「返済」と誤解してしまうのか?
私がファクタリング会社で営業をしていた頃、多くの経営者がこの「支払い」を「返済」と混同されていました。
その最大の理由は、やはり2社間ファクタリングの「回収した売掛金をファクタリング会社に送金する」という行為が、見た目上、融資の返済と非常によく似ているからです。
実際にあったトラブル事例
建設業を営むA社は、2社間ファクタリングで得た資金で急場をしのぎました。
しかし、後日、売掛先から入金された売掛金を「これは自社の売上だ」という感覚で、別の仕入れ代金の支払いに充ててしまったのです。
A社の社長に悪気はなかったのですが、これは明確な契約違反であり、ファクタリング会社との間で大きなトラブルに発展してしまいました。
このA社のように、売却して既にお金を受け取っているにもかかわらず、手元に入金されたことで自分の資金だと錯覚してしまうケースは、残念ながら少なくありません。
2社間ファクタリングを利用する場合、「売掛先から入金されたお金は、既にファクタリング会社のものであり、自社はそれを預かって送金するだけ」という意識を徹底することが極めて重要です。
ファクタリングの支払期日はいつ?契約形態別の期日一覧
では、その「支払い」は、具体的にいつまでに行う必要があるのでしょうか。
これも契約形態によって異なります。
2社間ファクタリングの支払期日:原則「売掛金の入金日」
2社間ファクタリングの場合、支払期日は「売掛先から貴社の口座に売掛金が入金された日」に設定されるのが一般的です。
契約書には、以下のように記載されていることが多いでしょう。
- 「売掛金の支払期日当日」
- 「売掛金の支払期日の翌営業日以内」
これは非常に重要です。
例えば、売掛金の入金日が25日であれば、その25日当日か、遅くとも26日までにはファクタリング会社に支払う必要がある、ということです。
手元にお金が入るからといって、数日間プールできるわけではないことを、肝に銘じておいてください。
3社間ファクタリングの場合:利用者の「支払期日」は存在しない
前述の通り、3社間ファクタリングでは売掛先が直接ファクタリング会社に支払いを行います。
そのため、貴社(利用者)にとっての「支払期日」というものは存在しません。
これにより、貴社は回収や送金の手間から解放され、使い込みなどのリスクも完全にゼロになります。
業務負担やリスク管理の面では、3社間ファクタリングに大きなメリットがあると言えます。
平均的な「返済期間(支払いサイト)」はどのくらい?
「返済期間」というキーワードで検索される方も多いですが、正しくは売掛債権の「支払いサイト」(売上発生から入金までの期間)を指します。



ファクタリングで取り扱われる売掛債権の支払いサイトは、30日〜60日程度が最も一般的です。
私が銀行やファクタリング会社で見てきた経験上、業種によっても傾向があります。
- 運送業・IT業など: 30日〜45日サイトが比較的多い。
- 建設業・製造業など: 60日〜90日、場合によっては120日といった長期のサイトも存在する。
ファクタリング会社は、この支払いサイトが長くなるほど未回収リスクが高まると判断するため、手数料が上がる傾向にあることも覚えておきましょう。
支払いが遅延する主な原因と、その深刻なリスク
もし、ファクタリング会社への支払いが遅れてしまったら、一体どうなるのでしょうか。
ここでは、私が現場で見てきたリアルな原因と、その先に待つ深刻なリスクについてお話しします。
【現場のリアル】遅延の二大原因:①使い込み と ②売掛先の支払い遅延
ファクタリング会社への支払いが遅延する原因は、突き詰めるとほぼ次の2つに集約されます。
1. 回収した売掛金の使い込み
これが最も多く、そして最も深刻なケースです。
先ほどのA社の例のように、他の支払いや運転資金に充ててしまうパターンです。
これは単なる契約違反に留まらず、法的には「横領罪」に問われる可能性のある、極めて危険な行為です。
2. 売掛先からの入金遅延
売掛先の経営状況が悪化し、約束の期日までに入金がなかった、というケースです。
これ自体は貴社の責任ではありませんが、ファクタリング会社への支払いは遅延してしまいます。
どちらが原因であれ、支払いが遅れるという事実に変わりはありません。
そして、その先には厳しい現実が待っています。
遅延損害金の発生と、その利率の相場
支払いが1日でも遅れれば、契約に基づき「遅延損害金」が発生します。
仮に100万円の支払いが30日遅れた場合、
100万円 × 14.6% ÷ 365日 × 30日 = 約12,000円
の遅延損害金が加算される計算になります。
遅延が長引くほど、この負担は雪だるま式に増えていきます。
最悪のケース:債権譲渡通知、訴訟、そして刑事罰
遅延を放置した場合、事態はさらに深刻化します。
2社間ファクタリングで契約していた場合、ファクタリング会社は債権を保全するため、売掛先に対して「この売掛債権は、我々が譲り受けました」という債権譲渡通知を送付します。
これにより、売掛先にはファクタリングの利用が知られてしまいます。
それでも支払いが行われない場合、ファクタリング会社は法的措置に移行します。
回収金の支払いを求める損害賠償請求訴訟を起こされ、最終的には資産の差し押さえといった強制執行に至る可能性があります。
特に「使い込み」が悪質だと判断された場合、ファクタリング会社は横領罪や詐欺罪で警察に刑事告訴する可能性があります。
私が知るケースでも、実際に逮捕に至った経営者がいます。
こうなれば、会社の存続はもちろん、経営者個人の人生も破綻しかねません。



これは決して脅しではありません。
軽い気持ちでの遅延が、取り返しのつかない事態を招くという現実を、どうか知っておいてください。
万が一支払いが遅れそうな場合の正しい対処法
では、もし本当に支払いが遅れそうになったら、どうすればよいのでしょうか。
パニックになる必要はありません。正しい対処法を知っていれば、最悪の事態は回避できます。
絶対にやってはいけないこと:無断での遅延と虚偽の報告
まず、絶対にやってはいけないことからお伝えします。
それは、ファクタリング会社に連絡もせず、無断で支払いを遅らせることです。
私がファクタリング会社にいた時、これが最も担当者の心証を悪化させる行為でした。
電話にも出ず、メールも返信しない。
これは「意図的に逃げようとしている」と判断されても仕方ありません。
また、「売掛先からの入金が遅れていて…」などと、虚偽の報告をするのも絶対にやめてください。
ファクタリング会社は与信管理のプロです。裏付けを取れば、嘘はすぐに発覚します。
信頼関係が完全に崩壊し、即座に法的措置へ移行される可能性が非常に高くなります。
対処法①:遅延が判明した時点ですぐにファクタリング会社へ連絡・相談する
最も重要かつ唯一の正しい対処法は、遅延の可能性が判明した時点で、すぐにファクタリング会社の担当者に正直に連絡し、相談することです。
「申し訳ありません。実は売掛先の〇〇社からの入金が、先方の都合で1週間ほど遅れるとの連絡がありました。入金され次第、すぐにお支払いしますので、お待ちいただくことは可能でしょうか?」
このように、
- 正直に状況を説明する
- 原因を明確に伝える(証拠があれば尚良い)
- 支払い意思があることを示す
この3点を誠実に伝えれば、多くの真っ当なファクタリング会社は、鬼のような取り立てをすることはありません。
むしろ、支払い計画の変更など、一緒に解決策を考えてくれるはずです。
大切なのは、問題を一人で抱え込まず、パートナーとして相談することです。
対処法②:弁護士への相談を検討する
誠実に相談しているにもかかわらず、
- 法外な遅延損害金を請求された
- 威圧的な言動で取り立てをされた
- 会社や自宅に押しかけてきた
といった対応をされた場合、その業者は悪質な違法業者(ヤミ金)の可能性があります。
その際は、すぐに弁護士や警察に相談してください。
不当な要求に応じる必要は一切ありません。
専門家の力を借りて、毅然と対応することが重要です。
失敗しないための返済(支払い)計画と契約時のチェックポイント
最後に、そもそもこのようなトラブルに陥らないために、契約前と契約後に何をすべきか、元銀行員・ファクタリングのプロとしての視点からアドバイスします。
【元銀行員が解説】償還請求権(リコース)の有無は必ず確認する
これはファクタリング契約における最大のリスク管理ポイントです。
償還請求権なし(ノンリコース)
万が一、売掛先が倒産して売掛金が回収不能になっても、貴社はファクタリング会社に支払う義務を負いません。リスクはファクタリング会社が負担します。これが本来のファクタリングです。
償還請求権あり(ウィズリコース)
売掛先が倒産した場合、貴社が代わりにその金額を支払う義務を負います。これは実質的に、売掛債権を担保にした「融資」と同じです。
もし、貸金業登録をしていないファクタリング会社が「償還請求権あり」の契約を提示してきたら、それは貸金業法違反の違法業者(ヤミ金)です。
絶対に契約してはいけません。
契約書に「償還請求権」「リコース」といった文言がないか、必ず自分の目で確認してください。
詳しくは「ファクタリングの償還請求権とは?をわかりやすく解説!「あり」と「なし」では大違い」という記事も参考にしてください。
契約書で確認すべき3つの重要項目
私がファクタリング会社で商品開発に携わっていた経験から、最低限、以下の3点は契約書で必ず確認してください。
1. 手数料の内訳
手数料以外に、登記費用、印紙代、交通費など、どのような費用が別途かかるのか、総額でいくらになるのかを明確にしましょう。
2. 支払期日の定義
「売掛金入金日当日」なのか「翌営業日」なのか。具体的な期日の定義を確認し、認識のズレがないようにしましょう。
3. 遅延損害金の利率と上限
年率何パーセントなのか、上限は設定されているのかを確認します。ここが法外な利率になっていないかは、悪質業者を見抜くポイントにもなります。
資金繰り表を活用した支払い計画の立て方
銀行員時代、私は多くの中小企業に資金繰り表の作成を指導してきました。
これはファクタリングを利用する際にも極めて有効です。
難しく考える必要はありません。
エクセルで簡単な表を作り、
- いつ、どこから、いくら入金があるか(売掛金の入金予定)
- いつ、どこへ、いくら支払いがあるか(仕入、経費、ファクタリングへの支払い)
これを時系列で書き出すだけです。



特に、ファクタリングで現金化した売掛金の入金予定日と、ファクタリング会社への支払日を目立つように色分けしておくことをお勧めします。
こうすることで、入金された資金を「支払い用の資金」として明確に区別でき、うっかり使い込んでしまうリスクを大幅に減らすことができます。
よくある質問(FAQ)
ここでは、経営者の皆様からよくいただく質問について、私、山崎がお答えします。
Q: ファクタリングの支払いを分割にしてもらうことはできますか?
A: 元銀行員・ファクタリング会社経験者の山崎がお答えします。
結論から言うと、できません。
ファクタリングは融資ではないため、分割での支払いは法律上「貸付」にあたります。
もし分割払いを提案してくる業者がいれば、それは貸金業登録のない違法業者(ヤミ金)の可能性が極めて高いので、絶対に利用しないでください。
Q: 売掛先が倒産してしまいました。支払いはどうなりますか?
A: 契約書にある「償還請求権」の有無によって結論が全く異なります。
「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約であれば、売掛金が回収できなくても貴社に支払い義務はありません。これがファクタリングの大きなメリットです。
一方、「償還請求権あり(ウィズリコース)」の場合は、貴社が代わりに支払う義務を負います。
契約前に必ずこの点を確認してください。
Q: 回収した売掛金を、別の緊急支払いに充ててしまいました。どうすればよいですか?
A: 非常に危険な状況です。法的には横領罪に問われる可能性があります。
言い出しにくいかもしれませんが、事態が深刻化する前に、一刻も早くファクタリング会社に正直に事情を説明し、支払い計画を相談してください。
誠実な対応が、解決への唯一の道です。
Q: 支払いが遅れそうで相談した場合、手数料が上乗せされることはありますか?
A: 事前の相談によって手数料が上乗せされることは通常ありません。
むしろ、正直に相談することで、ペナルティである「遅延損害金」の発生を待ってもらえる可能性があります。
隠さずに早く相談することが、結果的に貴社の損失を最小限に抑えることに繋がります。
Q: 銀行融資の返済とファクタリングの支払い、遅延した場合どちらがより深刻ですか?
A: 元銀行員の視点からお答えすると、どちらも深刻ですが、性質が異なります。
銀行融資の遅延は信用情報機関に記録され(いわゆるブラックリスト)、今後のあらゆる借入が困難になります。
一方、2社間ファクタリングの支払いを意図的に行わないことは「横領」という刑事事件に発展するリスクがあります。
金額や状況にもよりますが、刑事罰のリスクがある分、ファクタリングの使い込みはより深刻な事態を招く可能性があると言えるでしょう。
まとめ
ファクタリングにおける「返済」とは、正しくは売掛先から回収した資金をファクタリング会社へ「支払う」行為です。
この仕組みを正しく理解し、特に2社間ファクタリングでは回収した資金を確実に保全することが、失敗を避ける最大の鍵となります。



元銀行員、そしてファクタリング業界の人間として、私が経営者の皆様に最もお伝えしたいのは、何よりも大切なのは「誠実さ」だということです。
資金繰りに悩む経営者の孤独やプレッシャーは、痛いほど分かります。
しかし、万が一支払いが遅れそうな場合でも、迅速かつ正直に相談すれば、多くのファクタリング会社はパートナーとして解決策を一緒に考えてくれます。
この記事で解説した計画の立て方や対処法を参考に、ファクタリングを貴社の健全な資金繰りのための強力なツールとして、ぜひ有効にご活用いただければ幸いです。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認


-300x300.jpg)