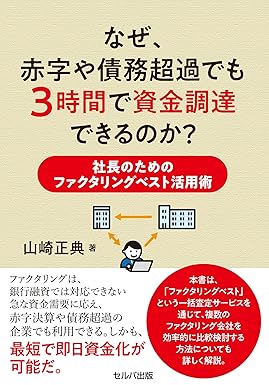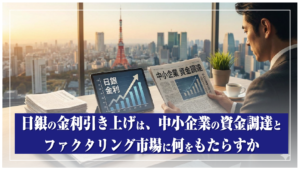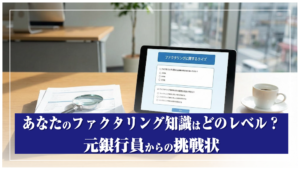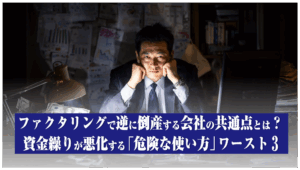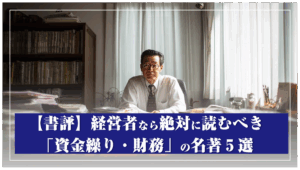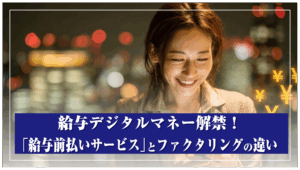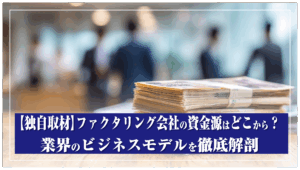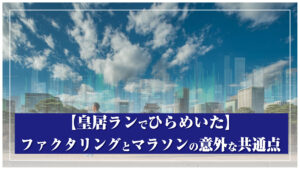元銀行員で、現在はファクタリングのプロとして活動する私、山崎正典は断言します。
M&Aの場面でファクタリングを安易に利用すると、良かれと思った一手で交渉が破談になるという最悪の事態を招きかねません。
「少しでも会社を高く売りたい」「買収後の運転資金を確保したい」…その切実な思い、痛いほどわかります。
しかし、その資金調達が、契約書に潜むたった一つの条項でディールそのものを吹き飛ばす「爆弾」になり得ることをご存知でしょうか?
ご安心ください。この記事では、私が銀行とファクタリング双方の現場で見てきた数々の事例に基づき、M&Aでファクタリングを利用する際の全リスクと、それを乗り越えるための具体的なチェックポイントを徹底解説します。
【この記事の結論】M&Aでのファクタリング利用 3つの鉄則
M&A(企業の合併・買収)の場面でファクタリングを安易に利用すると、交渉の破談につながる重大なリスクがあります。成功のためには、以下の3つのポイントを必ず押さえる必要があります。
- 鉄則1:安易な利用は「資金繰り悪化」のサインと見なされる
売り手側が財務改善(化粧)のために利用しても、買い手側からは「銀行融資を断られたのでは?」とデューデリジェンス(DD)で厳しく追及されます。合理的な説明ができない限り、企業価値のマイナス評価は避けられません。 - 鉄則2:デューデリジェンスで過去の利用は100%発覚する
ファクタリングの利用履歴は、通帳の入金履歴や決算書の「売上債権売却損」などの勘定科目から確実に把握されます。隠そうとせず、正直に開示し、利用理由を説明することが不可欠です。 - 鉄則3:最重要チェック項目は「COC条項」の有無
ファクタリング契約書にある「チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項」は、M&Aによる経営権の移動をトリガーに契約解除や即時返金を求められる可能性がある「爆弾」です。必ず弁護士に契約書を確認させ、必要であればファクタリング会社から事前の承諾を得てください。
M&Aにおけるファクタリングの基本的な関係性とは?
M&Aとファクタリング。
一見すると別々の金融取引ですが、実は企業の「資金」と「債権」という点で密接に結びついています。
M&Aのどの場面でファクタリングが活用されるのか
私が銀行員時代、融資が難しい局面で代替案としてファクタリングが検討されるケースは少なくありませんでした。M&Aの場面でも同様です。
- 【売り手側】財務状況の改善(化粧)
M&Aの直前、少しでも企業価値を高く見せるために、ファクタリングで売掛金を現金化し、キャッシュフローを良く見せたり、貸借対照表をスリム化(オフバランス化)したりするケースです。 - 【買い手側】買収後の運転資金確保
買収した事業を円滑に運営していくための運転資金として、買収対象企業が持つ売掛金を担保にファクタリングを利用するケースです。
しかし、これらの活用法には大きな落とし穴が潜んでいることを、まずは心に留めておいてください。
M&Aで扱うファクタリングの種類(2社間・3社間)とその影響
ファクタリングには大きく分けて2つの種類があり、M&Aにおける評価は全く異なります。
| 種類 | 仕組み | M&Aでの見え方(デューデリジェンス) |
|---|---|---|
| 3社間ファクタリング | 自社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で契約。売掛先に債権譲渡の通知・承諾を得る。 | 透明性が高く、取引の実在性が確認しやすいため、比較的ポジティブに評価されやすい。 |
| 2社間ファクタリング | 自社とファクタリング会社の2社間のみで契約。売掛先には通知しない。 | 売掛先に知られない手軽さがある一方、「なぜ取引先に知られたくないのか?」と買い手側から疑念を持たれやすい。二重譲渡などのリスクも懸念され、厳しくチェックされる。 |



特に2社間ファクタリングは、デューデリジェンス(DD)において、その必要性や背景を徹底的に問われることになるでしょう。
【売り手側】M&A前にファクタリングを利用するメリット・デメリット
会社を少しでも高く売りたい。その気持ちは経営者として当然です。
その手段としてファクタリングを検討する場合の光と影を見ていきましょう。
メリット:財務改善による企業価値向上
私が担当したある製造業のA社は、M&Aを前に大規模な受注があり、売掛金が急増しました。
手元の現金は少ないものの、将来性は高い。
このとき、受注した売掛金の一部をファクタリングで現金化し、キャッシュポジションを改善。
買い手側からは「キャッシュフローが潤沢で、財務が安定している」と評価され、当初の想定より高い価格での売却に成功しました。
このように、ファクタリングによって貸借対照表の売掛金(資産)が現金(資産)に変わることで、ROA(総資産利益率)などの財務指標が改善し、企業価値評価(バリュエーション)にプラスに働く可能性があります。
デメリット:高コストとデューデリジェンスでのマイナス評価
一方で、安易な利用は致命傷になりかねません。
利益の圧迫
ファクタリング手数料は融資の金利より高いため、利益を圧迫します。これは損益計算書を見れば一目瞭然であり、買い手は「収益性が低い」と判断する可能性があります。
資金繰り悪化の露呈
最も大きなリスクは、「銀行から借りられないほど資金繰りが厳しいのではないか?」というネガティブな印象を与えてしまうことです。
DDでは「なぜファクタリングが必要だったのか」を必ず問われます。ここで合理的な説明ができなければ、買い手の心証は一気に悪化し、買収価格の引き下げや、最悪の場合、交渉打ち切りの原因にもなります。
【買い手側】ファクタリング利用企業を買収する際のメリット・デメリット
次に、あなたが買収する側の立場だった場合です。
DDの過程で、対象企業がファクタリングを利用していることが発覚したら、どう考えますか?
メリット:売掛金の回収リスクの軽減
これは非常に限定的なケースですが、対象企業が「償還請求権なし(ノンリコース)」の3社間ファクタリングを利用している場合、売掛金の回収業務や貸し倒れリスクがファクタリング会社に移転しています。
買収後の債権管理の手間やリスクが軽減されている点は、小さなメリットと言えるかもしれません。
デメリット:簿外債務のリスクと潜在的な資金繰り問題
ファクタリング会社時代、あるIT企業B社の買収案件に関わったことがあります。
B社は2社間ファクタリングを利用していましたが、DDの過程でその事実が発覚。
買い手側はこれを「帳簿に載らない実質的な借金(簿外債務)」と判断しました。
さらに調査を進めると、B社は自転車操業状態で、ファクタリングで得た資金を別の支払いに充てていたことが判明。
この潜在的な資金繰り問題が決め手となり、買収交渉は白紙に戻りました。
このB社のケースのように、ファクタリングの利用は、買収後に引き継ぐことになる「隠れたリスク」のサインかもしれません。
買収後に同じ問題で苦しむことのないよう、その根本原因を徹底的に突き止める必要があります。
M&Aの成功を左右する!デューデリジェンス(DD)への影響とチェックポイント
DDは、M&Aにおける「身体検査」です。
ここでファクタリングの利用が発覚した場合、調査はより一層厳しくなります。
財務DD:売掛債権の実在性と簿外債務の特定
公認会計士や税理士は、プロの目で以下の点をチェックします。
- 【通帳履歴の精査】: ファクタリング会社からの入金がないか、不自然な入金がないか。
- 【勘定科目内訳明細書の確認】: 「売上債権売却損」などの科目が計上されていないか。
- 【売掛金の存在確認】: ファクタリングで譲渡済みの債権が、資産として二重計上されていないか。
- 【債権譲渡登記の確認】: 2社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記がされていないか。これは法務局で誰でも確認できます。
これらの調査から、ファクタリングの利用を隠し通すことは不可能です。
法務DD:契約内容と「チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項」の確認
財務DDと並行して、弁護士などの専門家はファクタリング会社との契約書を精査します。
ここで最も重要になるのが、次に解説する「COC条項」の存在です。
【最重要】チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項とは?M&Aにおける爆弾となりうる契約内容
この言葉を初めて聞く経営者の方も多いかもしれません。
しかし、M&Aを考えるなら絶対に知っておかなければならない、非常に重要な契約条項です。
COC条項の基本的な仕組みと目的
チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control)条項とは、
企業の支配権に重要な変更(例:株式譲渡による親会社の変更など)があった場合に、契約の相手方が、事前の通知や承認を求めたり、契約そのものを解除したりできる権利を定めた条項のことです。
これは、契約相手が「知らない会社」に変わってしまうことによるリスクを防ぐために、多くの契約書に盛り込まれています。
ファクタリング契約におけるCOC条項のリスク
もし、ファクタリング契約書にこのCOC条項が含まれていた場合、何が起こるでしょうか?
M&Aによってあなたの会社の株主が変わり、経営権が買い手に移った瞬間、COC条項が発動します。
ファクタリング会社は、その条項を根拠に「契約を解除するので、譲渡した売掛金の代金を即時に返済してください」と要求してくる可能性があるのです。
これは、M&A成立のまさにその日に、予期せぬ多額の資金流出が発生することを意味します。
買い手側からすれば、到底受け入れられる話ではありません。
このCOC条項の存在が、M&A交渉の最終段階で全てを白紙に戻す「ディールブレーカー」となり得ます。
M&A実行前に確認・交渉すべきこと
売り手・買い手双方が、DDの初期段階で必ずやるべきことがあります。
- 契約書の確認: ファクタリング契約書にCOC条項があるか、弁護士にレビューしてもらう。
- ファクタリング会社への事前交渉: もしCOC条項があれば、M&Aを実行することについて、事前にファクタリング会社から「承諾書(ウェーバー)」を取り付ける。
この事前交渉を怠ると、M&Aの成功はおぼつかなくなります。
よくある質問(FAQ)
Q: M&Aのデューデリジェンスで、過去のファクタリング利用は必ず発覚しますか?
A: はい、ほぼ100%発覚すると考えるべきです。財務デューデリジェンスでは、勘定科目内訳明細書や預金通帳の入出金履歴が精査されます。「売上債権売却損」などの勘定科目や、ファクタリング会社からの入金履歴から確実に把握されます。 隠そうとすることは信頼関係を著しく損なうため、正直に開示し、利用理由を合理的に説明することが重要です。
Q: 売り手側として、M&Aの直前にファクタリングで資金調調達するのは避けるべきでしょうか?
A: 一概には言えませんが、慎重な判断が求められます。緊急性のない資金調達であれば、買い手にネガティブな印象を与える可能性があるため避けた方が賢明でしょう。ただし、大型受注に伴う一時的な運転資金の確保など、事業成長に繋がるポジティブな理由がある場合は、その点を丁寧に説明することで理解を得られる可能性もあります。私としては、実行する前に必ずM&Aアドバイザーなどの専門家に相談すべきだと考えます。
Q: 買い手として、対象企業が2社間ファクタリングを利用している場合、特に注意すべき点は何ですか?
A: 2社間ファクタリングは売掛先に通知されないため、債権の二重譲渡といった詐欺的な取引のリスクが3社間より高いとされています。デューデリジェンスでは、債権譲渡登記の有無を確認するとともに、売掛債権の存在確認をより厳密に行う必要があります。また、売掛先との関係性が不透明な点もリスクとして認識し、なぜ3社間ではなく2社間を選択したのか、その背景を深く掘り下げるべきです。
Q: COC条項がファクタリング契約にない場合、M&Aをしても問題ありませんか?
A: COC条項がなければ、M&Aを理由に契約を解除される直接的なリスクは大幅に減少します。しかし、安心はできません。契約書に「譲渡禁止特約」など、他の関連条項がないかを総合的に確認することが不可欠です。法務デューデリジェンスにおいて、契約書全体を弁護士などの専門家がレビューすることが極めて重要です。
Q: M&Aの買収資金をファクタリングで調達することは可能ですか?
A: 理論上は可能ですが、一般的ではありません。ファクタリングはあくまで自社が持つ売掛債権を資金化する仕組みです。買収資金のような大規模な資金を調達するには、それに見合う巨額の売掛債権が必要となり、現実的ではないでしょう。私が銀行員だった頃の経験から言っても、M&Aの買収資金は、LBOローン(レバレッジド・バイアウト・ローン)といった専門的なファイナンス手法が用いられるのが通常です。
まとめ
M&Aの場面におけるファクタリングの利用は、短期的な資金繰り改善というメリットがある一方で、デューデリジェンスでの厳しい評価や、COC条項という取引の成否を左右しかねない重要なリスクを内包しています。
- 売り手にとっては、財務を良く見せる手段になり得ますが、その背景を厳しく問われることを覚悟せねばなりません。
- 買い手にとっては、将来の事業リスクを引き継ぐ可能性を意味します。



結論として、ファクタリングはM&Aのプロセスにおいて「諸刃の剣」となり得るのです。
安易に利用するのではなく、その影響を深く理解し、M&Aアドバイザーや弁護士、そして私のような金融実務の専門家に相談することが、M&Aという会社の未来を賭けた一大事業を成功に導く鍵となります。
資金繰りの悩みは、経営者にとって孤独な戦いです。
しかし、あなたは一人ではありません。
この記事が、あなたの会社の未来にとって、最善の選択をするための一助となれば、これに勝る喜びはありません。


⏱ 法人の資金繰り課題をスピード解決
┗ 最短3時間入金対応
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 厳選された優良ファクタリング会社のみ
【完全無料】「ファクタリングベスト」で最適な条件を今すぐ確認


-300x300.jpg)